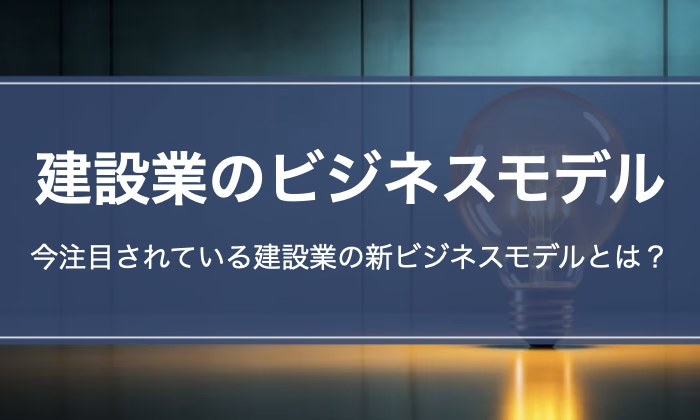建設業界では人手不足や価格競争の激化により、従来のビジネスモデルだけでは安定した経営が難しくなってきています。
そこで、今回は建設業界における新しいビジネスモデルの方向性や事例について解説します。
この記事を読めば時代に合った収益構造の作り方やビジネス転換のヒントがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業界の現状とビジネスモデルの必要性
建設業界は今、構造的な課題に直面しています。人手不足や利益率の低下といった問題が長期化し、従来の請負型ビジネスモデルでは限界が見え始めています。
ここでは、業界の現状を整理し、新たなビジネスモデルがなぜ必要とされているのかを明らかにします。
人手不足と高齢化による慢性的な労働力不足
建設業界では深刻な人手不足が続いています。
国土交通省の統計によると、建設業に従事する就業者のうち、55歳以上が約3割を占めており、29歳以下はわずか1割以下です。
若年層の入職が進まず、高齢化による退職が加速するなか、現場の人手は年々減少しています。
また、3K(きつい・汚い・危険)といわれる職場イメージや長時間労働・休日の少なさも、若手人材の確保を難しくしている要因です。
加えて、技能継承がうまくいかず、現場では熟練者が抜けたあとの技術的な空白も問題視されています。
このように、労働力確保の課題は慢性化しており、従来の人海戦術型モデルでは、今後の需要に対応できない可能性が高くなっています。
新しい技術の導入や業務プロセスの改革など、労働集約から脱却するビジネスモデルの構築が求められています。
利益率の低さと価格競争の激化
建設業界では、価格競争が年々激化しています。
公共工事や民間建築においても、元請けから下請け、さらに孫請けへと続く多重構造の中で、末端の業者に渡る報酬は極端に低くなりがちです。
そのため、請け負った仕事をこなしても十分な利益が得られないケースが珍しくありません。
さらに、資材価格や人件費の高騰により、利益率は圧迫され続けています。
しかし、価格転嫁が難しい業界構造の中で無理な価格競争を続けざるを得ず、結果的に経営体力を失う企業も少なくありません。
このような状況では単に案件を多く受注すれば良いという発想は通用せず、「選ばれる理由」を作るブランディングや独自性のある商品・サービス設計など、新たな付加価値を生み出すビジネスモデルへの転換が必要不可欠です。
従来の請負型モデルの限界
建設業界における主流のビジネスモデルは「請負型」です。
施主から仕事を受け、設計・施工・管理までを一括で請け負う形態が一般的でした。
しかしこのモデルには、近年になっていくつかの限界が明確になってきました。
まず、請負契約では「納期」と「予算」が厳格に定められ、それを守るために現場ではコスト削減や無理な工程調整が常態化しています。
その結果、現場の疲弊や品質低下、労災リスクの増加につながっています。
また、受注依存型のビジネスであるため、景気や発注者の都合に業績が左右されやすいという脆弱性もあります。
さらに、元請け・下請けの階層構造により利益分配が不公平になりやすく、現場を担う業者が正当な報酬を得られないことも多々あります。
こうした構造的な限界を打破するには、ストック型の収益構造や、サブスクリプション、アフターサービス型、地域密着型など、収益と信頼を長期的に得られる新しいモデルの導入が不可欠です。
建設業における従来のビジネスモデルの特徴
建設業界では、長年にわたり特有の商習慣と業界構造に基づいたビジネスモデルが定着してきました。
ここでは、従来の建設業における代表的な3つの特徴を通して、なぜ今このモデルが転換期を迎えているのかを明らかにします。
ゼネコン主導の多重下請け構造
建設業界における中心的な構造のひとつが、ゼネコン(総合建設業者)を頂点とした多重下請け構造です。
発注者(施主)から工事を一括で受注したゼネコンが、実際の施工は専門工事業者や職人に細分化して発注する形が一般的です。
このような多層構造により、現場の専門性や柔軟な対応が可能になる一方で、さまざまな弊害も生じています。
とくに問題となるのが「中抜き」と呼ばれるマージン構造で、下層に行くほど工事単価が下がり、実質的な工事を担う末端の職人や中小企業が圧迫される傾向があります。
また、情報の伝達が間接的になるため、設計意図や品質のズレ、工程の混乱を招きやすいという課題も見られます。
このような構造では現場力や技術力に優れた企業であっても自社ブランドや価格決定力を持ちにくく、業界全体としての生産性向上や魅力創出が困難になっています。
現場依存型の属人的な業務運営
建設業は、非常に現場依存の強い業種であり、その中でも特に属人的な運営体制が課題視されています。
工事の進捗管理や品質管理、安全対策など、多くの工程が「誰が現場を仕切るか」に大きく依存しており、マニュアルや仕組みよりも個人の経験や勘、判断力に頼る場面が少なくありません。
このような属人化された業務体制では、優秀な人材が現場を離れるだけで業務の品質が大きく変動し、組織的な再現性が担保されにくくなります。
また、デジタルツールの導入が遅れやすく、結果的に情報共有や工程管理の精度にも差が出てしまいます。
さらに、現場ごとに対応が異なるため、標準化が進まず会社としてのノウハウ蓄積やスケールメリットを活かしにくい構造となっている点も問題です。
これからの建設業にはITやBIM、クラウド管理の活用など属人性から脱却し、誰が担当しても一定以上の品質と効率が保てる仕組みづくりが不可欠です。
資材価格変動や天候リスクに左右されやすい収益構造
建設業の収益構造は非常に不安定で、資材価格の高騰や天候による工期の遅延といった外的要因に強く影響されます。
たとえば、鉄や木材、コンクリートといった主要資材の価格は、為替や国際情勢、災害などによって大きく変動するため、予算の見積もりが困難になります。
実際に、契約時の見積もりと実際の仕入れ価格に乖離が生じ、利益が大幅に削られる事例も少なくありません。
また、建設工事は天候にも大きく左右される業種です。
長雨や台風、積雪などによって工程が遅延すると、追加の人件費や仮設費が発生し、予期しないコスト増加につながります。
にもかかわらず、多くの請負契約では天候リスクに対する補償が十分に盛り込まれておらず、業者側がそのリスクを負うケースが一般的です。
こうした外的要因に対する脆弱性を減らすには、原価管理の高度化や資材価格を可視化するシステムの導入、天候に左右されにくい施工方法や工程管理の工夫が求められます。
また、請負型だけでなく、リース型・保守契約型など、継続的な収益を確保できる新たなモデルを組み合わせることも検討すべきでしょう。
今注目されている建設業の新ビジネスモデル
従来型の請負構造に限界が見える中、建設業界では新たなビジネスモデルが注目されています。
ここでは、利益率改善・生産性向上・継続的収益の確保に貢献する4つの注目モデルを紹介します。
内製化と少数精鋭で利益率を上げるモデル
多重下請け構造による「中抜き」が収益を圧迫してきた建設業界では、工程の一部または全部を自社で内製化する動きが広がっています。
たとえば、設計・施工・管理の一部を社内チームで担うことで、外注コストを削減しつつ、品質と納期のコントロールを強化できます。
これにより、利益率の向上と、顧客満足度の同時達成が可能になるのです。
特に中小規模の工務店や設計施工一体型の企業では、少数精鋭によるチーム体制の強化がカギとなっています。
業務を標準化・マニュアル化し、属人性を排除しつつ、専門スキルを持つスタッフに集中投資することで、効率的なプロジェクト運営を実現することが可能です。
人材の確保が難しい時代だからこそ、「人数」ではなく「スキル」と「仕組み」で勝負する体制づくりが注目されています。
建築×テクノロジー(BIM/クラウド管理/AI活用)
建設業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せており、BIM(Building Information Modeling)やクラウド型プロジェクト管理ツール、さらにはAIによる業務最適化が導入されています。
これらの技術は業務の可視化・標準化・高速化を実現し、従来の「人力依存型」からの脱却を可能にします。
BIMを活用すれば、設計段階から施工、維持管理に至るまで建物情報を一元管理できるため、設計ミスや施工トラブルを未然に防ぐことができます。
また、クラウド管理ツールによって、現場と事務所間の情報共有がリアルタイムで行えるようになり、意思決定のスピードも格段に向上します。
さらに、AIを活用した工程予測や原価管理の自動化は、人的ミスの削減や業務効率の大幅な改善に貢献しています。
こうしたテクノロジーの導入は「建設業=アナログ」というイメージを打破し、若手人材の採用にも効果的なアピール材料になります。
設計から施工・維持管理まで一貫請負モデル
従来は分業が主流だった建設業務ですが、近年では「設計・施工・維持管理」をワンストップで提供する一貫請負モデルに注目が集まっています。
このモデルは、施主側にとっては窓口が一本化されることで負担が減り、事業者側にとってはリピートやメンテナンス契約といった継続案件に発展しやすくなるというメリットがあります。
一貫請負によって、プロジェクト全体の品質管理やコスト管理がしやすくなり、途中での仕様変更やトラブル対応にも柔軟に対応できる体制が整います。
さらに、建物のライフサイクル全体を見越した設計や施工が可能となるため、より合理的かつ持続可能な建築が実現されます。
このモデルは、特に法人向け施設や医療・福祉・教育関連施設など、長期的なメンテナンスが必要な建物で高い評価を得ており、今後さらに導入が加速すると考えられています。
ストック型収益を生む「建物のサブスク・保守契約」
建設業の最大の課題のひとつが、「案件が完了すれば収益も終了する」というフロー型ビジネスに依存している点です。
そこで近年注目されているのが、建物のサブスクリプションや保守契約によるストック型収益モデルです。
たとえば、建物完成後も、定期点検・メンテナンス・修繕を月額制や年契約で提供することで、安定的かつ継続的な収益を確保できます。
また、IoT技術を活用した遠隔監視や劣化予測などと組み合わせれば、効率的な維持管理と付加価値の高いサービスが可能になります。
このモデルは、顧客にとっても「建てた後の安心」が得られるため、契約率の向上や顧客満足度の維持にもつながります。
短期的な利益だけでなく、長期的な企業の経営安定を実現するうえで、今後の建設業に不可欠なビジネスモデルといえるでしょう。
自社に合ったビジネスモデル構築の考え方
持続可能な経営を実現するには、自社の状況に応じたビジネスモデルを設計することが不可欠です。
そのためには、自社の強みや地域性を踏まえたうえで、業務プロセスや外部との連携を見直す視点が求められます。
自社の強みと地域ニーズの把握
ビジネスモデルを構築するうえでの第一歩は、「自社の強み」と「地域ニーズ」の正確な把握です。
たとえば、施工力の高さ、地元での信頼、特殊な工法への対応力といった技術的・人的な強みを棚卸しすることが必要です。
これらの資源を活かせる市場やニーズがどこにあるかを分析することで、無理のない戦略が描けます。
また、地域の人口動態や気候、行政の補助金制度なども重要な判断材料となります。
たとえば、高齢化が進むエリアであれば、バリアフリー改修や小規模修繕といった需要が安定して見込める可能性があります。
自社の「できること」と地域の「求められていること」が重なる部分を明確にし、そこを軸にビジネスを組み立てることが、再現性のあるモデルを生む鍵となります。
業務プロセスの見直しと内製化の検討
次に重要なのが、既存の業務プロセスの棚卸しと、内製化の可能性を含めた見直しです。
建設業は多くの工程を外注化しているケースが一般的ですが、その結果、品質管理のばらつきや原価の不透明さ、工程の遅れといった問題が生じやすくなります。
そこで、たとえば設計部門やアフター対応部門を内製化することで、品質の均一化と迅速な対応力を確保することが可能になります。
もちろん、すべてを自社で抱え込むのではなく、コア業務とノンコア業務を明確に分け、自社で行うべき領域と外部委託すべき領域のバランスを最適化することが肝心です。
さらに、内製化によって生まれるデータの蓄積やナレッジの共有は、社員教育や技術継承にもつながります。
これにより、中長期的に競争優位性を築くことができ、ビジネスモデルとしての安定性も高まります。
パートナーとの連携による新たな価値創出
自社単独での成長には限界があるため、ビジネスモデルの構築においては、外部パートナーとの連携も欠かせません。
たとえば、設計事務所や不動産会社、IT企業などとの協業によって、単なる「施工業者」ではなく「提案型ビルダー」としての立ち位置を確立することができます。
具体的には、設計事務所との共同ブランド開発、不動産会社とのリノベーション付き物件販売、IT企業とのスマートホーム開発など、パートナーの専門性を取り入れることで、新しいサービスや収益モデルを生み出すことが可能になります。
こうした連携は、単に業務の拡大にとどまらず、顧客体験の向上やブランディング強化にもつながります。
重要なのは、自社のリソースではカバーできない価値を外部から補完し、共創的なビジネスモデルを組み上げていく発想です。
競争から共創への転換が、これからの建設業界に求められる姿勢といえるでしょう。
まとめ
今回の記事では、建設業のビジネスモデルについて解説しました。
従来型のモデルに固執していると、収益性や競争力の低下を招きかねません。自社の強みや地域ニーズに合ったモデルを見直し、時代に即した変革を進めましょう。