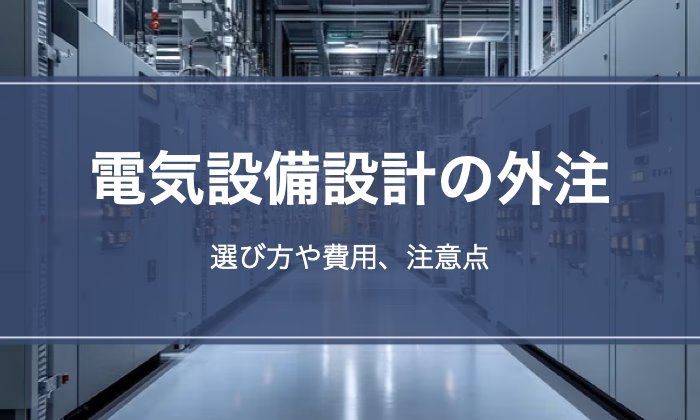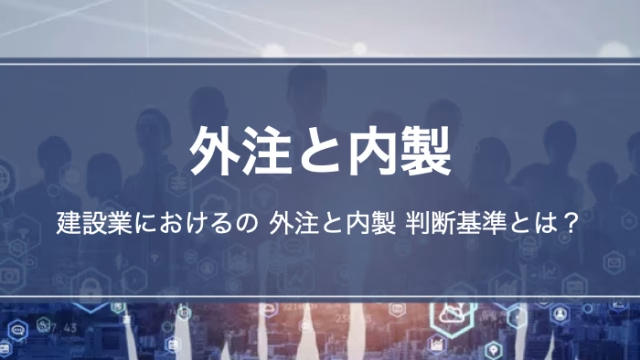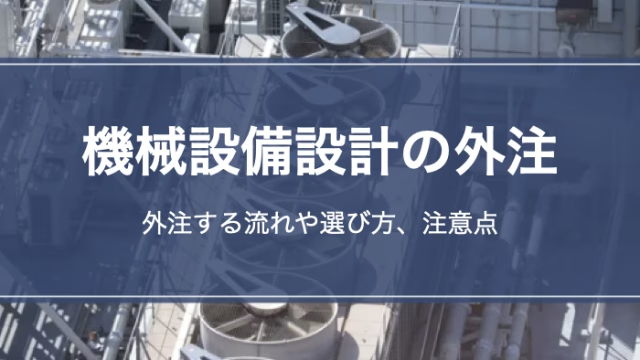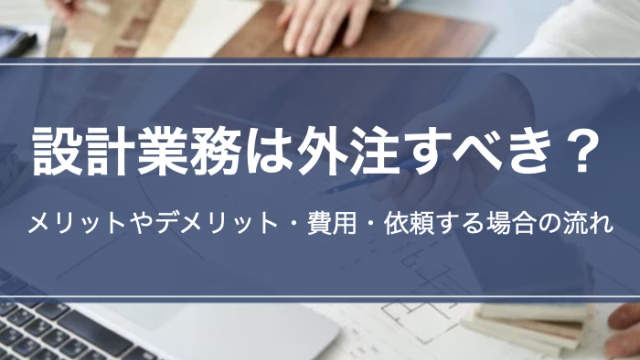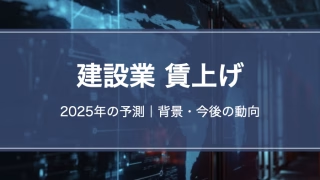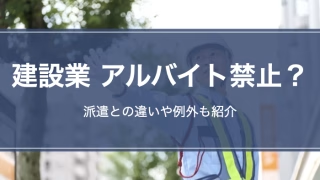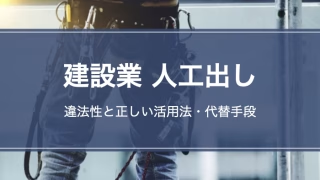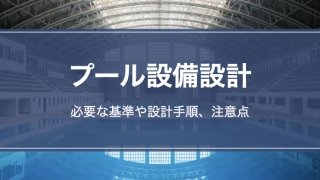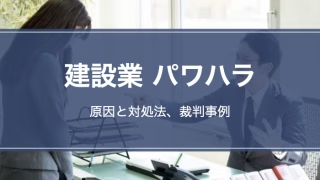「電気設備設計をどこまで依頼すればいいのか迷う」そんな悩みを抱えていませんか?
そこで、今回は電気設備設計を外注する際の費用相場と注意点、信頼できる設計者の選び方について解説します。
この記事を読めば、設計費の妥当性や契約前に確認すべき業務範囲、見積書の見方がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気設備設計を外注するメリット・デメリット
電気設備設計の外注には、専門性の確保や社内リソースの有効活用といった大きな利点がある一方で、業務のすり合わせ不足によるトラブルや品質のバラつきといったリスクも伴います。
ここでは、メリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説し、外注成功のためのポイントを整理します。
外注する3つのメリット(専門性・リソース確保・品質)
電気設備設計を外注する最大のメリットは、高度な専門性をスピーディに活用できる点です。
受変電設備や避雷設備、省エネ法対応など、高度な知識が求められる領域も、実績のある設計者であれば安心して任せられます。
また、社内の人手が不足していても、外部に委託することでリソース不足を補うことができ、繁忙期や突発案件にも柔軟に対応可能です。
これにより、自社の負担を抑えつつ、業務を効率よく進められます。
さらに、経験豊富な外注先であれば、図面の精度や納品スピードも安定し、社内での設計作業に比べてトラブルが少なく、品質の高い成果物を得やすくなります。
こうした理由から、特に公共案件や大規模施設の設計では、外注の活用が進んでいます。
外注で注意すべきリスクとその回避策
電気設備設計を外注する際には、いくつかのリスクに注意が必要です。
特に多いのが、設計意図の共有不足によるミスや、想定外の追加費用の発生です。
設計者との打合せが不十分なまま業務が進むと、図面の方向性がずれてしまい、後から修正や再設計が必要になることがあります。
また、設計変更への柔軟性が乏しい外注先では、急な仕様変更に対応できず、納期やコストに悪影響を及ぼすケースも少なくありません。
さらに、価格だけで業者を選んでしまうと、品質のばらつきが大きくなる恐れもあります。
これらを回避するためには、業務開始前に「業務範囲・成果物・対応内容」を明文化し、見積書の中身を具体的に確認することが重要です。
特に、打合せ回数や成果物の形式、追加費用の条件などを事前にすり合わせておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
成功のカギは「信頼できる設計者」と「業務範囲の明確化」
電気設備設計を外注して成功するかどうかは、信頼できる設計者を選ぶことと、業務範囲を明確にすることにかかっています。
まず、設計者の選定では、過去の実績、対応分野、図面のサンプルなどを確認し、自社の案件に合った専門性を持っているかを見極める必要があります。
また、単に価格の安さで判断するのではなく、「どこまで対応してくれるのか」「柔軟に対応できるのか」といった実務力とコミュニケーション力も重視しましょう。
業務範囲については、基本設計・実施設計・監理対応など、工程ごとの業務を分けて契約することで、責任の所在や対応範囲が曖昧になるのを防げます。
さらに、成果物の納品形式(CAD、PDF、BIMなど)や納期、設計変更時の対応条件も明文化しておくと安心です。
こうした準備を徹底することで、外注先と信頼関係を築き、設計業務を円滑に進めることができます。
電気設備設計の外注費用の目安と算出方法
電気設備設計を外注する際の費用は、建物の用途や規模、業務範囲によって大きく異なります。
ここでは、公共案件における工事費比例方式や、民間案件で用いられる費用算定方法、さらに戸建住宅など小規模案件の具体的な相場感について詳しく解説します。
工事費比例方式とは?公共案件での算定基準
公共施設における電気設備設計費は、国土交通省が定める積算基準や設計業務ガイドラインに基づき、「工事費に対する一定の割合」で算出されるのが一般的です。これが「工事費比例方式」と呼ばれる考え方です。
たとえば、建物の総工事費が1億円の場合、電気設備設計の委託費用は工事費の約3〜7%が目安とされ、300万〜700万円程度となります。
工事費が大きくなれば設計費も比例して高くなりますが、設計業務の密度や内容によってこの比率は変動します。
この方式のメリットは、案件の規模に応じた適正な設計費を算出しやすい点です。
特に小中学校、庁舎、病院などの公共建築物では広く用いられ、建築設計と同様に、設備設計も分離発注されるケースが多く見られます。
また、「設計業務委託等技術者単価表」や「建築設計標準業務量ガイドライン」も費用の裏付けとして活用され、信頼性の高い算出根拠となっています。
民間案件での費用の決め方(工数/成果物単位)
民間の電気設備設計業務では、公共案件のように明確な積算基準が存在しないため、設計者や設計事務所によって費用の決め方が異なります。
一般的には以下の3つの方式が主流です。
1つ目は「工事費比例方式」で、設備工事費の3〜5%を設計費とする方法です。
中規模ビルや集合住宅などでよく採用され、建築設計とは別に設備設計を外注する際に使われます。
2つ目は「工数ベースの積算方式」で、設計技術者の時給(例:5,500〜8,000円)に作業時間を掛けて算出します。
作業時間の根拠が必要ですが、業務内容が明確な場合には合理的な方法です。
3つ目は「成果物単位での固定報酬方式」で、たとえば「照明・配線図一式で●万円」「負荷計算+盤図作成で●万円」といった形で契約されます。
こちらは小規模案件やスポット業務に多く見られ、金額の明確さがメリットです。
いずれの方式でも、契約前に業務範囲と成果物内容をしっかりすり合わせておくことが、追加費用の発生を防ぐカギとなります。
戸建住宅・中小規模施設の費用相場
戸建住宅や小規模テナント、事務所などの電気設備設計を外注する場合、業務内容に応じて比較的シンプルな費用設定がされることが一般的です。
たとえば、30〜50坪程度の戸建住宅で、照明・コンセント・配線計画に加え分電盤図作成を依頼する場合、相場は15万円〜50万円程度が目安です。
住宅リノベーションでは10万〜30万円、店舗・事務所では20万〜80万円程度が実務的な範囲です。
ただし、費用はあくまで目安であり、対応が必要な項目が増えると価格も上昇します。
たとえばZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)対応やBIMデータ作成、照度シミュレーションなど、高度な業務を含む場合は追加料金が発生することもあります。
このような小規模案件においては、見積の内容が「一式」でまとめられていることも多く、設計の成果物・打合せの回数・納品形式などを事前に確認し、曖昧な点をなくしておくことがトラブル回避のポイントです。
コストだけでなく、業務の対応力や設計品質にも着目することで、適正な費用で満足度の高い外注が可能になります。
見積書で確認すべき業務範囲と注意点
電気設備設計を外注する際は、見積書の金額だけで判断するのではなく、業務範囲や成果物の内容、追加費用の条件などもあわせて確認することが重要です。
ここでは、見積書で確認すべき具体的なポイントと注意点について詳しく解説します。
業務範囲のチェックポイント5選
電気設備設計の見積書では、単に金額を確認するだけでなく、「どこまで対応してもらえるのか」という業務範囲の明確化が不可欠です。
特に注目したいのが次の5つのポイントです。
◆業務範囲のチェックポイント5選
- 設計フェーズの明示:基本設計、実施設計、申請図面、監理対応など、どの段階まで対応するかを確認しましょう。
- 図面枚数・種類の内訳:「照明平面図2枚」「系統図1枚」といった成果物の具体的な数と種類が記載されているかをチェックします。
- 打合せ・修正の回数制限:何回まで打合せが可能か、設計修正は何度まで無料かといった制限があるかを確認します。
- 納品形式の指定:PDF、CAD、BIMなど、成果物の納品形式が自社の要望と合っているかを見ておきましょう。
- 申請対応の有無:確認申請や法令対応の資料作成が見積に含まれているかどうかも見逃せないポイントです。
これらの項目が曖昧なままだと、業務の途中で「ここまでは含まれていない」といった認識のズレが生じやすくなります。
明文化された見積書をもとに、事前のすり合わせを丁寧に行うことが成功の第一歩です。
追加費用が発生しやすいパターンとは?
電気設備設計の外注において、想定外の追加費用が発生するケースは少なくありません。
これらは事前に見積書で回避できることも多く、リスクの理解が欠かせません。
まず多いのが、設計変更の回数超過です。
見積では「設計修正2回まで」など制限が設けられていることが多く、それを超えると追加料金が発生します。
仕様の変更や施主からの要望変更があった場合は特に注意が必要です。
次に、成果物の追加要求も費用増加の要因になります。
当初予定していなかった配線図や機器リストの作成などを後から依頼すると、都度追加費がかかります。
さらに、設計期間の延長も見逃せません。
納期が長引いた場合、再打合せや修正対応の手間が増えるため、時間的な追加請求が発生することもあります。
また、申請業務や法令対応が別料金になっている場合も要注意です。
最初の見積には含まれておらず、後から「確認申請は別途費用です」と言われることがあります。
こうしたリスクを避けるためにも、見積書には「追加費用の発生条件」を明記してもらい、想定できるケースを事前に洗い出しておくことが大切です。
見積だけでなく「成果物の内容」にも注目
設計業務の見積書では、価格や工数だけに目を向けがちですが、「どんな成果物が納品されるのか」という中身にも注目することが重要です。
成果物の内容次第で、設計の品質や後工程のスムーズさが大きく変わります。
たとえば、納品物が「照明・コンセント配置図一式」とだけ記載されている場合、それがどの範囲をカバーしているのか、どの程度の精度で作成されているのかは明確ではありません。
照明のスイッチ回路図や系統図が含まれていなければ、後からの修正対応が必要になることもあります。
また、BIM対応の有無やデータ形式(Revit、DWG、PDFなど)も成果物として明記されているかが重要です。
とくにゼネコンや建築設計側との連携が求められる場合、フォーマットの互換性は大きなポイントとなります。
さらに、成果物の納品基準(図面の解像度、凡例・注記の記載有無、色分けなど)も設計の質に直結する部分です。
これらが曖昧なままだと、納品後の手直しや再依頼につながる可能性があります。
そのため、見積書には「どのような成果物が、どのフォーマットで、何点納品されるのか」を具体的に記載してもらい、期待している成果とズレがないかを必ず確認しましょう。
価格と内容が見合っているかを見極める目を持つことが、良質な設計外注につながります。
信頼できる電気設備設計者の選び方
電気設備設計の外注で成功するかどうかは、設計者の力量と信頼性に大きく左右されます。
ここでは、実績や対応力を見極めるチェックポイントや初回打ち合わせで確認すべき質問、長期的な関係構築に必要な視点を具体的に解説します。
実績・対応力・図面の質を見るチェックリスト
信頼できる電気設備設計者を選ぶ際は、以下のような具体的なチェックリストを活用すると判断がしやすくなります。
まず最初に確認したいのは「過去の実績」です。
依頼する建物と同等規模・同種用途の案件を経験しているか、写真や図面などで確認しましょう。
似たようなプロジェクトでの実績があれば、業務内容や課題を理解してもらいやすくなります。
次に「図面のクオリティ」も非常に重要です。
過去に作成した照明図・配線図・系統図などのサンプルを見せてもらい、図面の見やすさや凡例の整備、法令への対応など、設計スキルの高さを確認します。
さらに「対応力」も見逃せません。
問い合わせへのレスポンスが早いか、質問に対して的確に答えてくれるか、打ち合わせの記録を残してくれるかなど、業務の進めやすさに直結するポイントです。
これらを総合的に確認することで業務範囲だけでなく、信頼関係を築けるかどうかの判断がしやすくなります。
初回ヒアリング時に確認すべき質問例
初回の打ち合わせではただ相手の話を聞くだけでなく、こちらからも積極的に質問することで、設計者の対応力や知識レベルを見極めることができます。
以下に、実際に確認すべき質問例を紹介します。
◆初回ヒアリング時に確認すべき質問例
「過去に対応された案件で、○○に近いものはありますか?」
→自社の建物と似た条件での実績があるかを確認。
「省エネ法や防災基準などの法令対応は、どのように対応されていますか?」
→法的な知識や更新情報への対応力を見る。
「納品物はどのような形式(CAD、PDF、Revitなど)になりますか?」
→成果物のフォーマットやBIM対応の有無をチェック。
「修正対応や追加設計が必要になった場合、どのような条件で対応いただけますか?」
→柔軟な対応が可能か、追加費用の発生条件も含めて明確にします。
「こちらからの要望を、設計図面にどのように反映してもらえますか?」
→ヒアリング内容を図面に落とし込む力を確認。
これらの質問に対して、曖昧な返答をせず、具体的に説明できるかどうかが判断材料となります。
聞きにくい内容ほど、事前に聞いておくことで後のトラブルを防ぐことができます。
提案力・対応力は長期的な信頼につながる
外注先としての電気設備設計者に求められるのは単なる「依頼された業務をこなす人」ではなく、自社の課題や目的を理解し、適切な解決策を提示できる「パートナー的存在」です。
そこで重要なのが、提案力と対応力です。
提案力のある設計者は法令やコスト、施工性を踏まえたうえで、最適な機器構成や配線ルートを提示してくれます。
依頼者が気づいていないリスクや改善ポイントを指摘してくれるなど、「プラスα」の視点を持っていることが信頼の証です。
また、対応力が高い設計者は、突発的な変更や確認申請のトラブルにも柔軟に対応でき、業務を中断させることなく前に進められます。
スケジュールや連絡面でのストレスが少ないという意味でも、設計品質に直接関係する能力です。
このような設計者とはプロジェクト単発にとどまらず、今後の継続的な案件でも安心して依頼できるようになります。
信頼関係を築くうえでも、「この人なら任せられる」と思える実力と姿勢を備えた相手を選ぶことが長期的に見て大きな価値をもたらします。
契約時に必ず確認したい6つの項目
電気設備設計を外注する際には金額や納期だけでなく、契約内容の詳細までしっかりと確認することが重要です。
ここでは後々のトラブルを防ぐために、契約時に確認すべき6つのポイントについて具体的に解説します。
設計業務範囲・納品形式・変更対応の明確化
契約書でまず押さえておきたいのは、「設計業務の範囲」「納品形式」「変更対応の条件」の3点です。
設計業務範囲ではどこまでを基本設計とし、どこからが実施設計になるのか、また、申請対応や監理業務が含まれるのかを具体的に明記しましょう。
「一式」といった曖昧な表現ではなく、業務の内容を詳細に記載することで、認識のズレを防げます。
納品形式については、PDF・CAD・Revitなどのファイル形式に加え、図面の枚数や内訳(照明図、配線図、系統図など)も文書化が必要です。
対応できない形式で納品されると、後の業務に支障が出る恐れがあります。
さらに設計変更への対応条件も重要です。
「設計変更は2回まで無料、それ以降は1回●円」など明確なルールを定めることで、追加費用の発生リスクを回避できます。
これら3点は、最もトラブルになりやすい要素のため、契約時点での明文化が必須です。
著作権や再委託禁止条項の取り扱い
設計に関連する知的財産の取り扱いや業務の実施体制も契約書の中で明確にしておくべき項目です。
まず、設計図面や計算書などの成果物に関する著作権・使用権の帰属については、「著作権は設計者に帰属するが、発注者は使用権を有する」といった文言で整理されることが一般的です。
BIMデータのように転用が想定される成果物の場合は、再利用の条件まで明記することが望ましいでしょう。
次に確認したいのが「再委託(下請け)」の可否です。
設計者が自ら業務を行うのか、外部のパートナーに再委託するのかによって、設計の品質や進行管理に大きく影響が出る場合があります。
「再委託を行う際は事前承諾を要する」や「再委託は一切禁止」といった条項を契約書に盛り込むことで、責任の所在を明確にできます。
これらの点を確認せずに進めてしまうと、「知らない外部スタッフが図面を作っていた」「成果物の再利用が制限された」といった事態になりかねません。
著作権と再委託については、信頼関係に依存せず、文書で合意を形成することが安全策となります。
瑕疵対応やアフターフォローも契約書に明記
設計業務においては、契約が完了して納品された後も思わぬ修正やトラブルが発生することがあります。
そのため、契約書には「瑕疵対応」や「アフターフォロー」の取り決めも明記しておくべきです。
瑕疵対応とは、設計ミスや計算誤りが発覚した場合に、無償で修正対応する期間のことです。
一般的には「納品後1ヶ月以内の無償修正対応」などの条項を設けますが、案件によっては3ヶ月など長めに設定することもあります。
これを記載しておかないと、修正対応を断られる、あるいは追加費用を求められる可能性があります。
アフターフォローについては、運用開始後の不具合確認や軽微な修正対応、問い合わせ対応などの範囲と条件を決めておくと安心です。
「メール問い合わせには原則3営業日以内に返答」「軽微な修正は納品後1ヶ月以内に1回まで対応」といった文言があれば、双方の期待値が一致しやすくなります。
設計業務は、成果物納品と同時に終わるものではありません。
トラブル時に責任の所在が曖昧にならないよう、事前に「アフター対応の範囲と条件」を合意しておくことで、信頼関係の維持と円滑なプロジェクト進行に繋がります。
まとめ
今回の記事では、電気設備設計の外注について解説しました。
費用や成果物の内容、契約条件まで細かく確認しないと、後でトラブルになることがあります。
外注する際は、信頼できる設計者かどうかを見極め、業務範囲を必ず文書で明確にしてから契約しましょう。
図面作成や機械設備設計、電気設備設計、自動制御設備設計、数量積算などの業務を外注したい、相談したいという方は以下のボタンをクリックしてお問い合わせページよりご連絡ください。