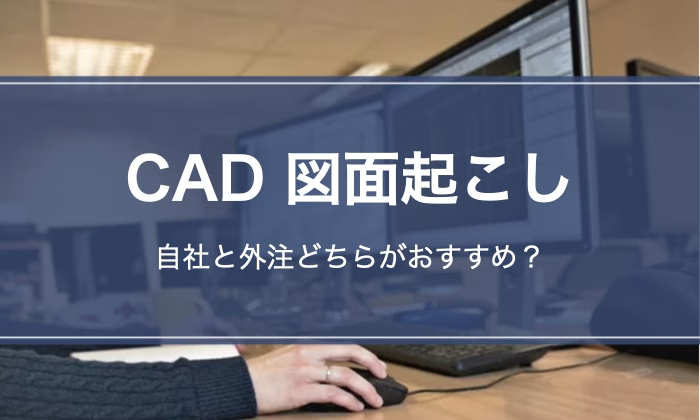「古い紙図面やPDFデータをCADできれいに図面起こししたいけれど、やり方や費用がわからない」といった悩みはありませんか?
そこで、今回はCAD図面起こしの基本や自分で行う方法、外注のメリット・デメリット、費用相場や依頼のコツについて解説します。
この記事を読めば図面起こしの全体像と、自社対応と外注の最適な使い分け方、失敗しない依頼方法がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
CAD図面起こしとは?トレースとの違いも解説
CAD図面起こしとは、紙図面やPDFのデータをCADソフト上で再作図し、精度の高いデータとして再構築する作業を指します。
トレースとの違いを正しく理解することで、適切な依頼や対応が可能になります。
ここでは、図面起こしの意味や具体的なシーン、CADトレースとの違いについて詳しく解説します。
図面起こしの意味(紙図面やPDFをCADデータ化)
図面起こしとは、既存の紙図面やPDFデータをCADソフトを使って再度作図し、編集可能なデータとして作り直す作業を指します。
例えば古い紙図面しか残っていない場合や、PDFしかデータが存在しない場合に、CADデータとして再構築することで、設計変更や施工に必要な修正を容易に行えるようになります。
紙図面をそのままスキャンしただけでは、線や寸法が画像データとして保存されるだけで修正できません。
一方、図面起こしでは、各要素を正確にCADの線や図形として作成するため、後工程での再利用がスムーズになります。
また、図面起こしは精度が求められる作業であり、測定誤差や情報欠落がある場合は現地確認や資料照合が必要です。
企業によっては社内で対応することもありますが、工数や技術的負担を考慮し、専門業者へ外注するケースも増えています。
CADトレースとの違い(作業範囲・目的・精度)
CADトレースも既存図面を基に作図を行う点では図面起こしと似ていますが、目的や作業範囲に違いがあります。
トレースは基本的に既存図面の輪郭や寸法をそのままCADに書き写す作業が中心で、図面の内容や構造を深く考慮しないケースが多いのが特徴です。
対して図面起こしは、図面の内容を理解し、不足情報を補完しながら精度の高いデータを再構築します。
具体的には、破損や欠落のある紙図面の寸法を現場で再計測して補完したり、古い規格の線種やレイヤー構成を現行ルールに合わせて修正したりする作業も含まれます。
こうした補完作業を行うことで、今後の設計や施工に直接活用できる高品質なCADデータが作成されます。
したがって、単なる写し作業を行うトレースよりも図面起こしは作業工数が多く、必要な知識や技術のレベルも高い傾向にあります。
図面起こしが必要になるシーン(既存建物・古い図面の再利用など)
図面起こしは、古い建物や設備の改修・メンテナンス時に必要となるケースが多く見られます。
例えば、建築物の改築や設備更新を計画する際、最新のCADデータがないと施工計画や部材発注に支障が出ます。
このような場合に紙図面やPDFを元に図面起こしを行うことで、正確な設計図面を再構築できます。
また、耐震補強や大規模修繕などの工事においても、既存構造の正確な把握が求められるため、現場測量と併用して図面起こしが実施されます。
さらに、企業の図面管理業務として古い紙図面をデジタル化し、今後の資産管理や設計データベースとして活用する目的でも需要があります。
以下は図面起こしが必要となる代表的なケースです。
| ケース | 目的 | 背景 |
|---|---|---|
| 既存建物の改築工事 | 正確な設計図面を再構築 | 紙図面しか残っていない |
| 設備更新や修繕 | 既存構造の正確な把握 | 古い図面の精度が低い |
| 資産管理用デジタル化 | 設計データベースの構築 | 過去図面を一元管理する必要がある |
こうしたシーンでは、図面起こしを行うことで業務効率や設計の精度が大きく向上します。
自分でCAD図面起こしを行う方法
CAD図面起こしは外注だけでなく、自分で対応することも可能です。
ここでは必要なソフト、具体的な作業手順、さらに自社対応のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
事前の準備や作業フローを理解しておくことで、効率的かつ精度の高い図面データ化が実現できます。
必要なソフト(AutoCAD・Jw_cad・DraftSightなど)
自分でCAD図面起こしを行うには、適切なCADソフトの選定が重要です。
代表的なのはAutoCAD、Jw_cad、DraftSightなどで、それぞれ特長や使いやすさが異なります。
AutoCADは世界的に最も利用されているソフトで、建築・製造・設備と幅広い業界で使える汎用性が強みです。
一方、Jw_cadは日本国内で広く普及しており、無料で利用できることから中小企業や個人利用者に人気です。
DraftSightはAutoCADと互換性の高い操作性が魅力で、低コストで導入できる点が特徴です。
これらのソフトには2D専用と3D対応版があり、作業する図面の内容に合わせて選ぶ必要があります。
また、スキャナや画像編集ソフトも併用すると作業効率が上がります。
ソフトを導入する際は、自社のPCスペックや業務で必要な図面形式(DWG、DXF、JWWなど)との互換性も確認しましょう。
作業の手順(スキャン→下書き→作図)
CAD図面起こしを自分で行う場合は、以下の手順で進めるのが基本です。
- 紙図面をスキャナで高解像度(300dpi以上推奨)でデジタル化します。
- スキャンしたデータをCADソフトに取り込み、参照画像として配置します。
- CAD上で参照画像に沿って線や図形をトレースし、寸法を正確に反映させながら作図します。
- レイヤー構成や線種・文字のサイズを業務ルールに合わせて整理します。
- 完成したデータを指定形式(DWG、JWW、PDFなど)で保存します。
作業の際は、元図面の寸法の誤差や欠落情報を補うため、現場での実測や設計者へのヒアリングを行うことも重要です。
メリット・デメリット(コスト・時間・精度の面から)
自分でCAD図面起こしを行う最大のメリットは、外注費用がかからない点です。
外部業者に依頼すると1枚数千円から数万円のコストが発生しますが、自社対応であればソフト代と作業時間だけで済みます。
また、外部とのやり取りが不要なため、情報漏えいのリスクを抑えられるのも利点です。
一方でデメリットもあります。CADソフトや作業スキルがない場合、学習コストがかかり、作業時間も大幅に増えます。
さらに、精度の高いデータを作成するには経験が必要で、誤差や情報不足によって業務に支障をきたすリスクもあります。
したがって、作業量が多い、または短納期が求められる場合は外注を検討した方が効率的です。
自社対応と外注の使い分けを明確にすることで、コストと精度のバランスを取りやすくなります。
CAD図面起こしを外注するメリットとデメリット
CAD図面起こしは、自社対応に比べて外注することで大きなメリットが得られますが、もちろんデメリットもあります。
ここでは、外注のメリットとデメリットを整理し、自社対応との使い分けのポイントを解説します。
外注のメリット(専門性・スピード・精度の高さ)
外注の最大のメリットは、高い専門性を持つスタッフに作業を任せられる点です。
CAD図面起こしは、図面の内容理解や精密な作業が必要であり、経験不足の社員が対応すると誤差や抜け漏れが発生しやすくなります。
外注先の業者は、建築・製造・設備など各業界に精通したCADオペレーターを抱えており、業務ルールや図面規格を踏まえた高品質なデータを作成してくれます。
また、外注は作業スピードの面でも有利です。
複数人の体制で対応できるため、短納期案件や大量の図面起こしが必要な場合にも効率的に進められます。
さらに、トレースや3D対応、BIM連携など、社内では対応が難しい高度な業務も依頼可能です。
結果として、社内リソースを設計や顧客対応などのコア業務に集中させられる点も大きな利点となります。
外注のデメリット(費用・依頼の手間・情報漏えいリスク)
外注のデメリットとしてまず挙げられるのは費用です。自社対応であれば人件費以外に大きなコストは発生しませんが、外注では1枚あたり数千円から数万円の料金がかかる場合があります。
難易度の高い図面や短納期対応ではさらにコストが増える傾向にもあるんです。
また、図面の使用目的や範囲、仕様を正確に伝える必要があるため、発注時に情報整理や打ち合わせが必要となり、指示が不十分だと手戻りが発生し、納期や費用が増えるリスクがあるため注意が必要です。
さらに、外注では情報管理の観点でも注意する必要があります。
建築計画や製品設計に関する機密情報が外部に流出する可能性があるため、信頼できる業者選定や秘密保持契約の締結が不可欠です。
こうしたリスクを把握し、対策を講じることが重要です。
自社対応と外注の使い分けポイント
自社対応と外注は、それぞれの特徴を理解して使い分けることで最も効率的に進められます。
例えば、枚数が少なく納期に余裕がある場合は自社で行い、短納期かつ大量の図面起こしが必要な場合や高精度が求められる案件は外注を活用するのが適しています。
また、専門性の高い図面(BIM対応や3Dモデル作成など)は外注に任せ、単純なトレース作業や小規模修正は自社対応にするなど、業務内容で分ける方法も有効です。
以下の表は使い分けの目安です。
| 状況 | 自社対応が適しているケース | 外注が適しているケース |
|---|---|---|
| 作業量・納期 | 少量で納期に余裕がある | 大量・短納期案件が必要 |
| 業務内容 | 簡単なトレースや修正作業 | BIM対応・3Dモデリングなど高度な作業 |
| コスト | コストを最小限に抑えたい | 高精度・スピード重視でコストをかけられる |
このように、案件の内容や状況に応じて自社対応と外注を併用することで、費用対効果を最大化しつつ業務の効率化が図れます。
CAD図面起こしの費用相場と料金を左右する要因
CAD図面起こしの費用は、図面の種類や難易度、依頼枚数、納期条件などによって大きく変動します。
ここでは、2D・3D図面の料金目安、1枚単価と時間単価の違い、さらに追加費用が発生しやすいケースについて詳しく解説します。
図面の種類・難易度別の料金目安(2D/3D)
CAD図面起こしの費用は、2D図面か3D図面かによって大きく異なります。
2D図面の場合、平面図や立面図など比較的単純な構成の図面は1枚3,000円〜10,000円程度が目安です。
構造図や詳細図など、情報量が多く精度が求められる図面は1枚15,000円以上になることもあります。
一方、3D図面は作業工程やスキルがより複雑になるため、1モデル50,000円以上が相場で、内容によっては10万円を超えるケースも珍しくありません。
以下に図面の種類別の料金目安をまとめます。
| 図面の種類 | 難易度 | 料金目安 |
|---|---|---|
| 2D平面図・立面図 | 低〜中 | 3,000〜10,000円/枚 |
| 2D詳細図・構造図 | 高 | 15,000円以上/枚 |
| 3Dモデリング(BIM含む) | 高 | 50,000〜100,000円/モデル |
このように、作業範囲や精度の高さが料金に直結します。
1枚単価・時間単価の違い
CAD図面起こしの料金は、1枚単価制と時間単価制のいずれかで提示されるケースが多く見られます。
1枚単価制は、図面1枚ごとにあらかじめ設定された料金が適用される方式で、費用が明確で予算管理がしやすい点がメリットです。
ただし、図面の内容が複雑で修正が多い場合、追加費用が発生する可能性があります。
一方、時間単価制は、作業にかかった時間に応じて費用が決まる方式で、相場は1時間あたり3,000〜5,000円程度です。
作業内容が不確定な場合や、依頼する図面の量が少ない場合には有効ですが、作業時間が予想以上にかかると費用が膨らむリスクもあります。
依頼する案件の規模や作業内容の確定度に応じて、適切な料金体系を選ぶことが重要です。
追加費用が発生するケース(修正回数・短納期・現地調査)
CAD図面起こしでは、基本料金のほかに追加費用が発生するケースがあります。
代表的なのは修正回数の超過です。多くの業者では2回程度までは無料対応ですが、3回目以降は1回あたり数千円〜の追加費用がかかる場合があります。
また、短納期対応を希望する場合も特急料金が発生するケースが多く、通常料金の1.2〜1.5倍になることもあります。
さらに、現地調査を伴う図面起こしでは、交通費や人件費が別途加算されるのが一般的です。
こうした追加費用は依頼前にしっかり確認しておかないと、想定以上の費用がかかる原因になります。
見積もり段階で修正ポリシーや特急料金の条件、現地調査の費用について明確にしておくことが重要です。
CAD図面起こしの外注先の選び方と比較ポイント
CAD図面起こしを外注する場合、業者選びは品質や納期に大きく影響します。
ここでは、対応ソフトや納品形式、納期や修正対応の柔軟性、さらに業界特化型業者を選ぶメリットについて解説します。
外注先の特徴を把握し、適切な比較基準を持つことが重要です。
対応できるソフト・納品データ形式で選ぶ
外注先を選ぶ際、まず確認すべきなのは使用可能なCADソフトと納品データ形式です。
建築や製造など業界によって使用ソフトが異なり、AutoCAD、Jw_cad、Revit、SolidWorksなどの中から適切なものを選ぶ必要があります。
依頼主が使用するソフトに対応できない外注先では、データの変換作業が必要になり、精度低下や納期遅延のリスクが高まります。
納品形式も重要なポイントです。DWG、DXF、JWW、PDFなど複数の形式に対応できる業者を選ぶと、後工程でのデータ活用がしやすくなります。
対応ソフトや形式は見積もり前に必ず確認し、必要であればサンプルデータの提供を依頼すると安心です。
納期・修正対応の柔軟性をチェック
CAD図面起こしの外注では、納期や修正対応の柔軟さも大切な比較基準です。
短納期案件や複数回の修正が想定される場合、業者が迅速に対応できる体制を持っているかどうかで業務効率が大きく変わります。
見積もり段階で初回納品までの期間だけでなく、修正対応のリードタイムや無料で対応してくれる修正回数も確認しておきましょう。
多くの業者は2回程度まで無料で対応しますが、それを超えると追加費用が発生する場合があります。
また、緊急時に特急対応が可能かどうかも重要です。
契約前に「どの程度のスピード対応ができるか」「休日や夜間の対応は可能か」を明確にしておくとトラブルを防げます。
建築・製造・設備など業界特化型を選ぶのも有効
CAD図面起こしは業界ごとに必要な知識やルールが異なるため、業界特化型の外注先を選ぶのも効果的です。
例えば建築分野では、建築基準法や施工図面の知識がある業者を選ぶことで、法的要件を満たした正確な図面を作成できます。
製造業向けであれば部品や製品図面の規格に詳しい業者が適しています。
業界特化型業者は専門知識を持つスタッフが多く、図面起こしの精度が向上するため、業界に合った業者を選定しましょう。
失敗しないCAD図面起こしの依頼方法
CAD図面起こしを外注する際は、情報整理や依頼内容の伝え方によって仕上がりの品質やコストが大きく変わります。
ここでは、発注前に準備しておくべき情報や依頼内容の伝え方のポイント、外注コストを抑える工夫について詳しく解説します。
発注前に準備すべき情報(元図面・仕様書・指示書)
CAD図面起こしの依頼をスムーズに進めるためには、発注前の情報整理が欠かせません。
最も重要なのは、元となる紙図面やPDFデータを正確に用意することです。
図面が不鮮明であったり情報が不足していると、外注先が正確なデータを作成できず、修正や追加の手間が増えてしまいます。
仕様書やレイヤー構成のルール、使用する図面フォーマット(DWG・JWW・PDFなど)も事前に整理しておくとよいでしょう。
可能であれば指示書を作成し、図面の目的や納期、注意点などを明記しておくと、依頼後の齟齬を防ぐことができます。
これらの資料を揃えることで、作業の精度が高まり納期短縮にもつながります。
依頼内容を明確に伝えるためのポイント
依頼内容が曖昧だと、外注先は意図を正確に把握できず、仕上がりの品質や納期に悪影響を及ぼします。
そのため、依頼時には図面の使用目的を明確に伝えることが大切です。
例えば「施工用図面として使用する」「申請用として提出する」など、用途をはっきりさせることで必要な精度や作業範囲が判断しやすくなります。
また、納期や優先順位、修正対応のルールも事前に共有しましょう。
曖昧な表現ではなく、数値や具体的な指示を使うことで外注先の理解度が高まります。
オンライン会議やチャットツールを使って質問や確認をリアルタイムに行える体制を整えるのも効果的です。
外注コストを抑える工夫(まとめ発注・依頼範囲の明確化)
CAD図面起こしの外注コストを抑えるには、発注方法を工夫することが有効です。
まず、複数の図面を一括で依頼する「まとめ発注」を行うと、ボリュームディスカウントを受けられるケースが多くあります。
また、作業範囲を明確に定義し、不要な工程を削減することも重要です。
例えば、レイヤーの細かい分類や3D化が不要であれば、その旨を伝えることで作業工数を減らせます。
さらに、初回依頼時に指示内容をできるだけ詳細にしておくことで修正回数を減らし、追加費用の発生を防ぐことが可能です。
見積もり段階で複数社を比較し、追加料金の発生条件や修正ポリシーも確認しておくと、予算超過のリスクを抑えられます。
まとめ
今回の記事では、CADの図面起こしについて解説しました。
まずは元図面や仕様を整理し、依頼内容を明確にしたうえで信頼できる外注先を選定しましょう。