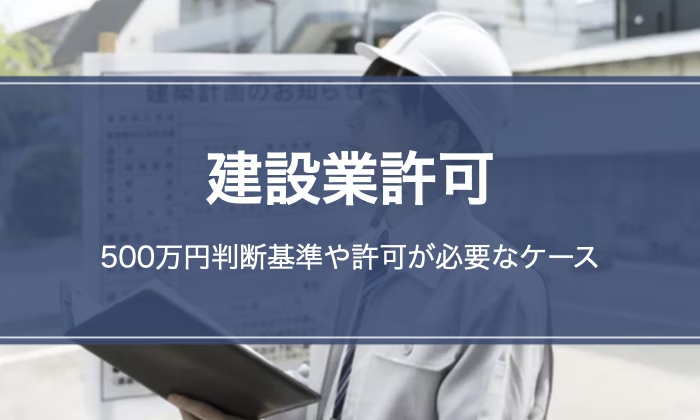「許可がなくても問題ない」と思っていたら、実は罰則の対象だった、そんな不安を抱えて検索されたのではないでしょうか。
そこで、今回は建設業許可が必要となる金額の基準や例外、違反時の罰則について解説します。
この記事を読めば、500万円の判断基準や許可が必要なケース、個人事業主が注意すべき点がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業許可が必要になる金額の目安とは
建設業許可が必要になるかどうかは「軽微な工事」に該当するかが判断基準となります。
一般的には請負金額500万円未満がその目安とされますが、解釈や計算方法によっては許可が必要になるケースもあります。
ここでは、建設業許可が必要となる金額基準や「500万円未満」という定義の正しい理解について解説します。
建設業許可が必要となる工事金額の基準
建設業法では、建設業許可が必要となる基準を「軽微な建設工事を除く」と定義しています。
軽微な建設工事とは、以下のように分類されます。
| 工事の種類 | 許可が不要な金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅 | いずれかを満たせば軽微な工事 |
| 建築一式工事以外(例:電気工事、塗装工事など) | 500万円未満 | 材料費・消費税を含む |
特に注意すべき点は、「500万円未満」とは「499万9,999円まで」であり、500万円ちょうどやそれ以上は対象外になるということです。
また、請負金額の中には「材料費」や「運搬費」、「消費税」も含まれるため、税抜き価格だけを見て判断するのは非常に危険です。
建設業許可がない場合、500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反となり、罰則の対象になります。
詳細は「建設業許可 罰則」にも関連する重要なポイントです。
「500万円未満」はあくまで軽微な工事の定義
「500万円未満だから許可はいらない」と考える方は多いですが、この定義はあくまで「軽微な工事」とみなされるかどうかの基準です。
実際には、以下のようなケースで軽微な工事の枠から外れる可能性があるため、正しい理解が求められます。
- 分割契約で合計500万円を超える場合
- 工種ごとに契約したが、全体で500万円を超える場合
- 材料費や運搬費を含めて500万円を超える場合
- 消費税込みで500万円を超える場合
たとえば、450万円の請負工事でも、消費税10%を加えれば495万円に。さらに材料の持ち込みや運搬費用があれば簡単に500万円を超えてしまいます。
また、元請企業が契約を2回に分け、300万円+250万円とした場合でも、建設業法では合算して判断されるため、許可が必要です。
こうした細かい点を見落とすと、建設業許可が必要な工事に無許可で着手してしまい、罰則を受けるリスクが高まります。
500万円未満の解釈に注意
「500万円未満=許可不要」という単純な認識は危険です。
建設業法では、請負金額の「合算」が原則とされており、契約の形式や分割の有無にかかわらず、実質的な金額で判断されます。
たとえば以下のようなケースでは注意が必要です。
| 状況 | 判断基準 | 許可の要否 |
|---|---|---|
| 300万円+250万円の分割契約 | 合算して550万円 | 許可が必要 |
| 480万円(税抜)+消費税10% | 税込528万円 | 許可が必要 |
| 450万円+無償提供の材料費100万円 | 実質550万円 | 許可が必要 |
また、支店や営業所で取り扱える業種が限定されている場合、500万円未満でも対象外の工事を請け負うと違反になる可能性もあります(例:屋根工事の許可しかない支店が塗装工事を請け負う場合)。
特に個人事業主は「小規模だから大丈夫」と油断しがちですが、「建設業 許可 個人事業主」の観点でも、信頼性や取引機会の拡大を目的に、許可取得を検討する価値があります。
工事金額の計算ルールと見落としやすいポイント
建設業許可が必要かどうかは、単に契約書に記載された金額だけでは判断できません。
請負金額には材料費や消費税、運搬費なども含まれ、契約の分割や工種ごとの合算も必要です。
ここでは、見落としやすい工事金額の計算ルールを整理して解説します。
材料費・消費税も含めて計算される
建設業許可の必要性を判断するうえで、最も注意すべきポイントの一つが「請負金額の範囲」です。
請負金額には、以下の費用を含めて計算する必要があります。
- 工事の人件費や施工費
- 使用する材料費(元請などから無償支給された場合も含む)
- 材料や機材の運搬費
- 消費税(税抜価格ではなく税込価格で判断)
たとえば、施工費が450万円であっても、材料費が50万円かかれば合計で500万円となり、建設業許可が必要になります。
さらに消費税10%を加味すれば、実質的に454万円以上の契約はすべて「許可が必要」となる可能性があります。
以下の表は、材料費や消費税の影響による金額の変化を示した例です。
| 施工費(税抜) | 材料費 | 税込合計金額 |
|---|---|---|
| 450万円 | 30万円 | 528万円(許可必要) |
| 430万円 | 50万円 | 528万円(許可必要) |
| 454万円 | 0円 | 499.4万円(許可不要) |
金額を税抜きで考えると、誤って許可不要と判断してしまうケースが多いため、契約前に税込価格での確認が必須です。
契約の分割は原則合算される(例:300万+250万)
契約を複数に分けることで、それぞれの金額を500万円未満に見せかける手法は、建設業法では認められていません。
工事の実態が一体であると判断される場合は、分割契約であっても請負金額を合算して判断することが原則です。
たとえば、700万円の工事を「300万円+400万円」の2契約に分けても、合算で700万円となるため建設業許可が必要です。
このルールは元請・下請どちらにも適用され、違反した場合は元請業者も罰則の対象となります。
また、以下のようなケースでも合算が求められます。
| 分割契約の内容 | 合算金額 | 建設業許可の要否 |
|---|---|---|
| 300万円+250万円 | 550万円 | 必要 |
| 490万円+材料支給(60万円相当) | 550万円 | 必要 |
| 250万円(建築)+300万円(内装) | 550万円 | 必要(次項参照) |
契約書上は分かれていても、発注元が同一、工期が同時、内容が連続性をもっているなどの場合は、単一工事として判断される点に注意が必要です。
工種ごとの合計にも注意が必要
異なる工種の工事を請け負った場合でも、その合算金額が500万円を超えると建設業許可が必要になるケースがあります。
たとえば、外壁塗装250万円、屋根工事300万円のように、それぞれの契約が500万円未満でも、同一現場で行う一連の工事と見なされれば、合算して判断される可能性が高くなります。
特に、同一建物や同一敷地内で行う複数工種の工事は「一体的な建設工事」とされる場合が多く、許可の要否判断において重要なポイントとなります。
工事内容が異なるからといって許可が不要と判断せず、以下のような状況では特に注意が必要です。
- 同一現場で複数の工種を連続して実施
- 発注元が同一であり、工期や請負目的が共通
- 工種ごとの業者が同一(例:一人親方が全工種担当)
こうした状況では、合計金額で建設業許可が必要かどうかを判断しなければなりません。
誤って「工種別だから大丈夫」と判断すると、建設業許可違反による罰則の対象となるおそれがあります。
実務では、契約時点で工種の範囲や金額、発注条件を正確に確認しておくことが重要です。
500万円未満でも建設業許可が必要なケース
建設業許可は原則として「請負金額が500万円以上(消費税込)」の工事に必要とされますが、500万円未満であっても許可が求められるケースがあります。
特定の業種や営業所の取り扱い、個人事業主の業態によって例外が発生するため注意が必要です。
支店・営業所の業種許可に注意
法人や複数拠点で建設業を営む場合、それぞれの営業所で取り扱う業種に対して建設業許可を取得する必要があります。
たとえ各現場での工事が500万円未満だったとしても、営業所単位で一定の業種を継続的に扱う場合は、許可が必要です。
たとえば、本社で「内装仕上工事業」の許可を取得していても、支店で「とび・土工工事業」を行う場合、その支店でも別途許可を取らなければなりません。
金額に関係なく、営業所で行う業種に応じて、必要な許可を取得しないと法令違反になる可能性があります。
このルールは元請・下請にかかわらず適用されるため、たとえ下請けでも営業所単位での許可漏れには注意が必要です。
営業体制を広げる際には、すべての拠点における業種と金額を確認し、必要に応じて建設業許可を取得しましょう。
個人事業主でも例外はある
建設業許可は法人だけでなく、個人事業主にも当然に適用されます。
特に注意が必要なのは、規模が小さいからといって「500万円未満だから許可は不要」と思い込んでしまうケースです。
たとえば、1人親方として活動している方でも、以下のようなケースでは建設業許可が必要になる可能性があります。
| ケース | 判断のポイント | 許可の必要性 |
|---|---|---|
| 材料費込みで450万円+消費税 | 税込で495万円超 | 原則不要だが注意が必要 |
| 複数現場で請負計550万円 | 一体の工事とみなされる | 必要 |
| 下請けだが元請の指示で分割契約 | 合算して判断 | 必要 |
また、建設業法では「軽微な工事」を除いて建設業許可が必須とされていますが、個人事業主であっても契約形態や工事内容によっては、その「軽微」に該当しないこともあるため要注意です。
建設業 許可 個人事業主 としての正しい知識がないまま受注を続けてしまうと、後々大きなトラブルや罰則に発展する可能性があります。
解体工事・電気工事・浄化槽工事は別途登録が必要
工事の中には、金額に関係なく建設業許可または別の登録制度が必要なものがあります。
特に「解体工事」「電気工事」「浄化槽工事」などは要注意です。
解体工事:2016年6月以降、独立した業種として「解体工事業」が建設業許可制度に追加されました。それまで「とび・土工工事業」として扱われていた場合でも、現在は原則として解体工事業の許可が必要です。
電気工事:建設業許可に加え、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」による登録も必要な場合があります。これは金額にかかわらず適用されます。
浄化槽工事:浄化槽工事は「浄化槽法」により、浄化槽設備士による施工や登録業者制度が設けられています。建設業許可とは別に、都道府県ごとの登録が必要です。
これらの工事を行う際は、金額が500万円未満であっても、法令で求められる許可・登録の有無を確認しましょう。
以下に金額にかかわらず許可・登録が必要となる主な工種をまとめます。
| 工種 | 必要な許可・登録 | 金額条件 |
|---|---|---|
| 解体工事 | 解体工事業の建設業許可 | 原則500万円以上、実態により登録が必要 |
| 電気工事 | 電気工事業の登録(電気工事業法) | 金額にかかわらず必要 |
| 浄化槽工事 | 浄化槽工事業者登録(浄化槽法) | 金額にかかわらず必要 |
これらは「500万円未満だから大丈夫」と思っていると違反となる典型例です。
着工前に各種法令と照らし合わせて、自社の対応状況を確認することが重要です。
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負った場合の罰則
建設業許可を持たずに500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法に違反することとなり、重大な刑事罰や営業停止、信用失墜のリスクが伴います。
また、元請けも連帯して責任を問われるケースがあり、個人・法人問わず重い影響を受ける可能性があります。
建設業許可 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
建設業許可がない状態で、軽微な工事の範囲を超えて500万円以上(税込)の工事を請け負うと、建設業法違反となり、以下のような罰則が科される可能性があります。
| 違反内容 | 罰則 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可なしで500万円以上の工事を請負 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 両罰規定により法人も処罰対象 |
| 虚偽申請で許可を取得 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 許可取消・再取得制限の対象 |
| 名義貸し | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 名義を貸した側も処罰対象 |
罰則は個人・法人問わず適用される「両罰規定」があり、会社が関与した場合は代表者および法人の双方に刑事責任が及ぶことがあります。
刑罰を受けた事実は行政処分や社会的信用にも影響を及ぼします。
違反した場合の事業影響と再取得制限
無許可で500万円以上の工事を請け負い処分を受けた場合、その後の営業活動に大きな支障が出る可能性があります。
刑事罰に加えて、建設業許可の再取得にも制限がかかるため、将来的な事業展開が困難になります。
違反後は、許可の再取得申請をしても、欠格事由として一定期間(原則5年)許可を受けられないケースがあります。
また、違反歴があることは公共工事の入札審査や元請企業との取引においても不利に働きます。
このような行政的・社会的ペナルティは、経営者本人だけでなく従業員の雇用や取引先との関係にも波及します。
とくに個人事業主の場合は、自身の名前で信用が築かれるため、一度の違反が取り返しのつかない結果につながることも少なくありません。
元請側の責任も問われるリスク
建設業法では、元請業者にも「無許可業者に工事を発注した場合の責任」が問われます。
たとえ下請け業者が無許可だったとしても、元請側がその事実を知りながら契約した場合、元請も指導・処分の対象となる可能性があります。
実際、元請企業が無許可業者に再三にわたって工事を発注し、行政から指導や監督処分を受けた例もあります。
また、コンプライアンス重視の時代において、許可の確認を怠ること自体が社会的評価を下げ、企業イメージを著しく損ねるリスクにつながります。
特に公共事業や大手企業との取引では、下請業者の許可有無や過去の違反歴を厳しくチェックされる傾向があるため、元請としても契約前の確認を徹底する必要があります。
元請け業者としてのリスクを回避するためには、協力会社の選定段階で建設業許可証の確認や更新状況のチェックを行い、無許可業者と取引しない社内体制を整えることが重要です。
個人事業主でも建設業許可を取得すべき理由
建設業許可は法人だけのものと思われがちですが、個人事業主にとっても多くのメリットがあります。
信頼性の向上、受注範囲の拡大、比較的簡単な手続きなど、将来的な事業発展を見据えるなら、許可取得は重要なステップといえます。
信頼性向上
個人事業主が建設業許可を取得する最大のメリットのひとつは、社会的な信頼性の向上です。
許可業者として登録されることで、行政機関の審査をクリアした証となり、取引先や顧客に対する安心感を与えることができます。
とくに元請や大手ゼネコン、公共工事などでは、建設業許可がなければ仕事の依頼そのものが受けられないケースも多く、無許可のままではビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。
建設業許可があることで、適正な管理体制が整っている事業者と見なされ、他社との差別化にもつながります。
また、許可業者であることはホームページや名刺、看板等でもアピール可能で、新規顧客獲得にも効果的です。
これらは地域密着型で営業する個人事業主にとって、大きな営業ツールとなります。
許可があることで受注の幅が広がる
建設業法では、1件の工事が500万円(税込)以上の場合は原則として建設業許可が必要です。
許可を持っていない場合、金額の大きな案件は請け負うことができず、軽微な工事に限定されてしまいます。
一方、許可を取得すれば金額にかかわらず様々な規模の工事に対応できるようになり、受注の幅が格段に広がります。
例えばリフォーム工事一式で500万円を超える住宅改修案件や、集合住宅の設備工事など、個人事業主でも手がけられる高額案件は多数存在します。
また、許可業者であれば元請として下請を使うことも可能になるため、事業のスケールアップも図れます。
個人でありながら元請として現場を動かすことができるのは、長期的な成長を目指す上で大きなメリットといえるでしょう。
法人よりも申請手続きが比較的簡単
個人事業主が建設業許可を取得する際の手続きは、法人と比べて簡便な面があります。
たとえば法人の場合は定款や登記簿謄本などの書類が必要ですが、個人事業主であれば開業届や所得証明など、比較的少ない書類で手続きを進められます。
また、申請費用についても法人と同じ金額でありながら、書類準備や経営事項審査の手間が比較的軽いため、初めて許可を取得する方にも取り組みやすいのが特徴です。
さらに、専任技術者や経営業務管理責任者の要件も、長年の実務経験があればクリアできるため、長く現場で働いてきた職人の方にとってはハードルが低く感じられることもあります。
このように個人事業主としての建設業許可取得は準備や費用の面でも十分に現実的であり、事業の信頼性と将来性を大きく高める手段となります。
建設業許可と500万円ラインの実務的チェックリスト
建設業許可の要否を見極めるうえで、500万円という金額ラインは非常に重要な判断基準です。
ここでは、工事前にチェックすべきポイントや申請の必要性を見分けるための早見表、不明点への対応方法について具体的に解説します。
工事前に確認すべきポイント一覧
建設工事に着手する前に「この工事は許可が必要か?」を確認することは、リスク回避の観点からも非常に重要です。
特に500万円(税込)を超えるかどうかの判断は罰則の有無にも関わるため、以下のような点を事前に明確にしておく必要があります。
| 確認項目 | チェック内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 請負金額 | 税込で500万円を超えていないか | 消費税を含めて判断 |
| 材料費の扱い | 自社が材料を手配する場合は含める | 材料費も請負額に含まれる |
| 契約分割 | 500万円未満で複数契約していないか | 実態が一体なら合算される |
| 工種の合計 | 同一工種で分けた契約か | 工種ごとの合算が必要な場合あり |
このように、単純に「契約書の金額が500万円未満だから大丈夫」と判断するのではなく、実態を基に精査することが求められます。
申請・登録が必要なケースの早見表
500万円未満の工事であっても、内容によっては建設業許可とは別に登録や届出が必要なケースもあります。
以下の表は、主要な業種における登録・許可の要否を示した早見表です。
| 工事の種類 | 金額基準を問わず必要な登録 | 備考 |
|---|---|---|
| 解体工事 | 解体工事業登録 | 軽微な工事でも要登録 |
| 電気工事 | 電気工事業者登録 | 経済産業省・都道府県への届出 |
| 浄化槽工事 | 浄化槽工事業登録 | 都道府県知事への登録が必要 |
| 土木・建築工事 | 建設業許可(500万円以上) | 許可業種ごとに必要 |
金額だけで判断せず、業種特有の規制を確認することが重要です。
とくに解体・電気・浄化槽といった分野では、許可とは別に登録が法令で義務付けられています。
不明点は行政書士や専門機関に相談を
建設業許可や各種登録の要否判断は、業種や金額、契約形態によって複雑になることが多く、個人や事業者だけで判断するのは難しい場面もあります。
とくに初めて許可申請を考えている個人事業主や小規模事業者にとっては、制度の仕組みそのものが分かりづらく、思わぬ法令違反を招くリスクもあります。
そうした場合には、都道府県の建設業課、商工会議所、または建設業法に精通した行政書士などの専門家に相談するのが最善の方法です。
相談窓口は無料で利用できることもあり、早期に適切なアドバイスを受けることで、不要な手続きや違反リスクを未然に防げます。
また、国土交通省や各都道府県のホームページにも建設業許可に関する詳細な情報や申請様式が掲載されていますので、最新情報をチェックする習慣も大切です。
まとめ
今回の記事では、建設業許可について解説しました。
工事金額が500万円を超える可能性がある場合や、業種ごとに登録が必要なケースでは、事前に専門家へ相談し、許可の取得を前向きに検討しましょう。