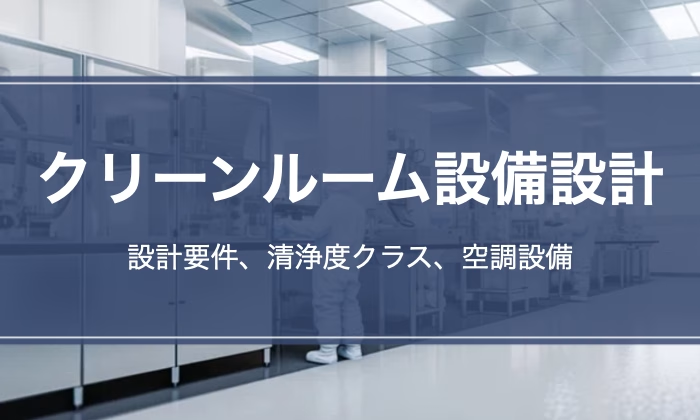クリーンルームの設備設計では、微粒子の影響を最小限に抑えつつ、効率的な空調・レイアウト・清浄度管理をどう設計すべきか悩んでいる方は多いはずです。
特に半導体や医療などの高精度環境では、設計次第で品質やコストに大きな差が生まれます。
そこで、今回はクリーンルームにおける設備設計の基本構造や清浄度、気流制御、最新技術について解説します。
この記事を読めば現場で失敗しないための設備設計の考え方や、コストを抑えつつ高い清浄度を保つ設計手法がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
クリーンルームにおける設備設計の重要性
クリーンルームは、微粒子や温湿度、気流の制御が厳しく求められる特殊な環境です。
そのため、設備設計の段階から高度な管理を前提とした計画が必要になります。
ここではクリーンルームにおける設備設計の重要性について解説します。
なぜクリーンルームの「設備設計」が重要なのか
クリーンルームの設備設計は、単に空調設備を導入すればよいというものではありません。
空気中の微粒子を徹底的に排除し、常に一定の温度・湿度を保ち、かつ効率的な気流を維持するという複雑な要件を同時に満たす必要があります。
これらを実現するためには、建物構造・空調方式・フィルター配置・作業動線など、あらゆる要素を統合的に設計する必要があります。
特に半導体やバイオ分野では、ナノレベルの微粒子が製品不良の直接的な原因となるため、わずかな設計ミスが品質や生産性に大きな影響を与える可能性があります。
設備設計の段階で「どの工程にどれだけの清浄度を求めるか」を明確にし、それに応じてゾーニングや機器配置を行うことが求められます。
また、運用開始後の保守やメンテナンスのしやすさ、ランニングコスト、エネルギー効率なども設備設計段階で考慮しなければなりません。
これらを見落とすと、長期的に高コストで非効率な運用を強いられることになります。
設備設計は、クリーンルームの性能を決定づける最重要フェーズであり、製造現場の安定稼働や製品の歩留まり向上にも直結します。
つまり、設備設計を制する者がクリーンルームを制すると言っても過言ではありません。
微粒子・温湿度・気流など多要素の管理が不可欠
クリーンルームの設備設計では、複数の要素を同時に制御し、バランスを保つ必要があります。
特に重要なのは
- 微粒子管理
- 温湿度制御
- 気流設計
の3つです。
まず、微粒子管理の基本はHEPAやULPAフィルターによる空気清浄です。
これらのフィルターを適切に配置し、空気の流れに無駄がないようにすることで、空間全体の清浄度を高めます。
気流設計が不十分だと、フィルターを通った空気も再汚染される可能性があり、性能を十分に発揮できません。
次に、温湿度の制御も不可欠です。
特に半導体製造などの精密加工では、わずかな温度変化が薬剤の反応や素材の寸法に影響を与えるため、設計段階で空調能力と調整精度を考慮する必要があります。
また、湿度が高すぎれば結露やカビのリスクがあり、低すぎれば静電気による障害が発生します。
最後に、気流の管理です。代表的な気流方式には「垂直一方向流」「水平一方向流」「乱流方式」があり、それぞれの方式には特徴があります。
清浄度が特に重視されるエリアでは一方向流を採用し、コストを抑えたい部分では乱流方式を使うなど、設計段階での組み合わせが重要です。
以下に、それぞれの気流方式の比較表を示します。
| 気流方式 | 特徴 | 適用例 |
|---|---|---|
| 垂直一方向流 | 上部から下部へ空気を均一に流す。微粒子が下に流されやすい。 | 半導体製造の高清浄度エリア |
| 水平一方向流 | 横方向に空気が流れる。レイアウト制約があるが効果は高い。 | クリーンベンチや局所エリア |
| 乱流方式 | 空気がランダムに流れる。清浄度はやや劣るがコストが低い。 | 中程度の清浄度を求める工程 |
このように、クリーンルームの設備設計には多くの要素を総合的に捉える視点が求められます。
単一の性能を追求するだけでは不十分で、複数の要因が連動してクリーン環境が維持されることを忘れてはいけません。
クリーンルームの清浄度クラスと設計要件
クリーンルームの性能を評価するうえで、清浄度クラスの理解と、それに適合する設備設計が不可欠です。
国際規格ISO 14644は、設計段階から遵守すべき重要な基準となります。
ここでは、クリーンルームの清浄度クラスと設計要件について解説します。
ISO 14644による国際規格の概要
ISO 14644は、クリーンルームにおける粒子汚染を管理・制御するための国際規格です。
特に「ISO 14644-1」では、空中微粒子の清浄度レベル(クラス)を数値で定義しており、設計・施工・運用までの一貫した品質管理に活用されます。
この規格に基づく設計を行うことで、医薬品製造・半導体工場・精密機器製造など高精度な管理が求められる分野において、国際的な品質基準に準拠した環境整備が可能となります。
規格は、室内の空気中に含まれる粒子の個数をサイズごとに定義し、それにより「クラス1」「クラス1000」などの分類が決定されます。
たとえば、ISOクラス5は、0.5μmの粒子が1立方メートルあたり3,520個以下でなければならないという厳しい基準です。
ISO 14644シリーズは設計者だけでなく、運用者や品質管理者にとっても必須の知識であり、室内環境の定量的評価と、パフォーマンスの継続的な改善を可能にする指標として機能します。
清浄度クラスと求められる粒子数
清浄度クラスとは、クリーンルーム内に存在する粒子数の基準値を定めたランクのことです。
これは作業環境に応じて選定され、製造物やプロセスの品質を直接左右します。
たとえば半導体製造では微小な粒子が歩留まりに大きな影響を与えるため、ISOクラス5以下の厳格な清浄度が求められます。
以下は、主要なISOクラスにおける粒子数の基準値を示した表です。
| 清浄度クラス | 0.5μmの粒子数(個/m³) | 主な用途例 |
|---|---|---|
| ISOクラス1 | 10以下 | ナノテクノロジー、極端な精密加工 |
| ISOクラス5 | 3,520以下 | 半導体、医薬品製造 |
| ISOクラス7 | 352,000以下 | 食品製造、一般的な医療機器 |
クリーンルームの清浄度は、空調システム、フィルター(HEPA/ULPA)、気流制御、圧力差の管理など設備設計と密接に関係しています。
そのため、目的に応じた適切な清浄度クラスを設定し、それを確実に満たす設備設計が極めて重要です。
設計時に考慮すべき規格対応ポイント
クリーンルームの設計段階で、ISO 14644に対応するためには複数のポイントを押さえる必要があります。
まず重要なのは、設計初期において必要な清浄度クラスを明確にし、それに基づいたゾーニング・気流計画を行うことです。
気流には主に「単一方向流(層流)」と「乱流混合方式」があり、要求されるクラスによって選択が異なります。
また、室内の正圧管理も不可欠です。
隣接する低清浄度エリアからの汚染物質侵入を防ぐために、空間ごとの圧力勾配を意識した設計が求められます。
さらに、フィルターの配置やメンテナンス性を含む「ライフサイクル設計」も重視されます。
規格への対応は、単に設備を導入すれば達成できるものではなく、施工精度・素材選定・室内動線まで含めた総合的なアプローチが必要です。
これらのポイントを設計段階で徹底することで、後の維持管理コストの削減と、安定した生産環境の実現が可能になります。
クリーンルームの構造と空調設備の設計
クリーンルームの性能を維持するためには、構造設計と空調設備の連携が不可欠です。
以下では、主要なフィルターの選定基準や気流制御の方式、それぞれの構造的な特徴について詳しく解説します。
HEPA/ULPAフィルターの選定基準と設置方法
クリーンルームの清浄度を確保するうえで、HEPA(High Efficiency Particulate Air)およびULPA(Ultra Low Penetration Air)フィルターの適切な選定と設置は重要なポイントです。
HEPAフィルターは粒径0.3μmの粒子を99.97%以上除去できる性能を持ち、一般的なクリーンルームで使用されます。
一方、ULPAフィルターは0.1〜0.2μmの微粒子を99.9995%以上除去可能で、より厳格な清浄度が求められる環境で使用されます。
選定においては、清浄度クラス、処理風量、圧力損失、設置スペースなどを考慮する必要があります。
また、フィルターの交換時期やメンテナンス性も設計段階で見込んでおくことが重要です。
設置方法としては、天井全面に配置する「フルフラット方式」や、必要箇所に集中させる「局所供給方式」があり、用途やクリーンルームのレイアウトに応じて選択されます。
| フィルター種別 | 粒子除去効率 | 主な使用用途 |
|---|---|---|
| HEPA | 99.97%(0.3μm) | 一般的な電子部品製造、医薬品包装工程など |
| ULPA | 99.9995%(0.1〜0.2μm) | 半導体製造、バイオ医薬品の無菌室など |
垂直流/水平流/乱流の違いと使い分け
クリーンルームにおける気流制御は、清浄度の安定維持に直結する重要な設計要素です。
代表的な気流方式には「垂直層流」「水平層流」「乱流」があります。
垂直層流は、天井から床へ向けて上から下へ均一な空気を流す方式で、パーティクルの速やかな排出が可能なため、特に高清浄度クラス(ISOクラス5以下)で多く採用されています。
水平層流は、壁面から対向壁面に向かって風を流す構造で、装置配置によっては短い流路での効率的な清浄化が期待できます。
ただし、風の流れが機器類により乱されやすく、設計時には流線の確保に注意が必要です。
一方、乱流方式は層流を用いず、空間全体を攪拌することで清浄度を保つ方式で、クラス7〜8程度の比較的緩い清浄度管理の場面で用いられます。
それぞれの方式にはメリットとデメリットがあるため、求められる清浄度、作業内容、設備構成などを踏まえて使い分けることが肝要です。
| 気流方式 | 特徴 | 適用例 |
|---|---|---|
| 垂直層流 | 天井から床へ均一に空気を供給し、パーティクルを直下に排出 | 半導体、医薬品製造の無菌工程 |
| 水平層流 | 壁面から対向壁面に向けて風を供給。装置配置に工夫が必要 | 精密機器組立、クリーンベンチ |
| 乱流 | 空気を攪拌して全体の清浄度を保つ | クラス7〜8のクリーンルーム、前室 |
陽圧制御による外気遮断と気流制御の実例
クリーンルームの性能を維持するためには、室内を外気より高い圧力状態に保つ「陽圧制御」が欠かせません。
陽圧をかけることで、ドア開閉時や微小な隙間からの外気の侵入を防ぎ、パーティクルや微生物の侵入リスクを最小限に抑えることができます。
この陽圧は、室内の給気量が排気量を上回るように空調設計することで実現されます。
例えば、ISOクラス5〜6を維持する無菌製造区域では、前室との間に10〜15Paの圧力差を設け、前室との境界を通過する空気の流れを常に一方向(清浄から非清浄)に保つようにします。
さらに、室内のゾーニングを設け、各エリア間で段階的な圧力差を設定することで、汚染拡散を防ぐ仕組みも一般的です。
このような圧力制御の仕組みは、クリーンルームの清浄度維持だけでなく、異物混入や品質トラブルの予防にも直結するため、設計段階から気流バランスや制御機構を慎重に計画することが求められます。
クリーンルーム設備設計における温湿度・静電気管理
クリーンルームでは、製造環境の品質と安定性を確保するために、温湿度や静電気の管理が欠かせません。
ここでは、それぞれの要素が設備設計においてどのように考慮されるべきかを解説します。
高精度温湿度制御が必要な理由
クリーンルームでの温湿度管理は、製造品質を左右する重要な設計要素です。
特に半導体や医薬品、精密機器の分野では、わずかな温度や湿度の変動が製品の歩留まり(良品率)や再現性に大きく影響します。
たとえば、半導体製造工程ではフォトリソグラフィやエッチングの精度に温度が関係し、湿度が高すぎると静電気が発生しにくくなる一方で、化学薬品の反応が不安定になります。
設計段階では、0.1℃単位での温度制御や、±1%RHの湿度制御が求められるケースもあります。
これを実現するには、恒温恒湿ユニットの選定だけでなく、空調機の能力設計、風量バランスの最適化、冷温水の精密制御など、複数の技術的工夫が必要です。
また、内部発熱の多い装置や人の作業による負荷も考慮し、負荷変動に応じたリアルタイム制御を可能にするシステム設計が求められます。
以下に一般的な用途別に求められる温湿度制御の基準をまとめます。
| 用途 | 温度制御基準 | 湿度制御基準 |
|---|---|---|
| 半導体製造 | 21±0.1℃ | 45±2%RH |
| 医薬品製造 | 22±1.0℃ | 50±5%RH |
| 精密機器組立 | 23±0.5℃ | 50±3%RH |
上記のように、用途に応じて求められる温湿度制御の精度は異なるため、設備設計においては対象工程の要件を十分に確認し、適切な空調・加湿・除湿システムを選定することが必要です。
静電気対策(帯電防止床、接地、イオナイザー)
クリーンルームでは微粒子の制御だけでなく、静電気の発生と放電によるダメージを防ぐことも非常に重要です。
静電気は人間の感知できない微細な電圧でも、精密機器や電子部品にとっては致命的な損傷の原因となります。
そのため、設備設計段階での静電気対策が不可欠です。
主な静電気対策には、以下の3つがあります。
帯電防止床材の使用:床には導電性または拡散性のある床材を採用し、静電気をスムーズに逃がすことが求められます。
導電床は比較的早く電気を逃がすのに対し、拡散床は徐々に電荷を分散させて放電リスクを軽減します。
設置時は、床下の接地網との確実な接続も必要です。
確実な接地設計:作業台やラックなど、すべての金属部材は接地(アース)されている必要があります。
これにより、静電気の蓄積を防ぎ、安全な放電経路を確保します。
また、人が着用するESDガウンや靴も接地環境と組み合わせることで効果を発揮します。
イオナイザーの配置:空間中に浮遊する静電気を中和するため、イオナイザー(静電気除去装置)を設置します。
特に帯電しやすい素材(プラスチック等)を扱う作業エリアや、部品の搬送ラインでは、局所的なイオナイザーの導入が効果的です。
| 対策手法 | 目的 | 設置例 |
|---|---|---|
| 帯電防止床 | 人体の静電気を床経由で除去 | 作業エリア全体 |
| 接地(アース) | 設備・作業台・人体の電位をゼロに保つ | 金属什器、ESD靴、手首バンド |
| イオナイザー | 浮遊帯電物の電荷を中和 | 天井吊下型、卓上ファン型 |
これらの対策を複合的に導入することで、クリーンルームにおける静電気リスクを最小限に抑えることができます。
設備設計段階から、対象工程や作業内容に合わせた静電気対策を講じることが重要です。
半導体製造で求められるクリーンルーム設計の特徴
半導体製造の現場では、微細な粒子の混入が製品不良に直結するため、極めて高度なクリーンルーム設計が求められます。
工程ごとの要件に応じたゾーニングや、ミニエンバイロメントの導入も重要です。
特に厳しい清浄度を求められる背景
半導体製造は、ナノメートル単位の微細な回路パターンを形成する工程であるため、空気中に浮遊する微粒子(パーティクル)や化学汚染物質(AMC:Airborne Molecular Contaminants)が致命的な影響を与えます。
例えば、直径0.1μmの粒子でも、回路パターンの上に付着すれば、製品としての機能を失う可能性があります。
そのため、クリーンルームにはISOクラス5(旧クラス100)やそれ以上の清浄度が要求されることも珍しくありません。
特に露光・成膜・エッチングといった工程では、高い清浄度が維持されていないと、歩留まり低下や信頼性の問題を引き起こします。
また、これらの問題は製品完成後に顕在化することもあり、結果的にコストや納期に大きな影響を与えるため、設計段階から高度な管理が必要です。
エリアごとに異なる設計要件(工程別ゾーニング)
半導体工場では、製造工程の特性に応じてクリーンルーム内のゾーニングが行われます。
たとえば、パーティクルに極端に敏感な露光工程ではISOクラス5の環境が必要とされる一方で、検査や搬送エリアなどではISOクラス6~7で十分な場合もあります。
このようにエリアごとに適切な清浄度を設定することで、エネルギーコストや初期投資を最適化しつつ、全体の歩留まりを維持することが可能となります。
また、クリーンエリアの人と物の動線にも注意が必要です。
交差汚染を防ぐためにエアロックやパスボックスを設けたり、スタッフの動線と材料の動線を分離したりと、動線設計も精密に行う必要があります。
ゾーニングを前提とした設計は、無駄な空調負荷の削減にもつながり、長期的な運用コストにも好影響を及ぼします。
ミニエンバイロメントの活用とその効果
近年の半導体製造現場では、クリーンルーム全体の清浄度を過度に上げるのではなく、製品が実際に露出する限られた空間を局所的に管理する「ミニエンバイロメント(Mini-Environment)」の導入が進んでいます。
これは、装置内部などの小空間において、HEPAフィルターやULPAフィルターで空気を循環させ、ISOクラス1〜3といった超高清浄度を維持する方法です。
この方式の最大の利点は、クリーンルーム全体の空調設備にかかる負荷を軽減しながら、必要な部位だけを高精度に管理できる点にあります。
また、作業員の動きによるパーティクル発生の影響を最小限に抑える効果もあり、オートメーション化された設備との相性も良好です。
ミニエンバイロメントは、設備設計段階からの導入を前提とすることで、空調・レイアウト・配線等との整合性を確保しやすくなります。
| 要素 | 従来型クリーンルーム | ミニエンバイロメント |
|---|---|---|
| 清浄度範囲 | クリーンルーム全体 | 装置内部・局所空間 |
| 空調負荷 | 高い | 低い |
| 導入コスト | 初期は抑えやすい | 初期は高めだが運用効率が高い |
| 自動化対応 | 一部困難 | 対応しやすい |
まとめ
今回の記事では、クリーンルームの設備設計について解説しました。
クリーン環境の維持には、用途に応じた温湿度・静電気管理が不可欠です。
特に再現性や歩留まりに直結するため、設計段階から要件を明確にし、信頼できる設計事務所に早期相談することをおすすめします。