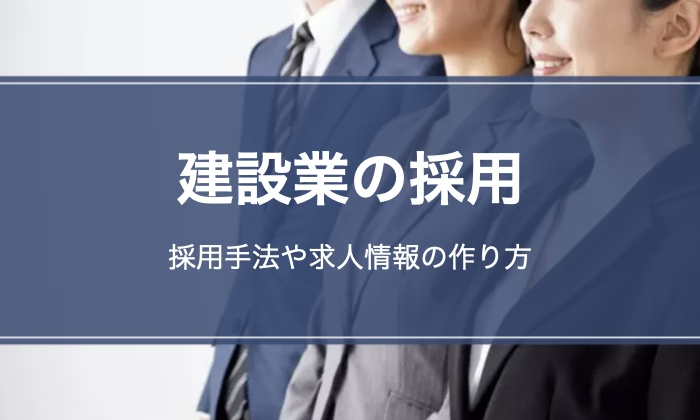建設業の採用、何から手を付ければいいかわからないということはありませんか?
そこで、今回は建設業における採用の考え方から、具体的な進め方、失敗しやすいポイントまでを体系的に解説します。
この記事を読めば、建設業の採用でまずやるべきこと、採用方法の選び方、自社に合った人材を集めるための実践的なポイントがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業の採用が難しいと言われる理由
建設業の採用が難航する背景には、業界特有の構造的な課題が複合的に存在します。
単なる人手不足ではなく、求職者側の意識変化や情報の伝わり方、他業界との比較による誤解などが重なり、採用活動の成果が出にくい状況を生んでいます。
ここでは代表的な3つの理由について解説します。
若年層の建設業離れと業界イメージ
若年層の建設業離れが進んでいる最大の要因は、業界イメージが更新されないまま固定化されている点にあります。
多くの若者は建設業に対して「きつい」「危険」「休みが少ない」といった印象を持ちやすく、実際の現場環境や働き方の変化を知る機会がほとんどありません。
ICT施工の導入や労働時間の是正、安全対策の強化など、業界内部では改善が進んでいるにもかかわらず、それが求職者に届いていないのが実情です。
また、進路選択の段階で建設業が選択肢に入らないケースも多く、採用活動以前に母集団形成が難しくなっています。
結果として、若年層にリーチできず、中高年層に応募が偏る構造が続いています。
求職者数と求人件数の需給バランス
建設業では慢性的な人手不足が続いており、求職者数に対して求人件数が大きく上回る状況が常態化しています。
特に現場職や技術職では有効求人倍率が高く、企業側が「選ぶ立場」ではなく「選ばれる立場」になっている点が採用難易度を押し上げています。
この需給バランスの崩れにより、従来と同じ採用方法では他社との差別化ができず、求人を出しても反応がない状態に陥りがちです。
また、地域差も大きく、都市部と地方では求職者の動き方が異なるため、画一的な採用戦略では成果が出にくいという問題もあります。
需給の現実を正しく理解せずに採用を進めると、無駄なコストと時間を消費する結果になりかねません。
他業界と比較した労働条件の誤解
建設業の労働条件は、他業界と比較されることで実態以上に厳しく見られることがあります。
たとえば、給与水準は決して低くないにもかかわらず、初任給や昇給モデルが分かりにくいため、求職者に正しく評価されていません。
また、休日や労働時間についても、企業ごとの差が大きいにもかかわらず、業界全体が長時間労働であるかのように一括りにされがちです。
こうした誤解は求人情報の書き方にも原因があり、条件を十分に言語化できていないことで、他業界の求人に見劣りしてしまいます。
本来の魅力や実情を適切に伝えられていない点が、採用を難しくしている大きな要因の一つです。
建設業の採用で最初に整理すべき考え方
建設業の採用を成功させるためには、求人媒体の選定や募集開始よりも前に、採用に対する考え方を整理することが不可欠です。
多くの建設会社がつまずくのは、準備不足のまま人を集めようとする点にあります。
ここでは、採用活動の土台となる基本的な考え方を解説します。
建設業の採用は「集める」前に「決める」
建設業の採用では、求人を出せば人が集まるという時代はすでに終わっています。
それにもかかわらず、採用活動を「募集開始」から考えてしまう企業は少なくありません。
本来、採用で最初に行うべきなのは、人を集めることではなく、何を目的として採用するのかを明確に決めることです。
たとえば、即戦力となる経験者が必要なのか、将来を見据えた未経験者育成なのかによって、採用手法や訴求内容は大きく変わります。
目的が曖昧なままでは、求人内容も抽象的になり、求職者に響きません。
採用とは経営判断の一部であり、現場の人手不足を埋める作業ではなく、会社の将来を支える人材を迎える戦略的な取り組みであると捉える必要があります。
誰を採用したいのかを言語化する重要性
採用活動がうまくいかない建設会社の多くは、「誰を採用したいのか」を明確に言葉で説明できていません。
年齢、経験年数、保有資格といった条件面だけでなく、どのような価値観を持ち、どんな働き方を望む人なのかまで言語化することが重要です。
これができていないと、求人票は誰に向けたものか分からない内容になり、結果として応募が集まらない、あるいはミスマッチが発生します。
言語化は社内認識を揃える効果もあり、経営者と現場担当者で採用イメージがずれることを防げます。
建設業では職種や現場環境の幅が広いため、曖昧な表現ではなく、自社に合う人物像を具体的に描くことが採用成功の前提条件となります。
「建設業採用何から始めればいい」と感じた時の基本ステップ
「建設業採用何から始めればいい」と感じた場合は、手当たり次第に求人を出すのではなく、段階的に整理することが重要です。
まず、自社の現状として人手不足の原因が一時的なものか、構造的なものかを把握します。
次に、採用の目的と必要人数、採用後に任せたい役割を明確にします。
そのうえで、どの層の求職者にアプローチするかを決め、初めて採用手法の検討に進みます。この順序を守ることで、無駄な広告費や工数を削減できます。
採用は感覚や勢いで進めるものではなく、現状分析と設計を経て実行するプロセスです。
基本ステップを踏むことが、安定した採用活動への近道となります。
建設会社の採用方法がわからない原因とは
建設会社が採用活動で行き詰まる背景には、情報過多と判断基準の不在があります。
採用手法自体は増えているものの、自社に合う方法を選べず、結果として「何をすればいいかわからない」状態に陥っています。
ここでは、その根本原因のついて解説します。
採用手法が多すぎて選べない問題
現在の建設業採用では、求人媒体、ハローワーク、自社サイト、SNS、紹介会社など、選択肢が非常に多く存在します。
一見すると手段が増えたことで採用しやすくなったように見えますが、実際にはこの多さが判断を難しくしています。
多くの建設会社は、それぞれの手法の特性や向き不向きを理解しきれないまま、名前を聞いたことがある方法や営業を受けた手段を選んでしまいがちです。
その結果、採用コストばかりがかかり、応募や定着につながらない状況が生まれます。
本来、採用手法は目的や採用したい人材像によって使い分けるべきものです。
選択肢が多いからこそ、軸がないと迷い続けるという問題が発生しています。
他社の真似では成果が出ない理由
採用方法がわからない建設会社ほど、うまくいっている他社の事例をそのまま真似しようとする傾向があります。
しかし、会社規模、地域、職種構成、現場環境が異なれば、同じ採用手法でも結果は大きく変わります。
他社で成果が出た背景には、社内体制や発信内容、受け入れ環境など複数の要素が絡んでいます。
それらを無視して表面的な手法だけを模倣しても、期待した効果は得られません。
また、真似をすることで自社の強みや特徴が見えなくなり、求人内容が没個性になるリスクもあります。
採用は再現性の低い取り組みであり、自社の状況に合わせた設計が不可欠です。
「建設会社採用方法わからない」状態から抜け出す視点
「建設会社採用方法わからない」と感じている状態から抜け出すためには、手法選びを先に考えないことが重要です。
まず必要なのは、自社が抱える採用課題を明確にする視点です。
応募が来ないのか、ミスマッチが多いのか、定着しないのかによって、取るべき対策は変わります。
そのうえで、採用の目的と対象人材を整理し、初めて手法を検討します。
この順序を逆にすると、いつまでも迷いが消えません。
採用方法は目的達成のための手段であり、正解は一つではありません。
自社の現状から逆算して考えることが、採用活動を前進させるための重要な視点です。
建設業に効果的な主な採用手法
建設業の採用では、単一の方法に依存するのではなく、複数の手法を理解したうえで自社に合うものを選ぶことが重要です。
それぞれの採用手法には向き不向きがあり、目的や採用したい人材像によって効果は大きく変わります。
ここでは代表的な手法について解説します。
求人媒体(建設業特化・総合型)の使い分け
求人媒体は建設業の採用において、現在も中心的な役割を担う手法です。
ただし、一口に求人媒体といっても、建設業に特化した媒体と総合型媒体では特性が大きく異なります。
建設業特化型は、業界経験者や資格保有者が集まりやすく、即戦力採用に向いています。
一方で、総合型媒体は母集団が広く、未経験者や若年層への接点を持ちやすいという特徴があります。
重要なのは、どちらが優れているかではなく、採用目的に合っているかどうかです。
経験者不足を補いたいのに総合型だけを使う、若手育成を狙っているのに特化型に絞るといった選択は、成果が出にくくなります。
媒体の特性を理解し、役割分担させる意識が必要です。
ハローワーク採用のメリットと限界
ハローワークは無料で利用できる点から、多くの建設会社が活用している採用手法です。
地域密着型で求職者層も幅広く、地元人材を採用したい場合には一定の効果があります。
また、公共機関であるため安心感があり、初めて採用活動を行う企業でも利用しやすい点はメリットです。
一方で、求人情報の表現に制限があり、自社の魅力を十分に伝えにくいという限界もあります。
掲載企業数が多いため埋もれやすく、待ちの姿勢になりがちなのも課題です。
ハローワークだけで採用を完結させようとすると、応募数や人材の質に限界が出やすいため、他の手法と組み合わせて活用する視点が欠かせません。
自社採用サイト・SEOを活用した採用
近年、建設業でも注目されているのが、自社採用サイトとSEOを活用した採用手法です。
自社サイトでは、仕事内容や現場の雰囲気、働く人の声などを自由に発信でき、他社との差別化がしやすくなります。
また、「建設業 採用」「建設会社 採用 方法」といったキーワードで検索する意欲の高い求職者に直接アプローチできる点も大きな強みです。
即効性は低いものの、継続的に情報を発信することで、広告費に依存しない安定した採用基盤を構築できます。
採用を短期施策ではなく、長期的な仕組みとして考える建設会社にとって、非常に相性の良い手法といえます。
SNS・リファラル採用の可能性
SNSやリファラル採用は、建設業ではまだ十分に活用されていない分、可能性の大きい手法です。
SNSでは、現場の日常や社員の働き方を発信することで、求人情報だけでは伝わらないリアルな雰囲気を届けることができます。
特に若年層は、企業の公式情報よりも実際の様子を重視する傾向があります。
また、社員紹介によるリファラル採用は、ミスマッチが起こりにくく、定着率が高い点が特徴です。
ただし、仕組みづくりをせずに始めても効果は出ません。
発信内容の方針や社内ルールを整え、無理なく継続できる形で導入することが成功の鍵となります。
建設業の採用で成果を出す求人情報の作り方
建設業の採用では、求人情報の内容次第で応募数も応募者の質も大きく変わります。
ただ条件を並べるだけでは求職者の心は動きません。
ここでは、建設業で実際に成果につながりやすい求人情報の考え方と作り方を解説します。
仕事内容を具体的に書く重要性
建設業の求人で最も多い失敗は、仕事内容が抽象的すぎることです。
「現場作業全般」「施工管理業務」といった表現では、求職者は実際の働く姿をイメージできません。
その結果、不安を感じて応募を見送るケースが増えます。
成果を出す求人情報では、1日の流れや関わる工事の種類、現場の規模、チーム体制などを具体的に記載します。
たとえば、朝礼の有無や現場への移動方法、未経験者が最初に担当する業務内容などを示すことで、入社後のギャップを減らせます。
具体性は応募数だけでなく、定着率にも直結します。
仕事内容を細かく書くことは、求職者に対する配慮であり、信頼を得るための重要な要素です。
給与・休日・働き方の正しい伝え方
給与や休日、働き方は、求職者が最も重視する情報です。
しかし、建設業の求人では「経験・能力による」「当社規定による」といった曖昧な表現が多く見られます。
これでは他社求人と比較された際に不利になります。
成果を出すためには、給与レンジや昇給の考え方、残業の実態、休日の取り方などを正直に伝えることが重要です。
すべてを理想的に見せる必要はありません。
現実を開示したうえで、その中でのメリットを説明する方が信頼されます。
また、働き方改革や現場改善に取り組んでいる場合は、その内容を具体的に示すことで、業界イメージの払拭にもつながります。
条件は隠すものではなく、比較材料として整理して伝えることが重要です。
建設業ならではの魅力の言語化
建設業の求人情報では、他業界と同じ切り口で魅力を伝えようとして失敗するケースが少なくありません。
建設業ならではの魅力は、形として残る仕事に関われる点や、技術が身につき一生使えるスキルになる点にあります。
しかし、これらは意識して言語化しなければ求職者に伝わりません。
たとえば、完成後も地域に残る建物に関われることや、資格取得によってキャリアの選択肢が広がる点などを具体的に表現します。
また、現場の人間関係や達成感といった感情面の価値も重要です。
条件面だけで勝負するのではなく、建設業だからこそ得られる経験や成長を言葉にすることで、共感を軸にした採用につながります。
採用がうまくいく建設会社に共通するポイント
建設業の採用で継続的に成果を出している会社には、共通した考え方と取り組み方があります。
単発的な募集ではなく、社内全体で採用を捉え、改善を重ねている点が特徴です。
ここでは、採用が安定している建設会社に共通するポイントについて解説します。
採用を「短期」ではなく「仕組み」で考える
採用がうまくいく建設会社は、採用を一時的な人手補充ではなく、継続的な仕組みとして捉えています。
人が足りなくなった時だけ求人を出す方法では、常に後手に回り、採用難から抜け出せません。
一方、仕組みとして採用を考える会社は、年間を通じて情報発信や母集団形成を行い、必要なタイミングで採用できる状態を維持しています。
たとえば、自社サイトの更新や現場の様子の発信を継続することで、今すぐ転職を考えていない層にも認知を広げています。
採用は短距離走ではなく、長期的な積み重ねが結果を生む活動であるという認識が、成果の差を生んでいます。
現場社員を巻き込んだ採用活動
採用活動を経営者や管理部門だけで完結させないことも、成果を出す建設会社の共通点です。
実際に現場で働く社員が関わることで、求人情報のリアリティが高まり、求職者とのミスマッチを防げます。
現場社員の声を求人原稿に反映したり、面接に同席してもらったりすることで、働くイメージを具体的に伝えることができます。
また、社員自身が会社の魅力を再認識するきっかけにもなり、組織の一体感向上にもつながります。
採用は人事だけの仕事ではなく、現場を含めた全社的な取り組みとして進めることで、建設会社ならではの強みが活かされます。
定期的な採用改善と見直し
採用がうまくいく建設会社は、一度決めた方法に固執せず、定期的に振り返りと改善を行っています。
応募数、採用単価、定着率などを確認し、何がうまくいき、何が課題なのかを整理します。
そのうえで、求人内容の修正や採用手法の見直しを行い、常に最適化を図っています。
建設業を取り巻く環境や求職者の価値観は変化しており、数年前の成功事例が通用しないことも珍しくありません。
改善を前提に採用活動を行うことで、変化に対応できる柔軟な採用体制が構築され、長期的な人材確保につながります。
まとめ
今回の記事では、建設業における採用が難しくなっている背景や、若者離れが起きている理由、そして採用を成功させるための考え方や具体策について解説しました。
ここまでお読みいただき、「考え方は理解できたが、自社の採用がなぜうまくいかないのかまでは整理できていない」と感じた方も多いのではないでしょうか。
建設業の採用は、単に求人を出すかどうかではなく、誰に向けて、何を、どの順番で伝えているかによって成果が大きく変わります。
採用活動を見直すことで、応募数の改善だけでなく、ミスマッチの防止や定着率の向上といった効果も期待できます。
一方で、自社の採用活動のどこに課題があるのかは、内部にいると客観的に判断しにくいというリスクもあります。
思い込みや過去の成功体験が、改善の妨げになっているケースも少なくありません。
現在、建設業・設備業に特化した採用支援として、求人ページや採用導線の無料診断を行っています。
- 求人内容が求職者に正しく伝わっているか
- 採用手法や媒体選びが目的に合っているか
- 応募までの流れに無駄や離脱ポイントがないか
「今のやり方で問題ないか確認したい」という段階でも問題ありません。
無料診断を受けてみたい方、サービスの詳細を知りたい方は、以下のページをご確認ください。