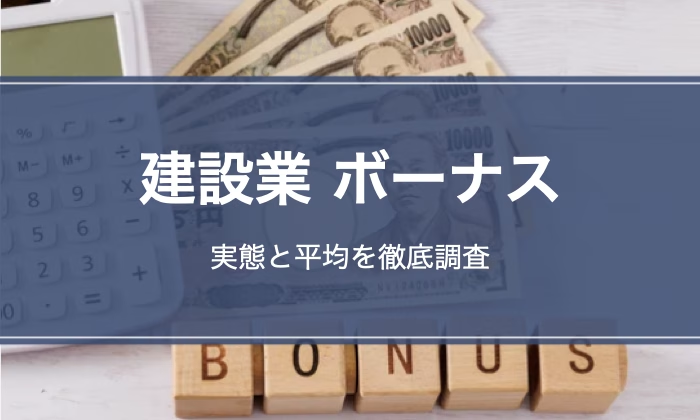「努力して働いているのに、ボーナスが出ないのは自分の会社だけなのか」と悩んでいるのではないでしょうか?
そこで、今回は建設業界におけるボーナスの平均支給額や、支給されない理由、ボーナスが多い企業の傾向について解説します。
この記事を読めば、建設業のボーナス事情の全体像や、自分に合った働き方・会社選びのヒントがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業のボーナスは本当に出ないのか?
「建設業 ボーナスなし」といった検索が多い背景には、待遇への不満や不安、そして将来への不透明感が見て取れます。
建設業界全体を見ても、ボーナス支給にはばらつきがあり、一概に「出ない」とも「出る」とも言い切れません。
ここでは、その実態に迫ります。
零細企業・個人経営ではボーナスがないケースも
建設業の中でも、特に従業員数10名以下の零細企業や一人親方のような個人経営においては、賞与の支給がないケースが非常に多いのが現実です。
実際に「建設業 ボーナスなし」と感じている人の多くが、こうした規模の会社で働いている可能性があります。
理由としては、以下のような構造的な制約が挙げられます。
| 規模 | 経営体力 | ボーナスの有無 |
|---|---|---|
| 大手ゼネコン | 資金に余裕あり | あり(年2回が一般的) |
| 中小企業 | 年によって波あり | 業績次第 |
| 零細企業・個人 | 経費でギリギリ | なし or 臨時手当レベル |
特に個人経営の場合、企業としての「月次・年次決算管理」が不十分なケースもあり、賞与支給の原資を年単位で積み立てる余裕がないことが多くなります。
そのため、ボーナスは出せる年と出せない年の差が極端で、従業員からすると「結局もらえない」という印象が残るのです。
また、賞与制度を設けていない企業も一定数存在しており、求人票に明記されていない限り、期待しすぎるのもリスクとなります。
転職や就職活動の際には、事前に「賞与制度の有無」「支給実績」まで確認することが重要です。
雇用形態(正社員・契約・派遣)による差異
建設業界では、雇用形態の違いによってボーナスの有無や支給額に大きな差が生じることがあります。
たとえば、正社員として大手建設会社に勤務している場合、安定して年2回のボーナスが支給されることが一般的ですが、契約社員や派遣社員には支給されない、あるいは極めて少額というケースも多く見られます。
以下に雇用形態別のボーナス傾向をまとめます。
| 雇用形態 | ボーナス支給の有無 | 支給額の傾向 |
|---|---|---|
| 正社員 | あり | 平均約60~90万円/年 |
| 契約社員 | 企業による(少ない) | 10~30万円/年(実績ありの場合) |
| 派遣社員 | 基本なし | 支給されないケースが大半 |
とくに注意すべきなのは、「派遣社員として働いている限り、ボーナスは一切期待できない」場合が多い点です。
企業によっては派遣元が「賞与に相当する手当」を含めて時給換算していることもありますが、それが実感として「ボーナスをもらっている」という感覚にならないことも多いでしょう。
そのため、将来的にボーナスを安定的に得たいと考えるなら、正社員登用を目指すことや、大手企業・ゼネコンを中心に転職活動を行う戦略が必要となります。
建設業のボーナス平均額はいくら?
建設業におけるボーナスの平均額は、業種や企業規模、職種によって大きく異なります。
本章では、統計データをもとに平均額を明らかにし、「建設業 ボーナス 平均」で検索する人の疑問を具体的に解消していきます。
国交省や厚労省の統計から見る平均支給額
建設業界全体としてのボーナスの平均額を把握するには、国土交通省や厚生労働省の公的な統計資料が参考になります。
以下は、2023年に公表された「賃金構造基本統計調査(厚生労働省)」と「建設労働需給調査(国土交通省)」などのデータを基にしたものです。
一般労働者(正社員)の建設業における年間賞与の全国平均は、約78万円前後で推移しています。
ただしこれはあくまで平均であり、企業規模や職種によって大きな開きがあります。
| 企業規模 | 年間賞与(平均) | 支給回数 |
|---|---|---|
| 大企業(従業員300人以上) | 約95万円 | 年2回 |
| 中小企業(従業員100~299人) | 約72万円 | 年1〜2回 |
| 小規模事業者(従業員100人未満) | 約50万円 | 年1回または不定 |
なお、建設業は景気や公共投資に大きく影響されるため、年度によって賞与額が上下する傾向があります。
業績連動型の企業も多く、良い年には100万円以上支給されるケースもある一方、景気低迷時にはゼロということも珍しくありません。
業種別(ゼネコン、設備、土木)での違い
建設業界内でも、ゼネコン、設備工事業、土木工事業などの業種によってボーナスの平均額には差があります。
これは業務内容や受注単価、利益率、取引先の支払いスパンなどが異なるためです。
以下に、代表的な業種別のボーナス平均額を比較した表を掲載します。
| 業種 | 平均年間ボーナス額 | コメント |
|---|---|---|
| ゼネコン(総合建設業) | 約85万円 | 公共事業・大型案件で安定。高待遇傾向。 |
| 電気・空調などの設備工事業 | 約70万円 | 民間案件中心。企業規模で大きな差。 |
| 土木工事業 | 約60万円 | 現場比率が高く、中小企業が多い。 |
このように、ゼネコンに勤務している方が平均的に高いボーナスを得られる傾向があります。
反対に、下請け構造の末端にある企業や、個人事業主に近い業者では賞与が出ない、もしくは「寸志レベル」にとどまることも多く見られます。
転職などを検討している場合、自身が希望する業種・職種がどの程度の賞与実績を持っているのかを知ることが、後悔のない選択につながります。
「建設業 ボーナス 平均」での検索ニーズに応える具体データ
「建設業 ボーナス 平均」で検索する人の多くは、自身の収入が他の人と比べて妥当なのかを知りたい、あるいは転職先を検討するうえで待遇の目安を把握したいといったニーズを持っています。
以下は、建設業の職種別に見たボーナス支給実績の一例です。
| 職種 | 平均年間賞与 | ボーナスの傾向 |
|---|---|---|
| 施工管理(建築) | 約90万円 | 管理職や経験年数で大きく変動 |
| 施工管理(土木) | 約80万円 | 公共事業の影響を受けやすい |
| 現場作業員 | 約50万円 | 零細企業ではなし or 臨時手当扱い |
| CADオペレーター | 約60万円 | 派遣社員では支給なしが多い |
上記データから分かるように、「建設業だから賞与が出ない」というのは誤解であり、あくまで職種・規模・雇用形態によって大きく異なります。
検索者が自身の状況と比較しやすいよう、具体的な数字とコメントを併記することが重要です。
また、求人票などでは「賞与あり」と記載されていても、実際の支給額や実績に触れていないケースがあるため、面接時に「過去の支給実績」や「賞与査定の基準」について確認しておくことをおすすめします。
ボーナスが多い企業は?建設業ランキング紹介
建設業界では、企業によってボーナスの支給額に大きな差があります。
ここでは、ボーナスが多いとされる企業をランキング形式で紹介し、傾向や対策も解説していきます。
「建設業 ボーナス ランキング」で注目される企業とは
「建設業 ボーナス ランキング」と検索する人は、ボーナスの多さを重視して就職・転職を考えている傾向があります。
特に業界経験者や若年層の求職者の間では、給与総額に占めるボーナスの割合に関心が集まっています。
そこで注目されるのが、財務が安定しており、大規模なインフラ整備や再開発事業を多く手がける大手企業です。
以下の表は、東洋経済オンラインや各社の有価証券報告書をもとにした、建設業におけるボーナスが多い企業の一例です。
| 順位 | 企業名 | 年間賞与(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | 鹿島建設 | 約180万円 |
| 2位 | 大成建設 | 約175万円 |
| 3位 | 清水建設 | 約160万円 |
| 4位 | 大林組 | 約155万円 |
| 5位 | 竹中工務店 | 約150万円 |
これらの企業は、「準大手」や「中堅ゼネコン」と呼ばれる企業と比べてボーナス水準が高く、年功序列型の昇給制度を持つ点も特徴です。
大手ゼネコンやインフラ系の安定企業の傾向
ボーナス支給額が高い企業には、共通した特徴があります。代表的なのが「大手ゼネコン」や「インフラ関連企業」です。
これらの企業は、景気の影響を受けにくい大型案件を多数抱えており、安定した収益を背景に高額な賞与を支給できる体力があります。
また、これらの企業は組合交渉によるボーナス支給も多く、毎年一定の基準に基づいた支給がされる傾向にあります。
賞与が業績連動である一方、ベースが高いため、最低限の支給額も他業界より高い水準に保たれているのが実情です。
加えて、インフラ系の企業(たとえばNEXCO、東京電力グループ、JR関連など)も賞与水準が高めです。
公共性の高い事業を担うこれらの企業は、業績の変動が小さく、賞与も安定的に支給される傾向にあります。
一方、地方の中小建設会社や下請け企業は、案件数・単価・利益率の面で厳しく、賞与は「年1回寸志レベル」または「なし」のところも少なくありません。
こうした企業との格差が、ランキング上位企業の魅力を際立たせています。
ボーナス支給の多い会社を選ぶ就職・転職戦略
ボーナスを重視するなら、就職・転職時に戦略的な企業選びが欠かせません。
まず意識すべきは「企業規模」と「案件規模」です。大規模インフラ工事や公共工事を安定して受注している企業は、ボーナス支給においても信頼できます。
次にチェックすべきは、求人情報や四季報などでの「過去の賞与実績」です。
「賞与あり」と記載されていても実際には支給実績が少ない企業もあるため、できれば面接で「昨年度の支給実績額」「業績連動かどうか」「支給回数(年何回)」を確認すると良いでしょう。
また、転職エージェントを活用するのも有効です。
特に建設業界に特化したエージェントであれば、非公開求人や内部事情、賞与額に関する情報を把握しているケースも多いため、客観的な視点でアドバイスをもらえます。
最後に、「ボーナスの多さ」だけにとらわれず、給与の総額(年収)や残業時間、福利厚生とのバランスを見ることも忘れてはいけません。
ボーナスが高くても、残業が多く精神的・体力的に厳しい職場では長続きしにくいものです。
ボーナスなしでも魅力のある働き方とは?
建設業ではボーナスが支給されない企業もありますが、それでも魅力的な働き方を実現する方法は存在します。
ここでは、収入の安定・向上や将来的なキャリア形成に役立つ選択肢について解説していきます。
ボーナスがなくても高単価な現場や日給制の魅力
「ボーナスがない=収入が低い」というわけではありません。
特に建設業界では、ボーナスがなくても高単価な日給制や出来高制の現場に就くことで、トータルの収入を大きく伸ばせるケースがあります。
たとえば、大型プロジェクトや都市部の再開発などでは、1日2万円以上の日給が設定されることも珍しくありません。
繁忙期で稼働日数が増えると、月収40万~50万円も十分に狙えるレベルです。
ボーナスがない代わりに「毎月安定して高収入が得られる」点は、手取り重視の働き方を希望する人にとって大きなメリットです。
また、協力会社や一人親方として現場に入ると、元請からの直接契約で中間マージンがカットされるため、さらに高い単価を受け取れる可能性もあります。
給与体系に柔軟性のある現場を選べば、年収ベースで見るとボーナス支給のある企業と遜色ない水準で働くことも可能です。
資格取得や独立による収入アップの道
ボーナスがない場合でも、資格やスキルによって収入を上げる道は十分に開けています。
特に建設業界では、資格の有無が直接的に日給や契約単価に影響するケースが多く見られます。
たとえば、以下のような国家資格を取得すると、現場での立場が上がり、月収・年収も向上します。
| 資格名 | 主な業務範囲 | 年収アップ例 |
|---|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 大規模建設現場の管理 | +100万円~150万円 |
| 電気工事士(第一種) | 屋内外の電気工事全般 | +50万円~100万円 |
| 土木施工管理技士 | 道路・橋梁などの工事監督 | +80万円~120万円 |
また、経験を積んだのちに「独立」という選択をとれば、収入を一気に伸ばすことも可能です。
独立後は自らが元請や下請を選べるようになり、収益構造を自分でコントロールできます。
独立には経理や法務など新たな知識が求められますが、最近では独立支援サービスや専門セミナーも増えており、支援体制も整いつつあります。
ボーナスに依存しない収入構造をつくるという意味でも、資格と独立は有力な選択肢と言えるでしょう。
将来的にボーナスのある企業に転職するためのスキルアップ法
「今はボーナスがないけれど、将来的には安定した大手企業に転職したい」と考える人にとっては、戦略的なスキルアップが重要です。
特に評価されやすいのが、即戦力として活躍できる資格や経験です。
まずおすすめなのが「施工管理技士」などの国家資格。
これらは求人票でも「有資格者優遇」として高く評価されており、実務経験+資格のセットで応募できる企業の幅が大きく広がります。
さらに、CADスキルや現場での安全管理、労務管理の知識もプラス評価されます。
また、転職成功のカギは「経験の言語化」にもあります。
過去にどのような現場を担当し、どんな役割を果たしたかをしっかり整理しておくことで、面接でのアピール力が大きく変わります。
ポートフォリオや職務経歴書のブラッシュアップも忘れずに行いましょう。
最近では、建設業界特化の転職エージェントやキャリア相談サービスも活用されています。
非公開求人の紹介や面接対策、キャリア設計のアドバイスを受けながら転職活動ができるため、特に初めての転職には心強いサポートとなります。
ボーナスをもらえる企業に転職するには、日々のスキル習得と実績の積み上げが不可欠です。
地道な努力が数年後に大きな成果となって返ってくるでしょう。
建設業界で「ボーナスのある働き方」を選ぶために
建設業で安定した収入を目指すうえで、ボーナス制度の有無は重要な判断材料です。
ここでは、ボーナスがしっかり支給される企業を選ぶための見極め方を解説します。
労働条件を見極めるポイント(就業規則・面接時確認)
まず、ボーナス支給の有無を判断するには「就業規則」と「労働契約書」の内容が非常に重要です。
企業によっては、「賞与あり」と記載しながら実際には業績次第で支給されないケースもあるため、文面の細かな表現を確認しましょう。
特にチェックすべき表現は以下の通りです。
| 記載例 | 意味 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 年2回支給(業績による) | 会社の業績次第で支給されない場合も | 過去の支給実績を質問する |
| 賞与制度あり(規定による) | 支給条件が別途規定で定められている | 具体的な支給条件を確認する |
| 賞与なし | 基本的に支給されない | 年収ベースで評価する必要あり |
面接時には、遠慮せずに「直近3年間のボーナス支給実績」や「部署ごとの支給の有無」など、具体的に質問しましょう。
曖昧な回答が続く場合は、制度が形骸化している可能性があります。
賃金体系・賞与制度のチェック項目
賃金体系や賞与制度の構造は、企業によって大きく異なります。
ボーナスがあると記載されていても、実際には「基本給の○ヶ月分」なのか、「業績連動のインセンティブ型」なのかによって実態は変わります。
以下の項目を確認すると、賞与制度の実効性を見極めやすくなります。
- 賞与の算定基準:評価基準が明確か、主観的評価ではないか
- 支給回数と時期:年1回か2回か、支給月はいつか
- 査定方法:人事評価と連動しているか、現場の上長の意見がどの程度反映されるか
- 支給実績:過去数年間の支給平均額
たとえば、「基本給が20万円で賞与が年2回・2ヶ月分」という場合、年間ボーナスは約80万円になります。
一方で、「基本給が低く、手当が多い給与体系」だと、賞与額が非常に低くなる可能性もあるため注意が必要です。
また、インセンティブ型の賞与を採用している企業では、プロジェクトの完成度や工期遵守、顧客満足度などの定量指標が評価項目に含まれているケースもあります。
こうした評価制度が透明で納得感のあるものであれば、高収入が目指せる可能性もあります。
福利厚生・手当とのバランス
ボーナスだけでなく、「総合的な待遇」を見て働き方を選ぶことも大切です。
福利厚生や手当が充実していれば、年収ベースで見たときに、ボーナスが多少少なくても実質的なメリットが得られる場合もあります。
代表的な手当には以下のようなものがあります。
| 手当名 | 内容 | 月額目安 |
|---|---|---|
| 住宅手当 | 家賃の一部を補助 | 1~3万円 |
| 家族手当 | 配偶者・子供の人数に応じて支給 | 5千円~2万円 |
| 資格手当 | 指定資格を取得した社員に支給 | 5千円~1万円 |
これらの手当や、健康診断・退職金制度・企業年金・交通費全額支給などの福利厚生を含めて考えることで、ボーナスの有無だけにとらわれない働き方の選択が可能になります。
特に中小企業では「ボーナスなし」でも手当が手厚く、結果的に生活の安定につながっているケースもあります。
転職先を選ぶ際には、求人票の金額欄だけでなく、全体の待遇を見て判断するようにしましょう。
まとめ
今回の記事では、建設業のボーナスについて解説しました。
ボーナスの有無や額は企業規模や雇用形態で大きく異なります。
就職・転職の際は、支給実績や給与体系を事前に確認し、自分に合った働き方を選びましょう。