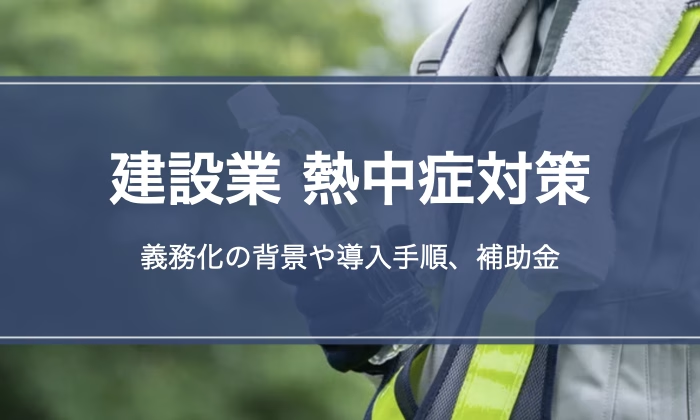現場での熱中症対策が「義務化」されたことで、どこまで対策すれば法令を満たすのか分からず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は建設業における熱中症対策の義務化内容と対応方法、活用できる補助金制度について解説します。
この記事を読めば、法的に必要な対策の具体例や補助金の申請方法、現場での実践ポイントがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
2025年6月から熱中症対策が義務化に
2025年6月1日より、厚生労働省の通達に基づき建設業における熱中症対策が法的に義務化されました。
対象は屋外作業を含む建設現場で、WBGT値(暑さ指数)の管理が求められます。
違反時には労働基準監督署の是正指導が入る可能性もあります。
義務化の背景と概要
建設業は他産業に比べて熱中症の発症率が高く、毎年7月〜9月にかけて多くの労災が発生しています。
特に真夏の屋外作業は高温環境下にさらされることが多く、命に関わるケースも後を絶ちません。
このような状況を踏まえ、厚生労働省は2025年6月より、建設業における熱中症対策を義務化する通達を発出しました。
義務化の主な内容としては、作業現場でのWBGT値(暑さ指数)の定期的な測定と、それに応じた作業時間・休憩時間の調整、また作業員への水分・塩分補給体制の整備が求められます。
また、熱中症の危険が高いと判断された際には、現場の一時中断を含むリスク回避措置を講じることも必要です。
今回の法改正は、単なる推奨事項から義務化への転換であり、事業者には実効性のある熱中症対策が強く求められています。
これにより、作業員の安全確保と労災防止の両立を図る狙いがあります。
対象となる現場と求められる管理措置
義務化の対象は、屋外で作業を行うすべての建設現場です。
特に足場組立・土木作業・舗装作業など、高温環境下での長時間作業が想定される現場は重点的に対策を講じる必要があります。
具体的に事業者が実施すべき管理措置は以下のとおりです。
| 対策項目 | 内容 | 実施のポイント |
|---|---|---|
| WBGT値の測定 | 作業場所における暑さ指数(WBGT)の計測 | 最低1時間ごとの測定、熱中症指数に応じた判断 |
| 作業計画の調整 | 高温時間帯の作業回避、休憩時間の確保 | WBGT値が高い時間帯を避けるシフト制の導入 |
| 水分・塩分の補給体制 | 現場にスポーツドリンクや塩タブレットを常備 | 定期的な声かけによる摂取の促進 |
| 応急処置体制 | 体調不良時の迅速な対応と救急搬送の準備 | 救急連絡先の明示と教育訓練の実施 |
これらの措置を怠ると、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けるリスクがあります。
今後、定期的な現場監査や帳簿確認を通じて、法令順守状況がチェックされる可能性も高まるでしょう。
このように、2025年6月からの義務化により、建設現場では従来の「努力義務」ではなく、明確な実行が必要となりました。
対策に不安がある事業者は、厚労省が配布する「建設業 熱中症対策マニュアル」や「建設業 熱中症対策 手順書」を活用し、組織的な対応を整えることが重要です。
建設業における熱中症の深刻な現状
建設業界では毎年、熱中症による死亡事故や重篤な健康被害が発生しています。
特に高齢作業員の多い現場ではリスクが増大しており、労災統計にもその傾向が明確に表れています。
ここでは、統計データや「建設業 熱中症対策 資料」などをもとに現状のリスクを詳しく解説します。
建設業界における熱中症の発生状況
建設業は屋外作業が中心であるため、他業種と比較して熱中症のリスクが非常に高いとされています。
厚生労働省の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、2023年における熱中症による死傷者数(休業4日以上)は全産業で881人、うち建設業は134人を占めています。
これは、全体の約15%が建設業に集中していることを意味し、特に7月~9月の夏季に集中して発生しています。
作業内容としては、足場作業やアスファルト舗装など、日射と高温にさらされる工程が多いことが原因です。
以下の表は、過去3年間の建設業における熱中症発生件数の推移を示したものです。
| 年 | 建設業の死傷者数(熱中症) | うち死亡者数 |
|---|---|---|
| 2021年 | 122人 | 5人 |
| 2022年 | 129人 | 6人 |
| 2023年 | 134人 | 7人 |
このように年々微増傾向にあることからも、従来の対策だけでは不十分であり、義務化に至った背景が浮き彫りとなっています。
高齢作業員が抱える特有のリスク
建設業界では人手不足の影響から、60歳以上の高齢作業員が多くの現場で活躍しています。
実際、国土交通省の統計によると、建設労働者のうち約35%が60歳以上というデータもあり、今後さらに高齢化が進む見込みです。
高齢者は加齢に伴い、体温調節機能や発汗機能が低下しやすく、脱水症状にも気づきにくいため若年層よりも熱中症にかかりやすく、また重症化しやすい傾向があります。
また、持病や服薬との関係で体温上昇が抑えにくいケースもあり、周囲の注意と補助が不可欠です。
このような背景を踏まえ、建設現場では「建設業 熱中症対策 手順書」などを活用した個別対応の徹底が求められています。
例えば、作業内容に応じた個別の休憩設定、体調の事前確認、暑さ指数による作業中止判断などを盛り込むことで、高齢作業員を守る体制が必要です。
現場管理者は「建設業 熱中症対策 資料」や厚労省の「職場のあんぜんサイト」を活用し、年齢・持病・体質など多様な作業員に対応したリスク管理を実行することが、今後ますます重要になります。
義務化された具体的な対策内容
2025年6月から建設業における熱中症対策が法的に義務化されたその内容はWBGT値の測定・掲示、水分補給環境の整備、作業時間の調整、マニュアルや手順書の作成・周知など、現場で実践すべき明確な基準を含みます。
ここでは義務化された各対策の内容と、現場での運用ポイントを詳しく解説します。
WBGT値の計測と掲示
WBGT(湿球黒球温度)値とは、気温・湿度・輻射熱をもとに算出される「暑さの指数」であり、熱中症リスクの判断基準として活用されます。
2025年6月以降、建設現場ではこのWBGT値を定期的に計測し、作業場の見やすい場所に掲示することが義務づけられました。
WBGT値が28℃を超えると中等度の熱中症リスク、31℃を超えると高リスクとされ、現場ではその数値に応じて作業の中断や休憩時間の追加、水分補給の促進といった具体的対応が求められます。
計測には携帯型のWBGT計やセンサー付き装置の活用が効果的で、現場責任者が定時にチェックする体制づくりが重要です。
作業時間の調整/休憩時間の明示
WBGT値をふまえ、建設現場では暑さ指数に応じた作業時間の調整が義務化されました。
具体的には、日中の気温が高まる11時~15時の作業を短縮または中止し、代わりに早朝・夕方の涼しい時間帯へ移行させる「時差勤務」の導入が推奨されます。
また、作業時間ごとに「定期休憩」の設定が必要であり、これを作業員に明示することが法的義務となります。
例えば、WBGTが28℃を超えた場合、1時間の作業に対して15分以上の休憩を確保することが厚生労働省の指針で推奨されています。
休憩時間は単なる“中断”ではなく、冷房の効いた休憩所や日陰での十分なクールダウンを含む必要があります。
水分・塩分補給の環境整備
熱中症を未然に防ぐには、こまめな水分・塩分補給が欠かせません。
そのため、建設現場では飲料水の常備が義務づけられ、さらに塩タブレットや経口補水液の配布、摂取タイミングの周知も求められるようになりました。
多くの現場で、自販機の設置や大型クーラーボックスの配置、個別に配布する携帯型ボトルの導入が進んでいます。
補給は「喉が渇いた時」では遅く、30分ごとの定期補給を促す声かけが効果的です。
また、熱中症対策の「建設業 熱中症対策マニュアル」に基づき、作業員への教育として、なぜ塩分が必要なのか・どのタイミングで補給すべきかといった基礎知識の共有も義務となりました。
熱中症対策マニュアルの作成と周知
建設現場では事業所ごとに「建設業 熱中症対策マニュアル」の作成が義務づけられています。
このマニュアルには、WBGT値の測定方法、暑さ指数ごとの作業可否基準、休憩の取り方、水分・塩分の補給方法、緊急時の対応フローなどが記載されます。
重要なのは、単にマニュアルを作るだけでなく、それを作業員全員に周知し、理解させることです。
朝礼や安全大会での説明、掲示物による視覚的共有、スマートフォンによる閲覧環境の整備など、現場に応じた工夫が必要となります。
特に外国人労働者が多い現場では、多言語対応やイラスト付きマニュアルの用意も検討すべきです。
内容が理解されていなければ、法令順守とは言えず、実効性のある対策とはなりません。
熱中症対策手順書の運用と活用方法
マニュアルに基づき、日々の現場運用を支えるのが「建設業 熱中症対策 手順書」です。
これは、WBGT測定→掲示→作業判断→休憩指示→飲料提供→体調確認→記録といった一連の流れを時系列で整理した実務向けの資料です。
例えば、以下のような手順書を作成することで、担当者が迷うことなく行動できるようになります。
| ステップ | 対応内容 | 記録の有無 |
|---|---|---|
| 1 | 朝のWBGT値測定・掲示 | チェックシートに記録 |
| 2 | 作業可否の判断と周知 | 掲示物・声かけ |
| 3 | 休憩時間・水分補給タイムの設定 | タイムスケジュール表 |
| 4 | 体調不良者の有無確認 | 作業前ヒアリング |
| 5 | 万一の緊急対応準備(搬送ルート・連絡先) | 緊急連絡表 |
このように手順書を活用することで、現場の誰もが統一された判断基準で動けるようになり、事故リスクを大幅に軽減できます。
現場特性に合わせて柔軟にカスタマイズし、作業の合間にも確認できるようなポータブル形式での提供が推奨されます。
罰則や企業責任のリスクも明確化
建設業における熱中症対策が「努力義務」から「法的義務」に変わったことで、必要な措置を怠った企業には労働安全衛生法違反として罰則が科される可能性が生じ、企業責任が一段と重くなっています。
以下では、法違反による罰則や、民事責任・元請業者の管理責任について解説します。
労働安全衛生法違反のリスク
法改正により、熱中症対策を怠った場合は「労働安全衛生法違反」として指導対象になる可能性があります。
たとえばWBGT値の未計測や、作業員への対策未周知、水分補給環境の不備などは、明確な法令違反と見なされるケースがあります。
労働基準監督署の立ち入り調査で違反が確認されれば、「是正勧告書」や「使用停止命令」が出され、最悪の場合は罰金刑が科されることもあります(労働安全衛生法第119条)。
また、熱中症による労働災害が発生した際、必要な措置を講じていなかったことが発覚すれば、重大な企業イメージの毀損にもつながります。
安全配慮義務違反と損害賠償
企業には労働契約法第5条に基づき「安全配慮義務」が課されており、作業員の健康を守るための十分な措置が求められます。
熱中症予防もこの範疇に含まれ、義務を怠った結果として作業員が死亡または後遺障害を負った場合、企業は損害賠償責任を問われる可能性があります。
損害賠償の内容は、入院費や休業補償だけでなく、慰謝料・逸失利益といった長期的な損失まで含まれるケースが多く、1件あたり数百万円〜数千万円規模になることも珍しくありません。
とくに法令が義務化された2025年6月以降は、「知らなかった」「対応が間に合わなかった」といった主張が通用しにくくなるため、全社を挙げてのリスク管理が求められます。
元請業者の管理責任にも注意
建設現場では、元請業者が一次・二次下請け業者の作業環境まで広く監督責任を負っています。
熱中症対策についても例外ではなく、下請業者の作業員が熱中症にかかった場合でも、「元請業者の安全管理が不十分」と判断される可能性があります。
たとえば、元請業者がWBGT値を計測していたとしても、下請業者の作業員に情報が共有されていなければ、管理責任が問われる余地があります。
そこで、以下のような「管理項目リスト」を整備し、元請としての対応状況を常にチェックできる体制が重要です。
| 管理項目 | 対応状況 | 確認方法 |
|---|---|---|
| WBGT値の計測・掲示 | 済/未 | 掲示板・写真記録 |
| 対策マニュアルの共有 | 済/未 | 朝礼での周知状況 |
| 水分補給環境の整備 | 済/未 | 現場点検チェックリスト |
| 緊急時の搬送体制 | 済/未 | 救護連絡表・訓練記録 |
このような対策の「見える化」を進めることで、万が一の事故時にも適切な管理体制を証明しやすくなり、法的リスクや企業責任の回避につながります。
下請との連携体制の強化こそが、義務化時代の安全管理に不可欠な視点です。
熱中症対策に活用できる補助金制度
熱中症対策の義務化に伴い、現場での設備導入を支援する補助金制度の活用が注目されています。
多くの都道府県では、「建設業 熱中症対策 補助金」を設け、空調服やミストファン、WBGT計などの導入費用を一部負担しています。
ここでは、補助対象設備の種類や、申請の手順、注意点について解説します。
対象となる設備と補助内容
各自治体が実施する「熱中症対策補助金」では、一定の条件を満たせば、熱中症対策に有効な機材の購入・設置費用が補助されます。
主な対象設備は以下の通りです。
| 設備名 | 概要 | 補助対象例 |
|---|---|---|
| WBGT計測器 | 現場の暑さ指数を計測する機器 | 携帯型・固定式の測定器 |
| 空調服 | 作業員の体温上昇を抑えるファン付き作業服 | バッテリー・ファン付き上下セット |
| ミスト扇風機 | ミストによる気化熱で周囲の気温を下げる機器 | 移動式・タンク一体型タイプ |
| 冷却ベスト・タオル | 着用することで体温の上昇を防ぐ保冷グッズ | 保冷剤付きベスト・首元冷却タオル |
補助率や上限金額は都道府県によって異なり、例えば東京都では最大50万円(補助率1/2)まで支給されるケースもあります。
なお、すべての設備が対象となるわけではないため、必ず事前に補助要綱を確認することが大切です。
補助金申請の流れと注意点
補助金の申請は、多くの自治体で以下の流れに従って行われます。
[box04 title=”補助金申請の流れ”]
- 補助対象事業の公募開始を確認
- 交付申請書の提出(見積書・製品カタログなどの添付が必要)
- 審査・交付決定の通知
- 機器購入・設置・使用開始
- 実績報告書の提出・検査
- 補助金の交付(後払い)
[/box04]
重要な注意点は、「交付決定前に機器を購入してしまうと補助対象外となる」ことです。
特に現場で早急な導入が求められるケースでも、必ず交付決定通知を受けてからの購入・設置がルールです。
また、補助金の予算には上限があり、先着順や予算消化で締め切られる場合もあります。
そのため、最新情報の取得と迅速な申請準備が重要です。
申請書の書き方や必要書類に不安がある場合は、商工会議所や地域の建設業協会に相談するとスムーズです。
補助金制度はコスト負担を抑えながら義務化対応を進める有効な手段です。
うまく活用することで、現場の安全性向上と経営負担の軽減を両立できます。
まとめ
今回の記事では、建設業の熱中症対策について解説しました。
2025年6月から義務化された対策には罰則も伴います。
マニュアルや手順書の整備だけでなく、現場に即した実践が重要です。
補助金も活用し、早めの対策を徹底しましょう。