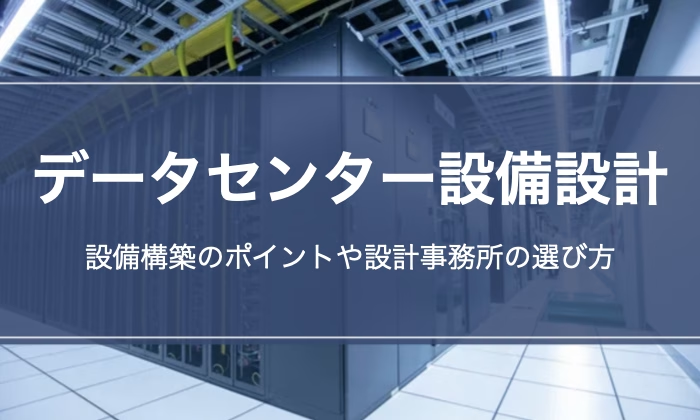私自身データセンターの設備運用に携わっていたからこそいえますが、データセンターの設備設計は、他の建築施設とは異なり、高度な専門性が求められる分野です。
「電源や空調、耐震性、セキュリティなど、多岐にわたる要素を的確に設計しなければ、稼働後のトラブルや運用コスト増につながってしまう」そんな不安を抱えて検索されたのではないでしょうか。
そこで、今回はデータセンターに特化した設備設計のポイントと設計事務所の選び方について解説します。
この記事を読めば安全・効率的なデータセンターを構築するために必要な設計上の考慮点と、依頼先を選ぶ際の判断基準がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
データセンターの設備設計が重要な理由
データセンターの設備設計は、常時稼働・大規模な電力使用・高度なセキュリティが求められる特殊な施設であるため、通常の建築設備とは異なる設計思想が必要です。
以下では、その設計における重要な視点を具体的に解説します。
24時間稼働を前提とした信頼性設計
データセンターは24時間365日、停止することなく稼働し続ける必要があります。
システム障害や機器停止によるダウンタイムは、業務への多大な影響や損失を引き起こす可能性があるため、設備設計段階から高い信頼性を担保することが求められます。
そのためには、空調・電源・通信設備などすべての基幹インフラに対して、故障を未然に防ぐための保守性・冗長性を確保することが基本です。
例えば、空調機器の多重設置や、配電系統の二重化などが検討されます。
また、点検時にも稼働を止めずに作業できるような、系統切替やバックアップの仕組みも必要です。
さらに、サーバールーム内の温度・湿度・電圧などを常時モニタリングし、異常があれば即時に通知・対応できる体制も重要となります。
人為的なミスを防ぐためのアクセス制限や監視カメラの設置も、信頼性を高める要素のひとつです。
熱負荷・電力需要に対応したシステム構成
サーバーや通信機器が密集するデータセンターでは、発熱量が非常に大きく、適切な冷却設計が欠かせません。
また、高密度なシステム構成により、大量の電力を安定的に供給する電源設計も重要です。
例えば、サーバーラック1台あたり数kWもの電力を消費することが一般的で、施設全体では数百kWから数MWに達するケースもあります。
この負荷に応じた変圧器や配電盤、無停電電源装置(UPS)の導入が必須です。
空調面では、従来の空冷方式に加え、液冷方式やスポット冷却などの先進的な技術の活用が進んでいます。
さらに、サーバーの配置を考慮した「ホットアイル/コールドアイル」方式など、効率的な気流制御も設計段階で取り入れるべきです。
以下は、電力・熱負荷に対する設計要素の一例です。
| 設計項目 | 設計上の考慮点 | 導入例 |
|---|---|---|
| 電源設備 | 高負荷対応・冗長構成 | UPS、発電機、二重系統化 |
| 冷却設備 | 発熱機器に応じた冷却能力 | 空冷+液冷併用、エアフロー制御 |
| 監視システム | 温度・湿度・電流の常時監視 | BMS・DCIMシステムの導入 |
災害・停電対策としての冗長設計
データセンターは災害時にもサービスを止めないことが重要視されるため、災害や停電への備えとして「冗長設計」が必要不可欠です。
冗長設計とは、一つの系統に障害が発生しても、別の系統で代替できるようにする設計手法のことです。
たとえば、商用電源が停止してもシームレスに電源供給を継続できるように、UPSや自家発電機のバックアップ体制を構築します。
UPSは瞬時に切り替えが可能なため、サーバーへの影響を最小限に抑えられます。
また、火災・浸水・地震などに備え、建物全体の耐震設計やラック固定、床下配線の保護、防火区画の分離なども行います。
サーバールーム内の消火設備は、機器を損傷しにくいガス系消火設備(例:ハロン代替ガス)が採用されることが多く、火災による二次被害の抑制が可能です。
災害リスクを最小限に抑えるためには、地域特性を踏まえた設計や、事業継続計画(BCP)との整合性も必要です。
緊急時に即座に対応できるよう、運用マニュアルの整備と定期的な訓練も重要な要素となります。
データセンター設備設計の主な対象設備
データセンターにおける設備設計では、特に空調・電源・防災・防犯の各設備が重要視されます。
これらはサーバーの安定稼働やセキュリティの確保に直結するため、それぞれの機能や構成について最適化が求められます。
空調設備:高発熱機器への対応策
データセンターでは、大量のサーバーやネットワーク機器が常時稼働しており、室内は高い熱負荷にさらされます。
そのため、空調設備の設計は、単なる冷房能力だけでなく、効率的な熱移動・空気循環を前提とした構成が必要です。
よく用いられる方式のひとつが「ホットアイル/コールドアイル」方式です。
これは、サーバーラックの排熱と吸気を空間的に分離し、空気の短絡を防ぐ配置手法です。
これにより、冷却効率が大幅に向上し、省エネルギーにもつながります。
近年では、水冷式やラック冷却といった局所冷却方式も導入されており、機器の密度が高いエリアに対応する柔軟な冷却設計が重要です。
さらに、冷却能力の冗長化も不可欠で、空調機器が故障しても他の機器で対応できるような冗長構成が一般的です。
以下は、空調設備の構成例を示した表です。
| 冷却方式 | 特徴 | 主な導入シーン |
|---|---|---|
| 空冷方式 | 一般的な冷却方式。設計が比較的容易 | 中小規模のデータセンター |
| 水冷方式 | 高密度熱負荷に対応。省スペース | 大規模・高集積な施設 |
| 局所冷却 | ラック単位で冷却。個別制御が可能 | ハイパフォーマンスエリア |
電源設備:UPS・非常用発電の構成
電源設備は、データセンターの中でも特に重要な要素のひとつです。
サーバーが一瞬でも停止すると、取り返しのつかないトラブルや損失につながるため、停電や瞬断への対策が不可欠です。
まず基本となるのが、UPS(無停電電源装置)です。
これは停電時に瞬時に電力を供給し、非常用発電機が立ち上がるまでの数分間をカバーする装置です。
UPSにはラインインタラクティブ方式やオンライン方式があり、用途に応じた選定が求められます。
加えて、商用電源が停止した場合でも電力供給を継続できるように、ディーゼル発電機やガスタービンなどの非常用発電機を設置します。
これらの発電機には、燃料供給の冗長性や定期的な試運転計画も設計段階で考慮すべきです。
さらに、配電系統の二重化、切替盤の自動制御、系統ごとの負荷分散といった設計も必須です。
信頼性を最大限に高めるためには、Tier基準(Uptime Instituteの信頼性指標)に準拠した設備構成が推奨されます。
防災・防犯設備:アクセス制御と消火設備
データセンターには、高価な機器や重要なデータが集中しているため、防災・防犯設備の整備も欠かせません。
物理的な侵入からの保護と、災害発生時の被害最小化を両立させることがポイントです。
まず、防犯面では、建物への入退室管理が重要です。
ICカードや生体認証を使ったアクセス制御システムにより、限られたスタッフのみがサーバールームに入れるように制限します。
監視カメラの設置と映像の長期保存も、セキュリティ体制の一環として不可欠です。
一方、防災面では、火災対策として自動火災報知設備やガス系消火設備(例:不活性ガスやハロン代替ガス)を採用します。
通常の水を使用するスプリンクラーでは、精密機器に重大な損傷を与える可能性があるため、機器に優しい消火方式を選定する必要があります。
さらに、地震対策としては耐震構造の採用やサーバーラックの固定、二重床の支持設計なども重要です。
こうした設備はすべて、設計段階で計画的に組み込むことで、より強固で安全なデータセンターが実現します。
設備設計時に考慮すべきポイント
データセンターの設備設計では、設計初期段階から将来的な拡張性や省エネ性能、保守性までを見据えた計画が求められます。
ここでは、BIM活用、省エネ・ZEB対応、保守性を意識した設計の3つの観点から解説します。
BIMや3D設計ツールの活用
BIM(Building Information Modeling)や3D設計ツールの活用は、複雑な設備系統を持つデータセンターにおいて非常に有効です。
これらのツールを用いることで、設計段階から施工・維持管理までのプロセスを一元化でき、設計ミスや施工段階での干渉リスクを大幅に減らすことが可能になります。
たとえば、配管やケーブルラックが他の設備と干渉していないかを3D空間で事前に確認することができるため、施工現場での修正工事を最小限に抑えられます。
また、情報を持った3Dモデルが完成すれば、竣工後の運用・保守にも活用でき、長期的な管理コストの削減にも寄与します。
さらに、複数の関係者(建築、電気、空調、通信など)が同じモデルを共有することで、設計段階からの整合性が保たれ、設計の質とスピードが向上します。
BIMは単なる図面作成のツールではなく、プロジェクト全体の効率化を実現する重要な基盤です。
省エネ・ZEB化への対応
データセンターは大規模な電力を消費する施設であるため、省エネ対策は設計段階からの必須要件です。
近年では、建築物のZEB(Net Zero Energy Building)化を目指した設備設計も推進されており、エネルギー効率の向上がますます重要になっています。
省エネ設計の代表的な取り組みとしては、空調効率を高める気流制御の最適化、自然換気の利用、外気冷房(Free Cooling)やヒートリカバリーの導入などが挙げられます。
また、高効率なUPSや照明設備、可変速制御のファン・ポンプの導入も有効です。
ZEB化を目指す場合、設備単体の省エネだけでなく、建築と設備の一体設計が必要です。
たとえば、断熱性能の高い外壁を採用することで冷房負荷を低減し、同時に高効率の熱源機器を組み合わせるといったアプローチが求められます。
以下は、省エネ・ZEB対応に向けた主な取り組みの一覧です。
| 項目 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 空調制御 | 外気利用・局所冷却など | 冷却コストの大幅削減 |
| 電源設備 | 高効率UPS・自動制御 | 待機電力の削減 |
| 断熱設計 | 高性能な建材の使用 | 外気の影響を最小化 |
運用・保守までを見据えた設計
設備設計は施工完了がゴールではなく、建物が稼働した後の「運用・保守」のフェーズまでを視野に入れて設計を行う必要があります。
特にデータセンターでは、設備が複雑かつ稼働を止められないため、保守性の高さが施設の安定運用に直結します。
たとえば、空調や電源設備の点検・交換がスムーズに行えるように、作業スペースを十分に確保した配置計画が求められます。
また、系統ごとに設備をゾーン分けしておくことで、運用中でも一部を停止して保守が可能な構成とすることも有効です。
さらに、BMS(ビルマネジメントシステム)やDCIM(データセンターインフラ管理)などのモニタリングシステムを設計段階から組み込んでおけば、設備の稼働状況をリアルタイムで監視・記録でき、異常時の早期対応や予防保全が可能となります。
このように、保守性を高める設計は、長期的な信頼性とコスト削減の両面に寄与する重要な視点です。
初期段階から「保守する人」の視点を取り入れることが、トラブルの少ないデータセンター運用につながります。
設計事務所選びで失敗しないために
データセンターのような高度な設備が求められる建築物では、設計事務所の選定がプロジェクト全体の成否を左右します。
以下の3つの観点から慎重に確認しましょう。
データセンター実績の有無を確認
データセンターの設計は、一般的な建築とは大きく異なる専門性が求められます。
高密度な設備、極めて高い信頼性、24時間365日の連続運転、非常時の冗長性確保など、多くの要件を満たす必要があるためです。
そのため、まず確認すべきは「過去にデータセンターの設備設計実績があるかどうか」です。
経験のある設計事務所は、設計段階でのリスク想定や、構築後のトラブル事例を踏まえた対応が可能です。
過去にどのような規模の案件に携わり、どのフェーズまで関わったのかも確認するとよいでしょう。
また、Tier基準(Uptime Instituteが定めるデータセンターの信頼性指標)への理解や、サーバールームの熱負荷計算に関する知見の有無も重要です。
建築・構造との調整力があるか
設備設計がいくら優れていても、建築・構造設計との整合性が取れていなければ実際の施工段階で大きな問題になります。
特にデータセンターでは、空調や電源設備が大型化しやすく、それらを効率よくレイアウトするために建築との調整が不可欠です。
たとえば、空調機械室の配置、ダクトや配線ルート、耐震架台の設置など、多岐にわたる項目で調整が求められます。
設計事務所を選定する際は、過去のプロジェクトにおいて、どのように他分野の設計者と連携を取りながら整合性を図ってきたのか、具体的な事例を聞いてみましょう。
また、BIMを用いた設計調整が可能かどうかも、調整力の指標になります。
| 調整項目 | 必要な連携先 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 空調機械室の配置 | 建築設計 | 天井高や搬入経路との整合性 |
| 重量設備の架台 | 構造設計 | 荷重配分と床構造の適合 |
| 電源配線ルート | 建築・構造 | 貫通部の位置や防火対策 |
施工や運用フェーズへの理解があるか
設備設計は図面を描くだけではなく、その設計が「どのように施工され、どう運用されるか」まで見据える必要があります。
特にデータセンターでは、施工時の省力化やトラブルの防止、保守点検のしやすさが重要視されます。
たとえば、空調機器の更新時にクレーン作業が必要かどうか、保守スペースが十分に確保されているか、ケーブルの増設が容易かなど、運用を考慮した設計が求められます。
また、施工会社との打ち合わせ経験が豊富である設計事務所は、現場での収まりや施工の実現性を意識した設計ができるため、後工程での手戻りが少なくなります。
さらに、竣工後の点検マニュアル作成や、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)との連携支援など、運用面でも頼れるパートナーであるかを見極めることが大切です。
まとめ
今回の記事では、データセンター設備設計における基本的な考え方から具体的な技術、設計事務所の選び方までを解説しました。
ITインフラの要であるデータセンターにおいて、設備設計の質は稼働率や安全性に直結します。
設計を依頼する際は、実績・技術力・対応力の3つを軸に慎重に検討しましょう。