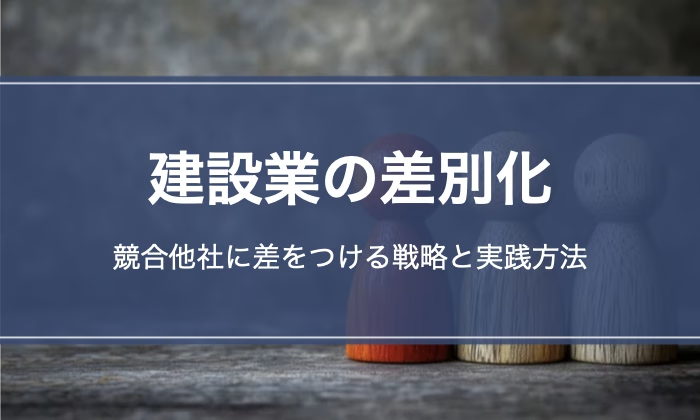「価格競争に巻き込まれて利益が出ない」ということはありませんか?
近年、建設業界では競合他社との価格競争が激化し、値引き合戦に疲弊している企業も多いのではないでしょうか。
「ウチならではの強みを活かして、他社と差別化したい」と思っても、どこをどう変えれば良いのか分からないという声をよく聞きます。
そこで、今回は建設業界で他社と差をつけるための差別化戦略と実践方法について解説します。
この記事を読めば、自社の強みの見つけ方や具体的な差別化の切り口、成功事例までがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業における「差別化」の重要性
建設業界では競争が激化しており、価格競争に巻き込まれる企業も少なくありません。
この状況を打破するには、他社と異なる「差別化」の視点が不可欠です。
以下でその背景と必要性を詳しく解説します。
競争が激化する建設業界の現状
建設業界は年々厳しさを増しています。
新規参入の増加や公共工事の減少、民間投資の不安定化などにより、企業間の競争が激化しています。
また、労働人口の減少により、職人や技術者の確保も難しくなり、人的リソースの取り合いも起きています。
さらに、デジタル技術の導入や環境配慮の対応など、多様な変化への適応が求められているのが現状です。
特に中小の建設業者にとっては、大手と同じ土俵で戦うことは容易ではありません。
差別化せずに汎用的なサービスを提供していると、価格でしか勝負できず、利益を削って案件を取りに行くことになります。
このような状況を回避するためには、「他社とは異なる価値」を持つことができるかどうかです。
価格競争に巻き込まれる危険
差別化できていない建設会社は、顧客から「どこに頼んでも同じ」と見なされてしまい、価格だけで判断される傾向があります。
すると値引き合戦が始まり、利益率はどんどん低下します。
利益が出にくくなると、社員の待遇や品質管理にも影響が出て、結果としてサービスの質も低下してしまうという悪循環に陥るのです。
以下は、価格競争によって起きる負のスパイラルを示した表です。
| 要因 | 影響 | 結果 |
|---|---|---|
| 価格競争に巻き込まれる | 利益率の低下 | 人材確保・品質維持が困難に |
| 値引きで受注 | コスト削減が必要になる | 品質・信頼の低下 |
このような事態を防ぐには、「価格」以外の価値を顧客に明確に伝える力、つまり差別化の戦略が重要になります。
なぜ今「差別化」が必要なのか?
かつては、「地元の建設会社」というだけで選ばれていた時代がありました。
しかし現在は、顧客もインターネットやSNSを通じて多くの情報を収集し、比較検討を行うようになっています。
これにより、単に「建てる」だけの会社は選ばれにくくなりました。
さらに、SDGsへの対応やZEB(ゼロエネルギービル)のような省エネ建築のニーズの高まり、デザイン性重視の若年層の増加など、顧客の価値観が多様化しています。
その中で「自社ならではの価値」を提供できなければ、顧客の記憶にも選択肢にも残れません。
差別化は、価格競争を避けて利益を確保するだけでなく、長期的に顧客から選ばれ続けるための「企業ブランド」の構築にもつながります。
今、建設業にこそ求められているのは「選ばれる理由をつくる力」なのです。
差別化とは何か?建設業における基本的な考え方
建設業で「差別化」とは、単に価格や広告戦略を変えることではありません。
他社と明確に異なる価値を提供し、顧客に選ばれる理由を構築することが重要です。
以下でその基本的な考え方を解説します。
差別化=他社と異なる価値の提供
差別化とは、自社が提供する商品やサービスにおいて、他社にはない独自の価値を打ち出し、顧客に「選ばれる理由」を作ることです。
これは価格を下げることとは異なり、「高くても頼みたい」と思わせる強みを明確に打ち出すことが求められます。
建設業においての差別化は、技術力・対応力・デザイン性・工期の柔軟さ・地域密着性など、多様な視点から構築できます。
顧客が施工会社を選ぶとき、単に「安いから」という理由だけではなく、「自分の希望をよく聞いてくれる」「安心できる」「実績がある」などの心理的・機能的な価値も判断材料になります。
他社と違う価値を提供するためには、まず「自社がどんな会社なのか」「顧客は何を求めているのか」を深く理解する必要があります。
これらを踏まえて、「自社独自の強みを言語化する」ことが差別化の第一歩となります。
建設業ならではの差別化要素とは?
建設業界における差別化のポイントは、業種特有のニーズや顧客心理に基づいたアプローチにあります。
特に以下のような切り口は、多くの企業で活用されています。
| 差別化要素 | 具体的な例 | 顧客に与える印象 |
|---|---|---|
| 施工技術・専門性 | 耐震工法に特化、木造リノベ専門 | 高品質で安心できそう |
| 対応力・柔軟性 | 短納期対応、小規模案件にも対応 | 相談しやすく頼りになる |
| デザイン性 | 女性建築士による設計提案 | センスが良い、希望が形になる |
| 地域密着 | エリア限定施工、地元イベント協賛 | 信頼できてアフターも安心 |
| 環境配慮 | 省エネ住宅、再生資材の活用 | 企業姿勢に共感できる |
このように、顧客にとっての「安心」「納得」「満足」につながる要素を見つけ、それを明確に伝えることが差別化戦略の核になります。
よくある誤解と落とし穴
差別化を試みる中で、よくある誤解のひとつが「とにかく他社と違えばいい」という考え方です。
確かに独自性は重要ですが、顧客が求めていない部分での差別化は意味を持ちません。
たとえば、特殊な建材を使った施工が差別化になると考えても、それが顧客のニーズに合っていなければ選ばれる理由にはなりません。
また、差別化を「広告文句」だけで完結させてしまうケースも見られます。
ホームページに「高品質・低価格」と書いてあるだけで、実際の施工内容や実績、根拠が示されていなければ、信頼性を欠く結果となります。
差別化はあくまで“行動や提供価値の中身”に基づいて語られるべきであり、見せかけだけの差別化は逆効果になる可能性すらあります。
さらに、自社の強みが現場スタッフに共有されていないというのもよくある落とし穴です。
現場と営業、広報が同じ認識を持たなければ、顧客接点でバラバラな印象を与えてしまい、ブランド構築は難しくなります。差別化は「一貫性」が鍵です。
建設業で使える差別化の切り口
建設業で差別化を実現するには、顧客のニーズに合った独自の「切り口」を見つけることが重要です。
以下では、実際に成果を上げやすい差別化の具体例を5つ紹介します。
技術力・施工品質で差別化
建設業において最も基本的かつ信頼性を高める差別化が、「技術力」や「施工品質」によるものです。
高精度な施工、独自工法、資格保有者の多さなどは、顧客に安心感と信頼を与えます。
例えば、耐震補強に強みを持つ企業や、ゼロエネルギー住宅(ZEH)の設計・施工に対応できる企業は、専門性が高く付加価値が明確です。
また、「施工不良ゼロ保証」「自社大工による責任施工」なども差別化の要素になります。
こうした品質面での差別化を行うには、第三者機関の認証取得や施工実績の公開、顧客の声を積極的に発信するなど、「根拠のある実力」を伝える工夫が求められます。
接客対応・アフターサービスで差別化
近年、顧客の建設業者選びの基準は「人」や「対応の丁寧さ」にも重きを置く傾向があります。
いかに技術が高くても、対応が不親切であればリピートや紹介にはつながりません。
初回の問い合わせ対応から契約後のフォローまで、顧客目線に立ったコミュニケーションを徹底することで差別化が可能です。
また、施工後の定期点検や緊急時の即時対応など、アフターサービスの充実は大きな安心材料となります。
さらに、SNSやチャット対応、マイページ機能の導入など、デジタルを活用したサービス提供も注目されており、こうした取り組みは若い世代にも好印象を与えるポイントとなります。
ターゲット特化型(高齢者住宅・工場・店舗専門など)
「すべてのニーズに応える」ことを目指すよりも、対象を絞った方が顧客に強く訴求できるケースがあります。
これは「ターゲット特化型」の差別化戦略です。
例えば、バリアフリーや手すりの設置などを得意とする「高齢者住宅専門」、設備や動線に精通した「工場建設専門」、内装やブランドイメージに注力する「店舗専門」など、それぞれのニーズに特化したサービス展開が可能です。
特化型にすることで、スタッフの経験値やノウハウも蓄積されやすくなり、結果として顧客満足度の向上とリピート率アップにもつながります。
| ターゲット層 | 主なニーズ | 対応内容の例 |
|---|---|---|
| 高齢者住宅 | バリアフリー、安全性 | 手すり・段差解消・介護設備対応 |
| 工場・倉庫 | 動線・耐久性・省エネ | 設備重視の設計、高天井や大型扉の設置 |
| 飲食・物販店舗 | デザイン・導線・開業支援 | 内外装提案、厨房設計、開業相談 |
デザイン性・エコ素材の活用
特に個人住宅や店舗などでは、機能性だけでなく「見た目」「環境配慮」も選定の決め手になります。
そうした文脈での差別化が「デザイン性」や「エコ素材の活用」です。
例えば、自然素材(無垢材や漆喰など)を使用した住宅は、健康志向や環境意識の高い層に支持されます。
また、断熱性能や太陽光発電などを標準装備にした省エネ住宅は、長期的なコストパフォーマンスを重視する顧客にアピール可能です。
さらに、女性設計士による細やかな設計提案や、インテリアと一体化した住宅設計などもデザイン重視の差別化として有効です。
機能+感性で選ばれる建設会社を目指すことで、競合との差を明確にできます。
地域密着型サービスの強化
建設業では「地元で信頼されているか」が大きな差別化要素になります。
特に中小企業にとっては、「地域密着型」という視点を強みにすることで、顧客の不安を払拭しやすくなります。
地域イベントへの協賛、地元工務店ネットワークとの連携、災害時の即時対応など、地元ならではの対応力がアピールポイントとなります。
また、地元の土地勘があることで、地盤や気候、自治体の補助制度などを活かした最適な提案ができるのも強みです。
口コミや紹介が多い業界だからこそ、「地域に根ざしているか」は顧客にとって安心材料です。
HPやチラシにも地域名を明記し、施工実績を地図や写真で掲載するなど、「地元のプロ」としての姿勢を前面に出すと効果的です。
自社の強みを見つける方法
自社を差別化するには、まず「強み」を把握することが不可欠です。
ここでは、建設業において活用しやすい強みの見つけ方を4つの観点から解説します。
SWOT分析の活用
SWOT分析とは、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の頭文字を取ったフレームワークで、自社を取り巻く内外環境を整理するための手法です。
これにより、他社と差をつけられる独自性を客観的に見出すことができます。
例えば、「地域密着の施工実績が豊富(強み)」「技術者の高齢化(弱み)」「再開発エリアでの需要増(機会)」「大手との価格競争(脅威)」など、自社の立ち位置を明確にしやすくなります。
SWOT分析は、経営層だけでなく現場や営業担当など、複数部門の視点を集めて実施すると効果的です。
また、分析結果から「強み × 機会」の組み合わせを狙うことで、戦略的な差別化が可能になります。
なお、SWOT分析については、以下の記事で詳しく解説しています。
https://construction-tech.site/industry-swot/
お客様アンケートでニーズを探る
本当の意味での「強み」は、自社が主観的に考えるものではなく、顧客が「価値がある」と感じるポイントです。
そのため、既存顧客に対してアンケートを実施することは、非常に有効な方法です。
たとえば、以下のような設問を盛り込むと、自社の魅力や他社との違いが浮き彫りになります。
- なぜ当社を選んだのか?
- 他社と比較して良かった点は?
- 今後期待するサービスは?
- 不満や改善してほしい点は?
このようなアンケート結果は、営業資料やWebサイトの改善にも活用可能です。
さらに、コメント内容は口コミやお客様の声として二次活用することもでき、信頼性向上にもつながります。
顧客満足度調査や定期フォローの一環として、年に1回程度実施するのが理想的です。
オンラインフォームやQRコードを使えば、回答のハードルも下げられます。
競合調査のポイントとツール紹介
自社の強みを見つけるうえで欠かせないのが、競合の調査です。
なぜなら、「他社がやっていないこと=差別化」だからです。
競合のサービス内容や価格帯、PR戦略を知ることで、自社の独自性を明確にできます。
調査する際の主なポイントは以下の通りです。
| 調査対象 | チェックポイント | 活用ツール |
|---|---|---|
| 公式Webサイト | サービス内容、価格帯、施工実績 | Google検索、Wayback Machine |
| 口コミ・評判 | 強み・弱みの傾向把握 | Googleビジネスプロフィール、エキテン |
| SNS発信 | 訴求ポイントや顧客層 | X(旧Twitter)、Instagram |
また、国土交通省の「建設業者検索システム」や地域の入札・契約情報も参考にすると、競合の動きが見えてきます。
分析結果をもとに、まだ競合が対応していないニーズや未開拓の顧客層に向けた戦略を立てましょう。
社員のスキル・社風も差別化要素になる
建設業の現場では「誰が施工するか」が成果に直結するため、社員のスキルや対応力、さらには社風そのものが大きな差別化要素となります。
例えば、以下のような特長が挙げられます。
- ベテラン職人が多数在籍している
- 若手技術者が最新技術に対応可能
- 女性スタッフによる丁寧な対応
- チームワークが良く、施工のスピードが速い
このような点は、お客様にとって「見えにくい価値」だからこそ、意識的に発信することが重要です。
施工中の様子を写真付きで紹介したり、社員インタビューを掲載したりすることで、信頼感や親近感が増します。
また、社員教育への投資や資格取得支援制度の有無も、「育成力がある企業」としてのブランディングにつながります。
社風や人材力は模倣されにくい差別化ポイントであり、持続的な競争優位性の鍵を握ります。
差別化を活かすためのマーケティング施策
せっかく見つけた自社の差別化ポイントも、伝わらなければ意味がありません。
ここでは、強みを効果的に届け、売上につなげるためのマーケティング施策を紹介します。
ホームページやSNSでの情報発信
建設業におけるマーケティングの要は、「認知の獲得」と「信頼の構築」です。
ホームページとSNSは、その両方を実現できる重要な媒体です。
自社の施工実績やスタッフ紹介、得意分野などを定期的に発信することで、「何が強みなのか」が明確に伝わり、受注にもつながります。
とくに、地域密着型の企業であれば、Google検索やGoogleマップ上での露出を増やすために「Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)」の活用が有効です。
写真付きの施工事例、顧客のレビュー、営業時間などを正確に掲載するだけでも、信頼感を高められます。
また、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを活用すれば、ビジュアルで直感的に施工内容を伝えることができます。
とくに住宅や店舗の施工を行う場合、デザイン性や清潔感などが写真でアピールできるため、競合との差別化に直結します。
自社の強みを言語化して訴求する方法
「うちの会社は対応が丁寧です」では他社と差がつきません。
差別化ポイントは、具体的かつ顧客視点で言語化しなければ伝わらないため、強みの「見える化」が重要です。
例えば「対応が丁寧」ではなく、「お客様1人ひとりに専任担当者が付き、LINEで迅速に連絡できる」と表現することで、具体性と安心感が伝わります。
また、専門性を打ち出す場合も「工場建設が得意」ではなく、「設備機器の搬入経路まで設計段階から考慮できる技術者が常駐」と記載すれば、訴求力が一気に高まります。
このように、強みは「どんな価値を、誰に、どのように提供しているのか?」を軸に5W1Hで分解して整理しましょう。
ホームページや営業資料、名刺裏など、あらゆる場面で一貫した言葉として打ち出すことが、ブランディング強化にもつながります。
リピート・紹介につなげる仕組みづくり
マーケティングの中でも最も費用対効果が高いのが、「既存顧客からのリピート・紹介」です。建設業はリピート性が低いと言われがちですが、OB顧客との関係性を大切にすることで、継続的な工事や紹介案件を得ることが可能です。
そのためには、「接点づくり」と「継続フォロー」の仕組みが必要です。例えば、以下のような施策があります。
| 施策 | 目的 | 効果 |
|---|---|---|
| 定期点検・季節ごとのDM | 接点を維持する | 再依頼・リフォームの依頼が増える |
| お客様紹介キャンペーン | 紹介を促す | 新規顧客の獲得 |
| 施工事例に名前を掲載(許可制) | 満足度の可視化 | 信頼度アップ・紹介率向上 |
さらに、顧客情報を一元管理できるCRM(顧客管理システム)を導入することで、過去の工事履歴や問い合わせ内容を元に、きめ細かいフォローが可能になります。
紹介やリピートは「信頼の証」です。
顧客満足度を高め、再接点を設計することで、長期的な売上基盤を築くことができます。
差別化の取り組みでよくある失敗と対策
差別化は競争優位を築くうえで重要な手段ですが、取り組み方を誤ると逆効果になることもあります。
ここでは、建設業でありがちな失敗事例とその対策を詳しく解説します。
ただの「ウリ文句」になってしまう
多くの建設会社が「丁寧な施工」「地域密着」「高品質」などを差別化ポイントとして掲げていますが、これらはもはや業界全体で当たり前の訴求文句となっており、差別化とは言えません。
つまり、顧客から見れば「どの会社も同じことを言っている」と映ってしまうのです。
このような表面的なキャッチコピーは、具体性に欠けるため印象に残らず、他社との違いが伝わりません。
本来の差別化とは、「自社ならではの具体的な価値を、お客様目線で明確に伝えること」です。
対策としては、曖昧な表現を避けると同時に、数字や事例を交えた訴求に変えることが効果的です。
たとえば「安心の施工体制」ではなく「国家資格保有者が常時監督、施工後も1年ごとに無料点検」など、事実に基づいた表現へ落とし込みましょう。
顧客ニーズとズレた訴求
自社が「これが強みだ」と信じて発信していても、それが顧客のニーズと一致していなければ、選ばれる理由にはなりません。
たとえば、高度な技術力を強調していても、顧客が求めているのは「相談しやすさ」や「価格の明確さ」だったというケースは少なくありません。
このようなズレは、顧客視点を欠いた内向きの発想から生まれます。
社内で議論して導き出した強みでも、実際の顧客ニーズと擦り合わせていない場合は要注意です。
対策としては、顧客アンケートやヒアリングを通じて、「選ばれた理由」や「不安だった点」を定期的に把握することが重要です。
また、受注時やアフター対応時に、お客様の声を記録・共有する文化を社内に根付かせることで、ニーズに即した差別化訴求ができるようになります。
継続できない・社内に浸透しない
差別化戦略を考えても、それが現場に浸透しておらず、「結局いつも通りの営業や施工になっている」というケースも多く見られます。
トップダウンで打ち出した戦略が、現場の担当者に伝わらず形骸化してしまうことが原因です。
さらに、最初は積極的に取り組んでも、数ヶ月後には更新が止まる、施策が継続されないといった「継続性の欠如」も、成果につながらない典型例です。
このような状況を防ぐには、「差別化」を全社員が理解・実践できるよう、言語化されたルールや仕組みに落とし込むことが欠かせません。
具体的には、以下のような取り組みが有効です。
| 対策 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| マニュアル化 | 対応方針や強みの言い回しを文書化 | 誰でも一貫した対応が可能になる |
| 定期ミーティング | 月1回の振り返りで進捗共有 | 取り組みの継続力を高める |
| 社内研修 | 差別化の目的と背景を全員に共有 | 納得感を持って行動できるようになる |
差別化の実現には、顧客だけでなく社内にも「伝える力」が求められます。
仕組みとして根付かせることで、初めて成果が継続的に表れるのです。
まとめ
今回の記事では、建設業における差別化について解説しました。
差別化をはかるには「顧客目線」と「継続性」が欠かせません。
自社の強みを一方的に語るのではなく、相手のニーズに応える形で伝え、社内全体で実行・維持できる仕組みづくりを進めましょう。