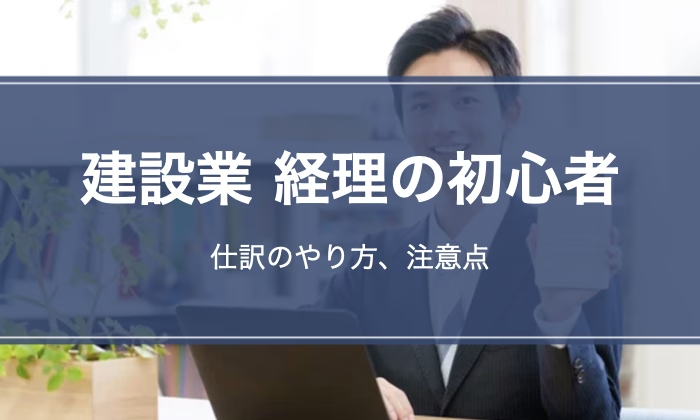建設業特有の経理処理や仕訳の仕方がわからず、不安や混乱を感じている初心者の方も多いはずです。
そこで、今回は建設業における経理の基本的な仕事内容や仕訳のやり方、初心者がまず学ぶべきポイントについて解説します。
この記事を読めば、建設業経理の全体像や他業種との違い、実務に必要な知識がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業の経理とは?仕事内容の全体像
建設業の経理は、一般企業の経理とは異なる独自の特徴があります。
特に工事の進行状況に応じた収益認識や工事原価管理など、専門的な知識と実務スキルが求められます。
以下で、その仕事内容や他業種との違い、関連する会計基準について詳しく解説します。
建設業 経理 仕事内容とは?
建設業の経理は、単に日々の仕訳や帳簿付けを行うだけではありません。
工事単位での損益管理、進行基準に基づく売上計上、原価の配分など、業種特有の処理が多数存在します。
具体的な仕事内容には、以下のようなものがあります。
| 業務内容 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 工事原価の計上 | 各工事にかかった費用を集計 | 正確な配分が必要 |
| 売上の計上 | 進行基準や完成基準に従って計上 | 基準に応じて時期が変わる |
| 原価管理資料の作成 | 工事ごとの予算と実績を比較 | 工程に合わせた更新が必要 |
| 請求書処理・支払管理 | 協力会社からの請求内容の確認と処理 | 工事ごとの分類が求められる |
建設業経理では、工事1件ごとに損益が発生するため、「完成工事原価」「未成工事支出金」など、特有の勘定科目を使いこなす必要があります。
日常の経理処理だけでなく、会計・税務・管理会計の観点からも業務に取り組む必要があるのが特徴です。
他業種との違いと特殊性
建設業の経理が他業種と大きく異なる点は、「工事」という単位で業務が進行する点にあります。
通常の小売業や製造業では、月単位や商品単位で会計処理を行いますが、建設業では工事単位で収支を把握する必要があるんです。
また、建設業は契約から完成までの期間が長期に及ぶことが多く、途中での収益認識や原価配分が重要になります。
加えて、受注生産の特性が強く、現場ごとに使用する材料や人員、機械のコストを個別に管理する必要があり、経理部門と現場担当者との連携も不可欠です。
さらに、下請会社との契約・支払処理、注文書や請書などの文書管理も経理の業務範囲に含まれます。
これらの管理が甘いと工事利益の見込みがずれることもあるため、経理担当者の業務は単なる数字管理にとどまらず、会社全体の経営判断にも影響を与える要素となります。
請負契約の特徴(長期工事・進行基準など)
建設業においては、1日や数週間で完了する仕事は稀で、数ヶ月から数年単位の工事が一般的です。
このような長期契約が多い点が、建設業の大きな特徴です。
そして、経理処理において最も重要なのが、こうした「請負契約」に基づく進行状況の把握です。
請負契約では、工事の着手日、完成予定日、契約金額、支払条件などが明確に取り決められます。
これに基づき、収益の計上方法を「工事進行基準」または「工事完成基準」で判断します。
進行基準では工事の進捗に応じて売上を計上し、完成基準では工事が完了した時点で一括して売上を認識します。
前者は工事の収支をリアルタイムに近い形で把握できるメリットがありますが、原価や進捗率の正確な把握が求められるため、業務の難易度も上がります。
建設業経理の実務では、どの契約にどの基準を適用すべきかの判断が欠かせません。
特に赤字工事の場合や10億円以上の大型工事では、より厳密な基準に従う必要があります。
会計基準「工事契約に関する会計基準」の概要
建設業の経理では、「工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号)」に従って処理を行う必要があります。
これは、請負契約に基づく工事収益・工事原価の認識方法を定めた基準です。
この基準では、工事進行基準と工事完成基準の使い分けが明確に示されており、信頼性をもって工事の進捗度を見積もれる場合には進行基準を、それができない場合には完成基準を適用することが推奨されています。
また、会計処理だけでなく、原価計算や収益認識のタイミングにも大きく関係しているんです。
会計基準に則って正確な処理を行うことで、財務諸表の信頼性を保つとともに、税務調査のリスクも低減できます。
建設業における経理担当者は、この会計基準を正しく理解し、実務に反映できるようになることが求められます。
日々の仕訳や報告書作成だけでなく、会計制度に関する知識を備えることが、信頼される経理担当者への第一歩です。
工事原価と勘定科目の基本
建設業の経理においては、工事ごとの原価管理が業務の中心となります。
ここでは、工事原価を構成する4要素と建設業特有の勘定科目について詳しく解説します。
工事原価の4要素
建設業の工事原価は、主に「材料費」「労務費」「経費」「外注費」の4つに分類されます。これらはすべて、完成工事原価を構成する重要なコスト要素であり、それぞれの正確な把握と分類が利益管理の鍵を握ります。
| 原価要素 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 材料費 | 工事で使用する資材や部品の購入費用 | 鉄筋、コンクリート、木材など |
| 労務費 | 現場作業員の人件費 | 日当、給与、法定福利費 |
| 経費 | 現場運営にかかる間接的な費用 | 現場事務所の光熱費、交通費、保険料 |
| 外注費 | 専門業者への委託費用 | 設備工事の外注、足場工事の委託など |
「建設業 経理 やり方」として大切なのは、これら4要素を工事ごとに分けて管理し、予算との差異を随時確認することです。
現場ごとの収支状況をリアルタイムに把握できるようにすることで、赤字工事の早期発見やコストコントロールにつながります。
たとえば、材料が予定よりも早く消費されている場合、それが設計変更によるものか、施工ミスによるものかを見極める必要があります。
原価を「見える化」することが、建設業経理の最大の役割ともいえるでしょう。
建設業用の勘定科目と仕訳例
建設業では、他業種には見られない独特の勘定科目が多数使われます。
その中でも代表的なのが、「完成工事高」「完成工事原価」「未成工事支出金」などです。
これらの勘定科目は、工事の進捗や収益の認識時期に応じて使い分けられます。
| 勘定科目 | 役割 | 使用タイミング |
|---|---|---|
| 完成工事高 | 完成した工事の売上を記録 | 工事完成時に売上として計上 |
| 完成工事原価 | 完成した工事の原価を集計 | 完成時に原価をまとめて記録 |
| 未成工事支出金 | 進行中工事の原価(費用)を記録 | 工事が完了するまでの費用記録 |
たとえば、工事が進行中の場合、材料の仕入や人件費などの原価はすべて「未成工事支出金」に記録され、完成後に「完成工事原価」に振り替えます。
そして、同時に「完成工事高」として売上を計上することで、損益が発生します。
以下は「建設業 経理 仕訳」の基本的な例です。
【例1】鉄筋100万円分を仕入れた(進行中の工事に使用)
借方:未成工事支出金 1,000,000円/貸方:買掛金 1,000,000円
【例2】工事が完成し、原価200万円、売上300万円を計上
借方:完成工事原価 2,000,000円/貸方:未成工事支出金 2,000,000円
借方:売掛金 3,000,000円/貸方:完成工事高 3,000,000円
このように、建設業では原価と売上の計上タイミングがずれることが多く、勘定科目の使い分けが非常に重要です。
初心者の方は、まずは仕訳の流れを理解し、工事単位で帳簿を組み立てていくイメージを持つことから始めるとよいでしょう。
売上計上基準の選び方
建設業における売上計上には、「工事進行基準」と「工事完成基準」の2つがあり、工事の内容や規模によって適切な基準を選ぶ必要があります。
ここでは、売上計上基準の選び方を解説します。
工事進行基準と工事完成基準の違い
建設業特有の会計処理の中でも、売上計上の基準を選ぶことは非常に重要です。
一般的な商取引と違い、建設工事は長期にわたることが多く、収益の認識方法によって損益の時期が大きく変わります。
代表的な2つの基準である「工事進行基準」と「工事完成基準」は、以下のように異なります。
| 基準 | 売上計上のタイミング | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 工事進行基準 | 工事の進捗に応じて売上を計上 | 業績を平準化できる/進捗率の把握が難しい |
| 工事完成基準 | 工事完了時に一括で売上を計上 | 計算が簡単/利益の計上時期が偏る |
たとえば、1年を超える長期工事では、進行基準を適用することで毎年一定の売上と利益を計上できます。
一方で、短期かつ小規模な工事であれば、完成基準のほうが実務的にはシンプルです。
これらの違いを理解し、工事の特性や契約内容に応じて柔軟に選択することが重要です。
建設業 経理 勉強として理解すべき選択基準と適用条件
「建設業 経理 勉強」の一環として、売上計上基準の選択ルールは確実に理解しておくべきです。
適用条件は、国税庁が定めたガイドラインや企業会計原則に基づいています。
特に注目すべきポイントは、受注工事の規模や契約期間、会計処理の信頼性に関する要件です。
進行基準を適用するには、合理的に進捗度を測定できる体制があることが前提となります。
たとえば、工事原価による進捗度の把握や、エンジニアリング部門と経理部門が連携して月次の進捗報告を行っていることなどが条件に該当します。
一方で、進捗の測定が困難な場合や、契約が短期で工事の開始と完成が同一会計期間内で完結するような場合には、完成基準の適用が認められます。
これらの基準は、建設業に特化した会計処理であり、業種特有の知識として経理初心者がしっかり学ぶべき内容です。
進行基準は制度上の選択肢であるだけでなく、銀行や取引先に対する業績説明の説得力にも直結するため、戦略的な観点からも重要です。
特に売上が一定しない企業では、進行基準の導入により業績の見通しが立ちやすくなるメリットがあります。
赤字工事や受注額10億円超のケースでの扱い
一定の条件下では、進行基準の適用が義務付けられるケースがあります。
代表例が、受注額が10億円を超え、かつ工期が1年を超える長期大規模工事です。このようなケースでは、工事進行基準によって売上を計上しなければなりません。
また、赤字工事の場合でも進行基準を適用する必要がありますが、注意が必要です。進行基準では工事の総原価と見積総収益を比較し、損失が確定する場合には、その損失を全額引き当てる「工事損失引当金」の計上が求められます。
たとえば、工事の進捗が50%の時点で、総工事費が契約金額を超過すると見込まれる場合、その超過額を当期に全額損失処理する必要があります。
この処理を怠ると、業績を過大に評価してしまい、決算の信頼性を損ねることになります。
さらに、公共工事などでは契約金額が変更されることも多く、定期的な原価の見直しや進捗の再評価が不可欠です。
建設業の経理担当者は、進行基準を選択した場合、こうしたリスクと責任をしっかり管理できる体制を整える必要があります。
このように、売上計上基準の選択は一度決めたら終わりではなく、継続的な監査・運用が求められる会計判断です。
経理初心者にとっては難解な分野ですが、建設業の収益管理の要となる重要な知識といえるでしょう。
経理初心者が抑えておくべき注意と対処法
建設業の経理初心者がつまずきやすいポイントを事前に把握し、適切な対処を行うことで、業務の正確性と効率を高めることができます。
以下では、注意すべき点と具体的な対処法を解説します。
工事原価管理のこまめな実施法
建設業の経理で最も重要な業務のひとつが「工事原価の管理」です。
工事ごとに発生する材料費、外注費、人件費などを日々適切に集計・記録することで、利益の見える化が可能になります。
初心者にありがちなミスは、原価データをまとめて記帳することです。
これでは月末や決算時に工事ごとの収支が不明確になり、正しい損益管理ができません。
対処法としては、原価をリアルタイムで記録・分類できる体制を構築することが重要です。
たとえば、現場担当者に日報を提出してもらい、経理部門がその情報を元に仕訳を行うなどの工夫が有効です。
エクセルやクラウド型原価管理ソフトを使うことで、コスト集計の自動化も可能になります。
また、月次で工事別の予算と実績を照らし合わせる「工事別原価管理表」の作成も効果的です。
これにより、想定以上にコストがかかっている工事を早期に発見し、適切な対策を講じることができます。
工事に関連する経費とそうでない経費の線引き
経理初心者が混乱しやすいのが、「工事原価」と「販管費(販売管理費)」の違いです。
建設業では、工事ごとに発生する費用を工事原価に、会社全体で発生する共通費を販管費として区分します。
この区別を正しく行わないと、工事ごとの利益計算が正確にできず、経営判断に悪影響を及ぼす恐れがあります。
たとえば、現場に直接関係する作業員の人件費や建材費は工事原価に該当しますが、本社の事務員の給料や営業活動の交通費などは販管費に分類されます。
判別が難しい費用として、工事監督の人件費やレンタル事務機器費用などがありますが、これらは原則として各工事に明確な関連があれば工事原価、それ以外は販管費とする考え方が基本です。
線引きが難しい場合は、社内でルールを定めるとよいでしょう。
たとえば、工事現場に常駐する社員の人件費は全額原価、定期訪問する社員は按分して処理するなどのガイドラインを設けると、判断が統一され、経理処理のブレが減少します。
会計・税務の相談先:建設業経験豊富な税理士の探し方
建設業の会計処理や税務申告には、業界特有の知識が求められるため、一般的な税理士では対応しきれないケースがあります。
初心者が安心して相談できるのは、建設業に特化した経験を持つ税理士です。
しかし、実際にどのように探せばよいかがわからないという声も多く聞かれます。
探し方の第一歩は、「建設業の顧問実績があるか」を確認することです。
税理士紹介サイトや各地の税理士会の登録情報から、建設業支援を明言している事務所を検索するのが有効です。
また、ホームページなどで「工事原価計算」「進行基準対応」「建設業許可支援」などのキーワードを扱っている税理士であれば、業界理解があると判断できます。
面談時には、「工事別原価管理の支援実績」「完成基準・進行基準の処理経験」など具体的な対応経験を質問することも大切です。
さらに、建設業専門の会計ソフト(建設大臣、PCA建設業会計など)への対応可否もチェックポイントになります。
自社の経理レベルや規模に合った税理士を選ぶことで、単なる帳簿の確認だけでなく、資金繰りや税務リスクへの対策まで幅広い支援を受けることが可能です。
建設業経理の成否は、適切な専門家との連携にかかっているといっても過言ではありません。
実務効率化のためのクラウド会計ツール
建設業の経理業務を効率化するには、クラウド型の会計ソフトの導入が効果的です。
ここでは、建設業に適したクラウド会計ツールのメリットや、選定時に重視すべき機能について解説します。
建設業向けクラウド会計ソフトのメリット
建設業の経理業務は、工事ごとの収支管理、仕訳の複雑さ、証憑の煩雑さなど、他業種に比べて工数がかかるのが特徴です。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、クラウド会計ソフトの活用です。
まず大きな利点は「銀行口座やクレジットカードと連携した取引データの自動取得」です。
人力で入力する手間を大幅に削減でき、入力ミスのリスクも軽減されます。
また、自動仕訳機能により、よく使う仕訳パターンを登録すれば、以降の仕訳処理を自動化できる点も魅力です。
例えば「建材業者Aからの請求=材料費」と設定すれば、同様の取引は自動処理されます。
さらに、資金繰りの見える化機能も重要です。クラウド型会計ソフトはリアルタイムでキャッシュフローを可視化でき、工事ごとの利益や支出をタイムリーに把握可能です。
工期の長い建設業では、資金の流れを早期に把握できることが、経営の安定化に直結します。
勘定科目のカスタマイズ自由度や他システム連携機能の重要性
建設業の経理では、他業種に比べて複雑な会計処理が求められるため、勘定科目の柔軟な設定ができる会計ソフトを選ぶことが重要です。
たとえば、「完成工事高」「未成工事支出金」「完成工事原価」などの業界特有の科目を設定できなければ、実務に即した仕訳が行えません。
また、工事ごとの原価管理を行う場合、原価集計や現場別収支を可視化するために、外部の原価管理ソフトとの連携が必要になるケースがあります。
そのため、API連携やCSV出力・インポート機能が充実しているクラウドソフトを選ぶことが望ましいです。
他にも、勤怠管理システムや請求書発行ソフト、税務申告ソフトといった周辺ツールとの連携も、業務効率化には欠かせません。
たとえば、現場の労務費データを勤怠管理システムから自動取得し、そのまま原価集計に反映できれば、手作業による転記や入力ミスを防げます。
以下に、建設業向けクラウド会計ソフトを選ぶ際に重視すべき機能を整理した表を示します。
| 重視すべき機能 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 勘定科目の自由設定 | 業界特有の科目が登録可能 | 建設業特化の処理に対応できる |
| 原価管理システムとの連携 | 外部ソフトと自動連携 | 現場別の原価集計が効率化 |
| 自動仕訳機能 | 頻繁な取引のルール化 | 入力ミスの削減・業務時短 |
| 資金繰り管理 | キャッシュフローの可視化 | 経営判断のスピードアップ |
建設業の経理を効率化するためには、単なる会計処理にとどまらず、全体の業務フローを視野に入れたツール選びが重要です。
導入前に自社の業務内容や課題を明確にし、最適なクラウド会計ツールを選定しましょう。
まとめ
今回の記事では、建設業の経理について解説しました。
まずは工事ごとの原価管理や仕訳の流れを押さえ、クラウド会計ツールの活用など実務効率化にも取り組んでみましょう。