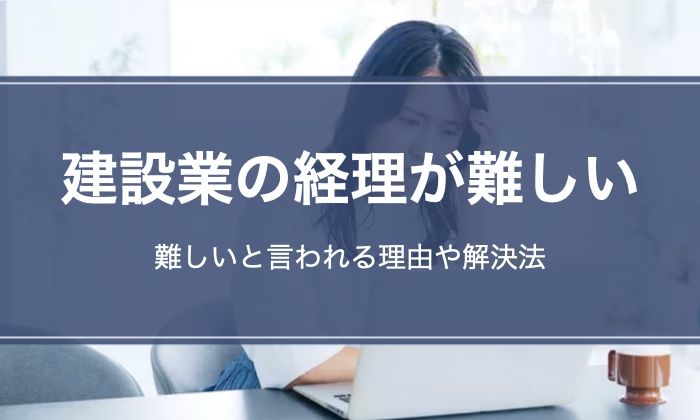「建設業の経理は他の業種と勝手が違って難しい….」そんな悩みを抱えている方に向けて、今回は建設業の経理が難しいと言われる5つの理由と、初心者でも理解しやすい克服方法について解説します。
この記事を読めば、建設業経理の特徴や必要な知識、そして未経験者がどのように学べばいいかがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業の経理はなぜ「難しい」と言われるのか?
建設業の経理が「難しい」と言われるのは、単に帳簿をつけたり決算を行ったりするだけではなく、業界特有の会計処理や原価管理、書類対応など、多くの業務に精通する必要があるからです。
特に他業種で経理経験がある人ほど、そのギャップに戸惑うことが多くなります。
他業種の経理と比較して難易度が高い理由
一般的な企業経理と比較して、建設業の経理は難易度が高いとされています。
その最大の理由は、収益や費用の認識方法が特殊であることです。
通常の商業簿記では、商品を仕入れて売ることで売上や原価が発生しますが、建設業では工事の進捗に応じて売上や原価を認識する必要があり、その処理が複雑です。
また、工事が長期間にわたるため、収益をどのタイミングで計上するかも一筋縄ではいきません。完成基準なのか、進行基準なのかといった判断も必要になります。
加えて、工事ごとに原価管理を徹底しなければならないため、工事台帳の作成や進捗の把握など、実務に即した運用力が求められます。
以下の表は、一般業種の経理と建設業経理の主な違いを比較したものです。
| 項目 | 一般業種の経理 | 建設業の経理 |
|---|---|---|
| 売上認識 | 販売時点 | 完成・進捗に応じて計上 |
| 原価管理 | 商品仕入が中心 | 工事ごとに詳細管理が必要 |
| 会計基準 | 商業簿記 | 工業簿記+建設業特有の処理 |
このように、建設業の経理は複数の帳票や判断基準を扱う必要があり、事務処理能力だけでなく業界理解も欠かせない業務となっています。
経理経験者でも戸惑う建設業特有のルール
他業種で経理経験がある人でも、建設業の経理に転職した途端に混乱することがあります。
その主な原因は、建設業に特有の勘定科目や帳簿の存在、さらに官公庁提出書類との連動です。
たとえば、「未成工事受入金」や「完成工事高」といった科目は商業簿記には存在せず、名称だけでは内容を把握しづらいため、実務経験がないと理解に時間がかかります。
さらに、建設業では工事台帳の管理が非常に重要です。各現場ごとに発生した材料費・外注費・労務費を正確に記録し、工事ごとの収益性を確認しなければなりません。
この「現場単位の管理」という概念も一般企業の経理にはあまりないため、経験者でも戸惑う要因となります。
加えて、建設業では行政対応も重要な業務の一つです。建設業許可や経営事項審査(経審)などの書類作成にあたっては、経理情報がベースになるため、経理担当が直接作業するケースも多いです。
これらの手続きは頻繁かつ煩雑で、対応には独特の知識と書類の整合性管理が求められます。
このように単に数字を扱うだけでなく、工事進捗の理解・現場管理・法的手続きといった複数の知識を統合的に活用する必要がある点が、建設業経理を難しくしている要因なのです。
建設業の経理が難しい5つの理由
建設業の経理が難しいとされるのは会計処理や管理業務において、他業種には見られない独特の要素が数多く存在するからです。
ここでは、建設業経理においてつまずきやすい5つの代表的な理由を順に解説します。
[box04 title=”建設業の経理が難しい理由”]
- 建設業特有の勘定科目が多い
- 原価と販管費の正確な区分が必要
- 工事ごとの原価管理が求められる
- 官公庁への提出書類が多い
- 給与計算・労務処理が複雑
[/box04]
①建設業特有の勘定科目が多い
建設業の経理でまず戸惑うのが、一般企業では使われない特有の勘定科目です。
たとえば、「未成工事支出金」「完成工事未収入金」「工事未払金」など、聞き慣れない名称が多く、初心者には内容のイメージが湧きにくいものもあります。
これらは建設業における工事の進捗状況や代金回収の状態を適切に会計処理するために用意された科目であり、売買を前提とする商業簿記とは全く異なる考え方が必要です。
特に「未成工事支出金」や「完成工事高」といった科目は、商業簿記における「在庫」や「売上」に似ているものの、実態との結びつきが抽象的で理解しづらいのが特徴です。
正確な会計処理を行うには、これらの科目の意味と使いどころをしっかり理解し、進行状況や契約形態に応じて適切に判断するスキルが求められます。
②原価と販管費の正確な区分が必要
建設業では、すべての費用を単純に経費として処理するわけにはいきません。
なぜなら製造原価報告書の作成が義務づけられており、工事原価として計上すべき費用(原価)と、営業活動などにかかる費用(販管費)を明確に区分しなければならないからです。
たとえば、現場で作業をする大工や職人に支払う給与は「賃金」として原価になりますが、事務所勤務の社員に対して支払う給与は「給与」として販管費になります。
つまり、同じ「人件費」であっても、業務の内容によって勘定科目が異なるのです。
この区別は人件費に限らず、水道光熱費や通信費、消耗品費などにも及びます。
費用の内容だけでなく、誰が、どこで、どのような目的で使ったのかという背景まで把握しておくことが重要です。
正確な区分を怠ると、製造原価報告書の精度が落ち、利益率や経営判断に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、非常に重要なポイントとなります。
③工事ごとの原価管理が求められる
建設業の経理では、工事ごとに原価を管理する「個別原価計算」が基本となります。
1つの材料を複数の現場で使う場合でも、それぞれの現場にどのくらい使ったかを明確に記録し、工事台帳に反映させる必要があります。
これは一般企業の「全社単位の費用管理」とは異なり、より細かく、手間のかかる作業です。
たとえば、10万円分の資材を購入して3つの現場で使用した場合、その配分を明確にして原価として各工事に割り当てなければなりません。
これに加え、外注費や労務費なども含めて工事単位で利益計算を行う必要があります。
| 原価要素 | 配分方法 | 記録帳票 |
|---|---|---|
| 資材費 | 使用割合で配分 | 工事台帳 |
| 労務費 | 現場別勤務記録 | 工事台帳 |
| 外注費 | 発注書に基づく | 支払調書+工事台帳 |
このように、工事別に正確なコスト管理を行うためには、日々の記録や関係者との連携が不可欠です。
管理が不十分だと、工事ごとの利益率や問題点を把握できず、経営判断の精度が下がってしまいます。
④官公庁への提出書類が多い
建設業では、官公庁に提出する書類の量と種類が他業種に比べて圧倒的に多く、経理担当者がその大部分を担うことになります。
特に公共工事を請け負う会社では、「建設業許可申請」「経営事項審査(経審)」「決算報告書」「入札参加資格申請」など、毎年のように提出すべき書類が複数あります。
これらの書類では、売上高や純利益といった財務データのほか、現場別の完成工事高や原価内訳など、非常に詳細な情報が求められます。
経理がしっかりと帳簿をつけていなければ、提出書類に不備が出てしまい、許可更新や入札参加ができなくなるリスクもあります。
また、行政書士などの専門家に作成を依頼する場合でも、経理担当者が正確なデータを提供しなければなりません。
そのため、日頃から正確な会計処理を行うことが重要です。
さらに、提出様式が年度によって変わることもあるため、法令や運用ルールの最新情報に目を通しておく必要があります。
⑤給与計算・労務処理が複雑
建設業の経理には、給与計算や労務処理の面でも特殊な業務が多く含まれます。
例えば、建設業における雇用保険料率は、一般業種よりも高く設定されていることがあり、毎年見直されることもあります。
また、労働保険の年度更新時には、「一括有期事業報告書」という特殊な書類の作成が求められ、通常の業種では見られない処理が必要になります。
さらに、現場ごとの出勤記録や作業日数を基に賃金を計算するケースもあり、事務所勤務とは異なる労働時間管理が求められます。
たとえば、現場作業員の残業や休日出勤、出張旅費の取り扱いも個別に処理しなければならず、給与計算ソフトのカスタマイズや人事との連携が重要になります。
労災対応についても注意が必要です。建設業は労災発生率が高いため、万が一事故が起きた際の労災申請書類の作成や、行政への報告対応も経理部門が担うことがあります。
こうした業務は事前の知識がなければ非常に負担が大きく、ミスが許されない分、精神的なプレッシャーもかかりやすい業務です。
建設業経理に向いている人の特徴とは?
建設業の経理は特殊な知識と丁寧な対応が求められるため、向き・不向きが明確に分かれます。
ここでは、どのような人が建設業経理に向いているのか、その特徴を紹介します。
細かい作業や管理が得意な人
建設業の経理には、細かな数字の確認や書類作成など、地道な作業が数多く発生します。
特に、工事ごとの原価管理や帳簿への正確な仕訳入力など、集中力を要する業務が日常的に求められます。
そのため、小さなミスにも敏感に気づき、丁寧に作業を進められる人が向いています。
また、工事台帳や原価台帳、請求書や支払調書など、管理すべき帳票類も多いため、情報を整理する能力も重要です。
建設業の経理に携わると、これらをすべて把握し、整合性を保ちながら処理する必要があります。
几帳面でルールや数字に強く、かつ安定した業務フローの中でコツコツ働くことにやりがいを感じる人にとっては、建設業の経理は非常に向いている職種だと言えるでしょう。
長く安定して働きたい人にもおすすめ
建設業界は、公共事業やインフラ整備といった社会基盤に直結する業種であるため、景気の影響を受けにくいという特長があります。
そのため、経理部門も安定した需要があり、長く腰を据えて働きたい人にとって魅力的な職場環境と言えるでしょう。
また、建設業経理に必要なスキルは、日々の実務の中で習得できるだけでなく、建設業経理士などの資格取得によってキャリアアップの道も開けます。
継続的に知識を蓄積し、専門性を高めていくことで、自分の市場価値を高めながら安定的に働くことが可能です。
特に、ライフステージに合わせた働き方を考える人にとって、長期的な雇用が見込める建設業経理は非常に魅力的な選択肢です。
資格取得支援制度や研修制度を整えている企業も多く、未経験からでもチャレンジしやすい点もポイントです。
建設業経理の難しさを乗り越える方法
建設業経理は独自の制度や処理が多いため、初学者にとってはハードルが高く感じられます。
しかし、正しいステップを踏めば誰でも着実に成長できます。ここでは、その具体的な方法を解説します。
基礎から学べる資格「建設業経理士2級」の取得
建設業特有の経理業務を理解するには、まず専門知識を体系的に学ぶことが欠かせません。
そこで注目されるのが「建設業経理士2級」の資格です。この資格は、建設業における会計処理の基礎を学べる国家試験であり、業界未経験でも挑戦しやすい内容になっています。
試験範囲は、原価管理・工事契約に関する処理・税務会計など、建設業に特化した内容が中心。特に工事ごとの個別原価計算や進行基準といった、一般企業では扱わない知識を習得できる点が特長です。
資格取得によって、実務での理解が深まり、職場での評価にも直結します。
また、多くの建設会社が有資格者を優遇しているため、就職・転職活動でも大きなアドバンテージになります。
| 項目 | 建設業経理士2級 | 一般的な簿記2級 |
|---|---|---|
| 対象分野 | 建設業特化 | 全業種共通 |
| 出題内容 | 原価計算、工事台帳、税務処理など | 商業簿記、工業簿記など |
| 実務活用度 | 高い(建設業に特化) | 中(広く浅く) |
経理未経験でも採用されやすい人材になるには
未経験から建設業経理の仕事に就くには、「ポテンシャルの高さ」を示すことがカギです。
特に採用側が重視するのは、数字への苦手意識がないこと、責任感があること、そして長く働く意志があるかどうかです。
まずは「日商簿記3級」や「建設業経理士2級」といった資格を取得することで、基本的な知識があることを証明できます。
さらに、建設業界に対する理解や意欲をアピールすれば、実務経験がなくても前向きな評価につながります。
また、事務作業や業務フローの効率化に関心がある人は、Excelや会計ソフトへの対応力もアピールポイントになります。
最近では、弥生会計や建設業専用のソフトに触れた経験があると、より即戦力として評価されやすいでしょう。
職務経歴書では、これまでの仕事で「数字管理」「資料作成」「チームとの連携」などの経験があれば、それを具体的に記載することで未経験のハンデをカバーできます。
まとめ
今回の記事では、建設業の経理について解説しました。
建設業の経理は他業種と異なり専門性が高いため、独学では限界があります。
まずは建設業経理士2級などで基礎を固め、実務で迷わないよう早めに学習を始めましょう。