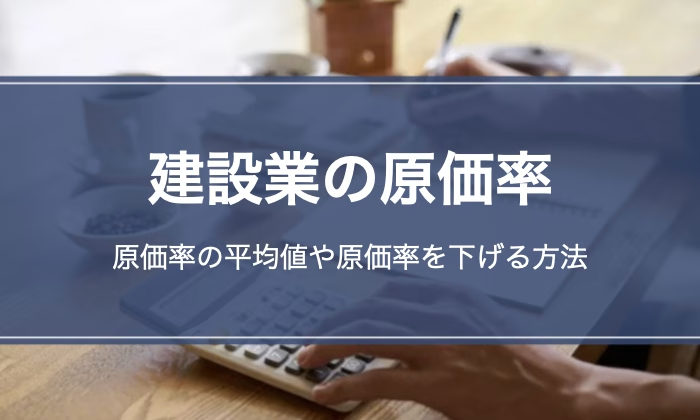「建設業の原価率が高すぎて利益が出ない」ということはありませんか?
そこで、今回は建設業における原価率の平均や、原価率が高くなる原因、改善のための具体的な対策方法について解説します。
この記事を読めば、原価率の正しい計算方法や業界平均との比較、自社の利益を守るための実践的な改善策がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業の原価率とは?
建設業における原価率とは、工事にかかる原価が売上に対してどれだけの割合を占めているかを示す指標です。
この原価率を正しく把握することで、利益構造を明確にし、適切な経営判断や原価管理が可能になります。
ここでは、原価率の定義と意義、さらに工事原価と工事価格の違いについて詳しく解説します。
原価率の定義とその意義
原価率とは、「売上高に対する原価の割合」を意味する経営指標で、計算式は以下のとおりです。
原価率(%)= 工事原価 ÷ 売上高 × 100
建設業では工事ごとに収支が発生するため、原価率の把握がとくに重要です。
一般的に、原価率が高すぎる場合は利益が確保できていない状態を意味し、過剰なコストがかかっている、もしくは受注価格が低すぎるといった問題が考えられます。
一方、原価率が適正であれば、利益確保に加えて経営の安定化にもつながります。
また、「建設業 原価率 平均」は企業規模や業種によって異なりますが、2020年度の統計では平均76.5%程度とされており、80%を超えると利益圧迫のリスクが高まります。
このような情報を参考に、自社の原価率が高いのか低いのかを客観的に判断する材料になります。
工事原価と工事価格の違い
建設業の原価計算において混同されがちなのが、「工事原価」と「工事価格」の違いです。
これを明確に区別することで、原価率の正しい把握と管理が可能になります。
工事価格とは、顧客に提示する契約金額であり、企業にとっての「売上高」に相当します。
一方、工事原価はその工事にかかった実際のコストで、「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4要素で構成されます。
工事原価はさらに、以下の2つに分類されます。
| 分類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 純工事費 | 直接工事にかかる費用 | 材料費、外注費、労務費など |
| 現場管理費 | 施工現場を管理するための費用 | 現場監督の人件費、安全対策費など |
このように、工事原価と工事価格を正確に区別し、それぞれの構成を理解することが、建設業における原価率の適正化と利益向上の第一歩となります。
適切な原価管理体制を整えるには、日々の工事ごとの原価集計と、全社的なコスト意識の醸成が欠かせません。
建設業における原価率の平均値(最新データを紹介)
建設業における原価率平均は、業界の利益水準を把握する上で重要な指標です。
ここでは、2020年度の最新データを基に、従業員規模別・個人企業を含めた原価率平均を紹介します。
企業の現状把握や改善方針の参考として役立ててください。
2020年度の建設業 原価率 平均とその傾向
国土交通省の「建設業の経営分析参考資料(令和3年度版)」によれば、2020年度における建設業全体の平均原価率は約76.5%となっています。
これは、売上の約4分の3が工事原価として消費されていることを意味し、利益確保の余地が25%程度しかない厳しい構造であることを示しているのです。
とくに中小企業や個人事業主では、材料費の高騰、人件費の上昇、施工ミスによる追加コストなど、原価率を押し上げる要因が複数存在します。
したがって、自社の原価率が平均と比べて高いのか低いのかを把握することで、原価管理の精度を高め、利益改善の方向性を見出す手がかりとなります。
以下に、従業員規模別および個人企業の建設業における原価率の平均値を整理した表を示します。
| 企業規模(従業員数) | 建設業 原価率 平均 | 傾向 |
|---|---|---|
| 5人以下 | 81.2% | 小規模で外注比率が高く、原価率が高め |
| 6〜20人 | 76.8% | 比較的平均に近く、業務効率により変動 |
| 21〜50人 | 73.6% | 内部体制が整い、原価管理の精度が向上 |
| 51人以上 | 71.1% | スケールメリットが働き、原価率が低下 |
| 個人企業 | 84.9% | コスト管理が難しく、極めて原価率が高い |
このデータから見えてくるのは、従業員数が増えるにつれて原価率が下がる傾向があるという点です。
つまり、組織力のある企業ほど、材料調達の効率化や労務管理、工程管理の精度が高く、結果的に原価率の低下につながっています。
一方で、個人企業や小規模企業では、工程ミスや仕入れ単価の不利などが重なり、平均を上回る原価率となっているケースが多く見られます。
こうした数値は、自社の改善目標を設定する上で非常に有用です。
今後、原価率を意識した経営を行うためには、平均値を単なる指標として終わらせず、実際の経費項目に落とし込んで改善策を講じることが求められます。
原価率が高くなる主な原因
建設業において原価率が高くなる背景には、いくつかの代表的な要因があります。
中でも「販売価格の低さ」「仕入れ価格の高さ」「施工ミスの多発」は、業績に直接的な影響を及ぼす重要な要素です。
ここではそれぞれの原因について、事例や具体的な状況を交えて解説します。
販売価格の低さ
建設業の価格競争は年々激化しており、とくに中小企業では受注獲得を優先するあまり、利益を圧迫する低価格で契約してしまうケースが目立ちます。
これが「販売価格の低さ」につながり、結果的に原価率の上昇を招く要因となります。
たとえば、ある地域工務店では、地場の競合に対抗するために坪単価を相場よりも1割安く設定して受注を増やしていました。
しかし、実際の工事にかかる原価は下がらず、原価率は85%を超えていました。
結果として、件数は増えても利益が残らない構造に陥り、資金繰りが悪化してしまったのです。
このような事例からも分かるように、適正な利益を確保できる販売価格の設定は、経営の安定化に不可欠です。
安請け合いが習慣化すると、社内のモチベーション低下や品質の低下にもつながるため、売上重視から利益重視へのシフトが求められます。
仕入れ価格の高さ
原価率を左右する大きな要因のひとつが「仕入れ価格の高さ」です。
資材費や外注費の増加は直接的に工事原価を押し上げ、結果的に原価率を高くしてしまいます。
たとえば、地方の住宅建設業者A社では、特定の建材卸業者との長年の取引に頼り切っており、市場価格よりも割高な価格で資材を購入していました。
業界の価格見直しが進む中でも交渉は一切行われず、同業他社と比較して最大10%以上も高い原材料費を負担していたのです。
その結果、原価率は常に80%台後半となり、経営を圧迫する要因となっていました。
こうした状況を改善するには、複数の仕入れ先と価格交渉を行うことが基本です。
また、共同仕入れの仕組みを活用することで、規模の経済を生かした価格の引き下げも可能になります。
単に仕入れるのではなく、「いかに仕入れるか」が問われる時代です。
施工ミスの多発
建設現場では、人的ミスや工程の乱れによって「手戻り工事」が発生することがあり、それが原価を押し上げる大きな原因となります。
これが「施工ミスの多発」による原価率上昇の典型です。
例えば、あるビル建設の現場では、設計図の読み違いによって配管の位置が大幅にずれて施工されてしまいました。
すでに壁が立ち上がっていたため、いったん解体して再施工を行う必要が生じ、予定外の人件費と資材費が大幅に発生。最終的に工事原価は当初見積もりの1.3倍に膨れ上がり、原価率も90%近くに達しました。
このような施工ミスは、ヒューマンエラーだけでなく、業務の属人化や現場間の情報共有不足によっても発生します。
対策としては、施工前の確認体制の強化、標準化されたマニュアルの整備、現場管理ソフトの導入などが有効です。
品質管理と工程管理の徹底が、原価率を抑える大きな鍵となります。
建設業における原価計算方法
建設業における原価管理の基本は、工事原価を正確に把握し、原価率を適切に分析することにあります。
ここでは原価計算の基本ステップとして、工事原価の4要素とその分類、原価率の算出方法、そして実際の計算例を交えて解説します。
工事原価を構成する4要素の分類
「建設業 原価計算」を正しく行うためには、まず工事原価を構成する4つの主要要素を明確に理解する必要があります。
これらは「材料費」「労務費」「外注費」「経費」です。各要素の意味と内訳を以下にまとめます。
| 費目 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 材料費 | 建設に使用される物理的な資材の費用 | コンクリート、鉄骨、木材、配管、電線 など |
| 労務費 | 自社雇用の作業員・技術者にかかる人件費 | 現場作業員の給与、社会保険料、賞与 など |
| 外注費 | 下請業者や専門工事会社への発注費用 | 電気工事業者への外注、塗装・足場の請負 など |
| 経費 | 工事現場に関連する間接費 | 現場事務所の光熱費、運搬費、安全対策費 など |
これらをすべて合計した金額が「工事原価」となります。原価管理の第一歩は、費目ごとに正確に分類・集計することです。
工事原価率の計算式とその意味
工事原価率は、原価が売上に対してどの程度の割合を占めているかを示す指標です。
以下の式で簡単に求めることができます。
工事原価率(%) = 工事原価 ÷ 売上高 × 100
たとえば、ある工事案件での売上が1,000万円、工事原価が750万円であった場合、
750万円 ÷ 1,000万円 × 100 = 75%
このように、売上の75%が原価で消費され、残りの25%が粗利益となることがわかります。
工事原価率は高すぎると利益が圧迫され、低すぎると逆に見積もりの信頼性が疑われるため、業種・業態に応じた適正値を意識することが重要です。
建設業における原価率の計算例
ここでは、企業規模別に中小企業と大手企業のケースを想定し、実際の原価率を計算してみます。
| 企業規模 | 売上高 | 工事原価(4要素合計) |
|---|---|---|
| 中小企業(従業員10名) | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 大手企業(従業員100名) | 3億円 | 2億1,000万円 |
上記をもとに原価率を計算すると
中小企業:4,000万円 ÷ 5,000万円 × 100 = 80%
大手企業:2億1,000万円 ÷ 3億円 × 100 = 70%
中小企業は規模が小さい分、仕入れ単価や外注費のコントロールが難しく、原価率が高めになる傾向にあります。
一方、大手企業はスケールメリットを活かして原価の最適化が可能となり、原価率も相対的に低く抑えられる場合が多いのです。
このように、「建設業 原価計算」は売上だけでなく、工事原価の構成と原価率のバランスに着目することで、経営改善や利益最大化につながる分析が可能となります。
原価率を下げる具体的な対策
建設業における高い原価率は、利益圧迫の大きな要因です。
ここでは、販売管理・仕入管理・施工管理・IT活用の4つの観点から、原価率を下げるための具体的な施策を紹介します。
販売管理の見直し:値下げ限度・利益確保の工夫
受注競争が激しい建設業では、安易な値下げが利益率を大きく損ないます。
価格交渉においては、事前に「この価格を下回ると利益が出ない」というラインを明確に設定し、社内で共有することが重要です。
また、値下げではなく、付加価値の提案(例:工期短縮、品質保証、アフターサービスの拡充)によって競争力を高める工夫も効果的です。
たとえば、ある住宅リフォーム会社では、「●月末までに契約すれば保証期間を延長」というキャンペーンを導入し、値引きせずに成約率を向上させた結果、利益率の維持に成功しました。
このように、価格だけでなく提案力を強化することで、原価率を悪化させずに売上を確保することができます。
仕入管理の改善:複数社比較・まとめ買いによる諸経費削減
材料費の削減は、原価率改善の効果が直結しやすいポイントです。
まず行うべきは、仕入れ先を1社に固定せず、複数社の見積もりを常に比較する体制を整えることです。
また、発注の頻度が高い材料については、まとめ買いや一括発注によるボリュームディスカウントを交渉するのも有効です。
たとえば、ある中小建設会社では、以前は地元業者に都度発注していたものを、ネット卸と比較し月単位でまとめて発注するように変更。
その結果、年間で約8%の材料費削減を実現しました。
このような工夫は、仕入れ担当者のちょっとした意識改革から始めることができます。
歩留まりの最適化:材料ロス・施工ミスの低減
「歩留まり」とは、仕入れた資材や労働力をどれだけ無駄なく使えているかを表す指標です。
材料の過剰発注・無駄な端材・施工ミスなどは、原価率を押し上げる要因となります。
現場でよくあるのが「余裕を見て多めに材料を仕入れたが結局使い切れず廃棄した」といったケースです。
このような無駄を防ぐには、過去の使用データを活用した精度の高い見積もり、現場管理者による材料管理の徹底、施工手順のマニュアル化などが効果的です。
また、施工ミスを減らすためには職人の教育だけでなく、チェックリストの導入や2人体制でのダブルチェックも有効です。
わずかな改善の積み重ねが、大きなコスト削減につながります。
原価管理システムの導入:クラウド型/オンプレミス型の特徴とおすすめ
原価率を正確に把握・コントロールするためには、原価管理のデジタル化が欠かせません。
現在多くの建設業者で導入が進んでいるのが、原価管理システムです。
主に「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があり、それぞれにメリットがあります。
| システム種別 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| クラウド型 | 初期費用が安く、どこからでも利用可能。アップデートが自動。 | ネット環境が必須。月額費用が発生。 |
| オンプレミス型 | カスタマイズ性が高く、自社サーバーで管理できる。 | 初期導入費用が高い。保守・運用が必要。 |
中小規模の建設業者には導入のしやすさとコスト面から「クラウド型」が向いています。
一方、情報セキュリティや高度なカスタマイズが求められる大手企業では「オンプレミス型」が選ばれる傾向があります。
いずれにせよ、リアルタイムでの原価把握と分析が可能になることで、無駄を即座に発見し、原価率の改善につなげることができます。
原価管理システムの選び方と活用
建設業における原価管理を効率化するには、自社に合ったシステム選定が重要です。
ここでは、クラウド型とオンプレミス型それぞれの特徴と代表的なツールを紹介し、導入による業務効率化や利益改善の効果について解説します。
クラウド型「アイピア」、オンプレミス型「MIYABI」の比較
建設業向けの原価管理システムは大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2タイプがあります。
それぞれ運用方法や機能に違いがあり、業種規模や運用方針に応じて選定する必要があります。
たとえば、クラウド型で代表的な「アイピア」は、インターネット環境さえあれば現場・本社・自宅などどこからでもアクセス可能で、現場の進捗状況や原価をリアルタイムで共有できます。
一方、オンプレミス型の「MIYABI」は、社内サーバーでの運用を前提としており、高度なカスタマイズ性とセキュリティ面での安心感が魅力です。
以下は両者の比較表です。
| システム名 | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|
| アイピア | クラウド型 | 月額制で導入コストが低く、外出先からでも利用可能。自動アップデート対応。 |
| MIYABI | オンプレミス型 | 自社環境に合わせてカスタマイズが可能。データ管理は社内で完結。 |
どちらを選ぶかは、導入・運用コスト、システムの柔軟性、セキュリティ体制など、自社のニーズとリソースをもとに判断する必要があります。
導入メリット:リアルタイム原価把握、進捗管理・データ解析による効率化
原価管理システムを導入する最大のメリットは、工事ごとの「原価の見える化」にあります。
従来は紙やExcelで分散していた情報を一元管理できるため、リアルタイムでの原価確認や進捗把握が可能になります。
また、データが自動で蓄積されていくため、過去案件との比較分析や、職人別・工事種別ごとのコスト傾向の把握も容易です。
これにより、次回以降の見積精度向上や、無駄な支出の洗い出しに活用できるなど、経営判断の質も向上します。
ある中堅建設会社では、「アイピア」導入により、手作業で2日かかっていた月次集計業務がわずか1時間に短縮され、同時に予算超過の早期発見率が大幅に向上しました。
こうしたデジタル化の成果は、現場の効率化だけでなく、全社的な利益体質の強化にもつながります。
原価率の適正化は属人的な判断だけでは困難です。
だからこそ、精度の高いデータに基づいた管理が可能な原価管理システムは、これからの建設業にとって不可欠なツールといえるでしょう。
まとめ
今回の記事では、建設業の原価率について解説しました。
原価率の改善には、日々の原価管理と定期的な見直しが欠かせません。
まずは自社の原価率を業界平均と比較し、課題を明確にしたうえで具体的な対策を講じていきましょう。