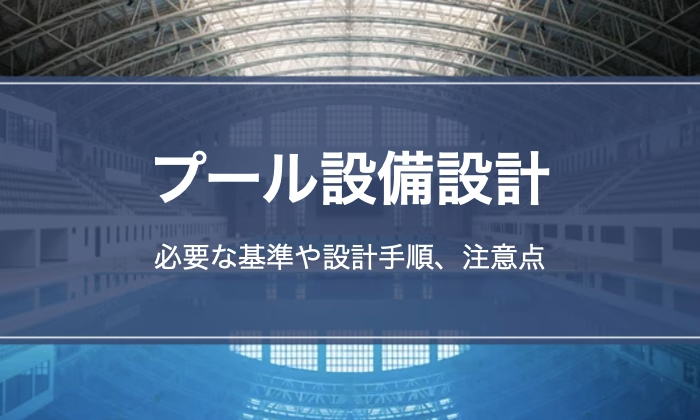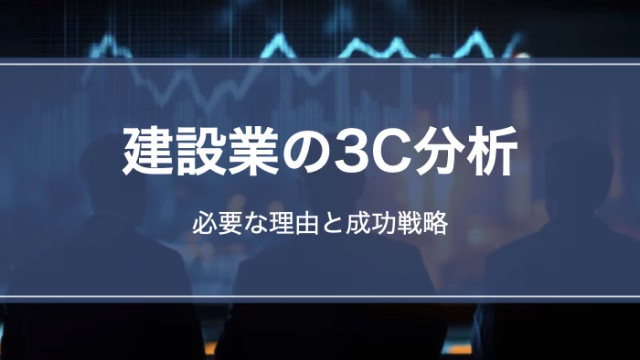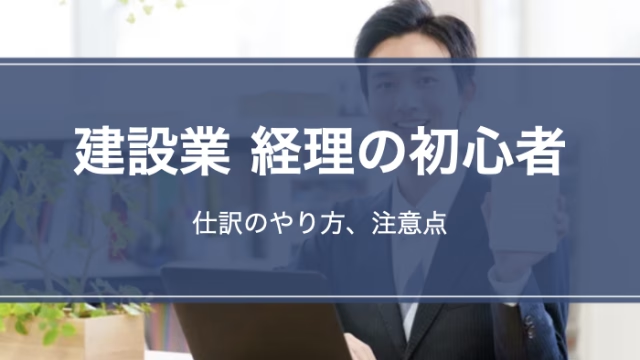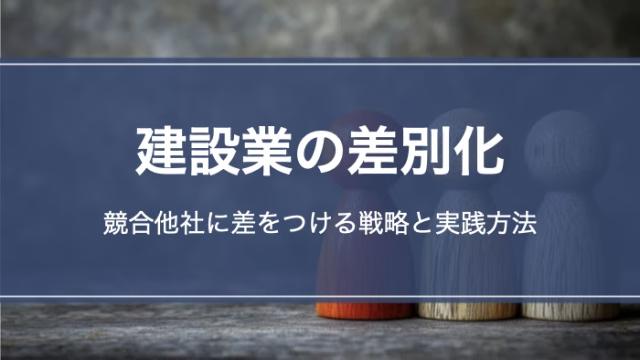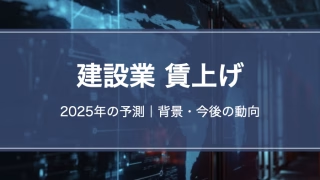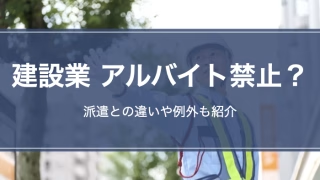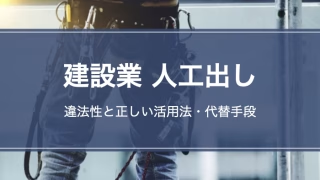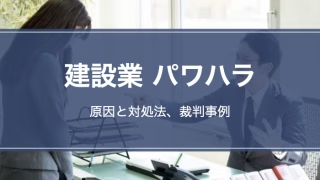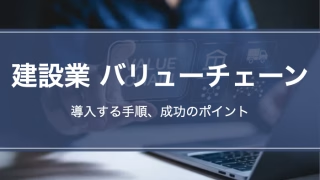公共施設や屋内プールの設計に関わる中で、給排水・空調・安全基準など、専門的な知識を求められて戸惑う設計者の方も多いはずです。
そこで、今回はプール設備設計の基本的な考え方と、押さえておくべきポイントについて解説します。
この記事を読めば、プールの設備設計に必要な基準や設計手順、注意点がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
プールの設備設計とは?
プールの設備設計には、施設の用途や規模、設置場所に応じた多面的な計画が必要です。
安全性・快適性・衛生管理の3点を軸に、設計方針を明確にすることが欠かせません。
以下では、設備の種類や設計の考え方を具体的に解説します。
プール施設に求められる設備の種類
プールは単に水を溜めるだけの施設ではなく、さまざまな設備が連携して機能しています。
代表的なものに、給排水設備、ろ過・消毒設備、空調・換気設備、電気・照明設備、安全管理設備があります。
たとえば、給排水設備は水の循環や温度調整に関わる要であり、利用者の快適性と衛生面を保つ重要な機能を担っています。
ろ過装置や消毒装置は、水質を常に清潔に保つために不可欠であり、特に公共施設では法令基準への準拠が求められます。
空調や換気設備は、特に屋内プールでの結露やカビの発生を防ぐために重要です。
加えて、照明設備では、安全に遊泳できる照度を確保するだけでなく、施設の雰囲気を演出する役割もあります。
設備は単体ではなく、全体のバランスを考慮して設計されるべきであり、それぞれの連携によって、安全で快適なプール空間が実現されます。
屋内/屋外で異なる設計方針
プールの設計では、屋内か屋外かによって求められる設備の内容や設計方針が大きく異なります。
屋外プールでは自然環境を前提とした設計が必要であり、日照・風向き・外気温などの影響を受けやすいため、特に水温管理や日差しへの対応が課題となります。
一方、屋内プールでは、建物内部に設けられるため、空調・換気・湿度管理といった要素が設計の中心となります。
また、屋内プールでは外部環境からの遮断により、水質の変化が比較的少なく安定した運用が可能ですが、その分、空気中の塩素臭や結露、カビの発生リスクが高まるため、空調設備の設計精度が求められます。
屋外プールでは逆に、紫外線や降雨による水質変化に注意が必要であり、耐久性の高い素材の選定や、雨水排水計画も設計の一部になります。
以下の表は、屋内プールと屋外プールにおける主な設計ポイントの違いをまとめたものです。
| 設備項目 | 屋内プール | 屋外プール |
|---|---|---|
| 空調・換気 | 湿度・結露・臭気対策が必要 | 基本的に不要だが風よけ設計は必要 |
| 水温管理 | 年間通じて必要 | 季節に応じた管理 |
| 水質維持 | 比較的安定しやすい | 紫外線・降雨の影響を受けやすい |
| 素材・構造 | 耐湿性重視 | 耐候性・紫外線対策が必要 |
安全性・衛生・快適性をどう確保するか
プール設備設計において最も重視すべきなのが「安全性」「衛生」「快適性」の3要素です。
まず、安全性の観点では、滑りにくい床材の採用、感電や漏電防止のための電気設備の防水仕様、万一の事故時に備えた監視カメラや非常用ブザーなどの設置が必要です。
また、給排水システムでは逆流防止や水の滞留を避ける設計が、衛生面の確保に直結します。
衛生面では、塩素濃度やpH値の自動管理システムを取り入れることで、常に一定の水質を保つことが可能になります。
利用者の肌や目に与える刺激を軽減するための設備選定も重要です。
たとえば、紫外線処理装置やオゾン処理など、塩素以外の消毒方法を併用するケースも増えています。
快適性の面では、プール周辺の空調、音響、照明設計に加え、動線のスムーズさやロッカー・更衣室との配置計画も影響します。
利用者が「使いやすい」「居心地が良い」と感じる設計こそが、長期的な運営の成功につながります。
これらの要素を設計段階でバランスよく組み込むことが、プール施設の価値を大きく左右します。
プールの給排水・循環設備の設計ポイント
プールの給排水・循環設備は、水質を衛生的に保ち、快適な利用環境を維持するために欠かせない要素です。
以下では、水質管理機能、循環方式と濾過装置の選定、給排水のゾーニングについて詳しく解説します。
必要な水質管理機能
プール水の水質は、利用者の健康や快適性に直結するため、適切な管理機能が求められます。
基本的には、遊泳に適したpH値(7.2〜7.8)と残留塩素濃度(0.4〜1.0mg/L)を常に維持できるよう、監視・制御機器を設置することが必要です。
また、利用者数が多い公共プールなどでは、リアルタイムで水質を測定し、薬注装置と連動させて自動制御するシステムが一般的になっています。
近年では、塩素以外にも紫外線殺菌装置やオゾン処理装置など、副生成物を抑える技術の導入が進んでおり、より高い水質と安全性が求められています。
これらの機器は、設計時に施設規模や予算、管理体制を考慮して選定する必要があります。
水質管理の機能を設計段階で確実に取り入れることは、法令遵守はもちろん、利用者の満足度や施設の運営効率にも大きく影響します。
循環方式と濾過装置の選定基準
プール水の衛生を保つためには、汚れを効率的に除去する循環システムと、それに連動する濾過装置の設計が重要です。
循環方式には、主にスキマー方式とオーバーフロー方式の2種類があります。
スキマー方式はコストを抑えたい小規模施設向けで、特定の吸水口から水を取り入れて再循環させる方法です。
一方、オーバーフロー方式は大型施設で多く採用されており、プール水を全面的に溢れさせて側溝から回収・循環させるため、水質の均一性に優れます。
濾過装置には、砂濾過、カートリッジ式、DE(ダイアトマシャスアース)濾過などがあります。
一般的には、処理能力、濾過精度、維持管理のしやすさ、運用コストをもとに選定します。
たとえば、砂濾過はコストが低く管理しやすい反面、微細な粒子の除去にはやや劣ります。
反対に、DE濾過は非常に高精度ですが、設備費用と保守負担が増える傾向があります。
以下に、主な循環方式と濾過装置の特徴をまとめます。
| 項目 | スキマー方式 | オーバーフロー方式 |
|---|---|---|
| 特徴 | 低コスト、小規模向け | 水質均一、大規模向け |
| 濾過装置例 | 砂濾過、カートリッジ | 砂濾過、DE濾過 |
| メンテナンス性 | 比較的容易 | 定期的な清掃が必要 |
給水・排水系統のゾーニング
プール設備設計において、給排水系統のゾーニングは機能性と安全性の両面で非常に重要です。
ゾーニングとは、施設内の各エリアに応じて給水・排水のルートや機器配置を最適化する設計手法であり、水の流れを効率的に管理する上で欠かせません。
たとえば、給水はろ過装置や加熱装置を経由してプール本体へ供給される必要がありますが、このとき複数の供給口をバランスよく配置することで、水温や塩素濃度のムラを防ぐことができます。
一方、排水は使用済みの水を衛生的かつ安全に処理するため、他の設備機器や利用者動線から十分に距離を取ったルートを確保する必要があります。
また、非常時の排水経路やメンテナンス用のバイパスルートも、あらかじめ設計に組み込んでおくことが求められます。
ゾーニングが適切に行われていない場合、設備の不具合や水質トラブルのリスクが高まり、結果的に施設の運用コストやクレーム対応が増えることになります。
以上を踏まえ、設計時には設備配置図だけでなく、配管系統図やゾーニング図面も併せて整備し、施工時や将来的な保守がスムーズに行えるように準備しておくことが重要です。
換気・空調設備の考え方と注意点
屋内プールでは、湿気・結露・臭気の発生を防ぎつつ、快適な温湿度を保つことが求められます。
ここでは、湿気対策、適正な換気量、局所と全体換気のバランスについて解説します。
湿気・結露・カビ対策の重要性
屋内プールにおける湿気と結露の対策は、設備劣化の防止と利用者の健康を守る上で非常に重要です。
プール水は常に蒸発し続けており、これが空気中に多量の水分を供給することで、高湿度の状態が常態化します。
この状態を放置すると、天井や壁、照明器具などに結露が生じ、建材の劣化やカビの発生を引き起こす要因となります。
とくに断熱性能が低い建物や、外気との温度差が大きい冬場には、結露が顕著に発生します。
そのため、設計段階から断熱材の選定や、適切な空気の流れを考慮した換気・空調システムの導入が求められます。
さらに、結露やカビは、目に見えない空調ダクトや壁内部にも発生する可能性があり、長期的には構造体に悪影響を及ぼします。
カビの発生は、利用者の健康にも影響し、特に喘息やアレルギーを持つ人にとっては深刻な問題です。
よって、湿気・結露・カビ対策は、設計品質だけでなく施設運営の信頼性にも直結する要素であり、軽視できません。
屋内プールの適正な換気量の目安
屋内プールにおいては、空気の入れ替えを通じて湿度や臭気、汚染物質を効率的に排出するために、適正な換気量の設計が不可欠です。
プールエリアの換気量は、「空気回数(ACH)」または「換気回数」によって算出されるのが一般的であり、1時間あたりの空気の総入れ替え回数を表します。
国際的な目安としては、屋内プールの換気量は少なくとも空気回数4〜8回/時が推奨されており、施設の規模や用途によって調整されます。
たとえば、公共の競泳用プールでは回転数が高くなる傾向があり、衛生管理を重視する場合は換気量をより高める必要があります。
また、空調と換気は一体で設計されるべきで、単に外気を取り入れるだけではなく、温度・湿度のバランスも重要になります。
外気が過剰に入りすぎると室温が下がり、利用者が寒さを感じることがあるため、熱交換器や再熱コイルなどを活用して、熱損失を抑えた換気計画を立てることが望まれます。
以下の表に、用途別の目安となる換気回数をまとめます。
| 用途 | 推奨換気回数(回/時) | 備考 |
|---|---|---|
| 一般利用プール | 4〜6回 | 標準的な利用を想定 |
| 競技用プール | 6〜8回 | 高い利用率に対応 |
| リハビリ・福祉施設 | 3〜5回 | 温度・湿度をより高精度に管理 |
局所換気と全体換気のバランス
屋内プールの換気設計では、「局所換気」と「全体換気」を適切に組み合わせることが、効率的な湿度管理と快適性の確保につながります。
全体換気は空間全体の空気を入れ替える機能を持ち、基準となる換気回数の達成に不可欠です。
一方、局所換気は湿気や臭気が特に溜まりやすい箇所に対し、ピンポイントで排気や送風を行う方式であり、設備の補完的役割を果たします。
たとえば、プールの水面近く、出入口付近、シャワー室や更衣室との接続部は、湿気が滞留しやすく、カビや結露の発生源となりやすいため、これらのエリアには局所的に排気口やファンを設けることで、リスクを低減できます。
また、局所換気はエネルギー消費の削減にもつながり、効率的な空調運転に寄与します。
ただし、局所換気だけに頼ると全体の空気循環が偏る可能性があるため、あくまで全体換気とのバランスが重要です。
ダクトの設置位置や風量設定は、CFD解析(流体解析)を用いて空気の流れをシミュレーションしながら設計すると、より最適化された配置が可能になります。
快適性・衛生性・省エネ性を両立するには、この局所と全体の役割を明確に分け、補い合う形で設計を進めることが鍵となります。
電気・照明設備と安全設計
プール施設では感電リスクや漏電事故を防ぎながら、適正な照度と演出効果を両立させる電気・照明設計が求められます。
以下では安全性と快適性を確保するための要点を解説します。
漏電対策・感電リスクの最小化
水と電気が共存するプール空間では、漏電や感電による事故のリスクを最小限に抑えることが電気設計の最重要課題です。
まず基本として、すべての電気機器に対し「漏電遮断器(ELB)」を設置し、漏電発生時に自動的に電源を遮断できる仕組みを整える必要があります。
特に水中照明やポンプなど、水と直接接する機器については、絶縁性能の高い製品を選定し、万一の故障でも感電しないよう設計しなければなりません。
さらに、アース接地の確実な施工も不可欠です。
金属製の器具や構造物に万一電流が流れた場合でも、確実に地面へ電流を逃がすことで感電を防ぐ構造が求められます。
あわせて、電気配線はプール利用者の動線から十分に離し、必要に応じて隔壁や防護カバーを用いて直接接触を防ぐ設計が推奨されます。
また、万一の事態に備えた非常停止スイッチの設置も重要です。
監視員や管理者がすぐに電源を遮断できる体制を整えることで、事故発生時の被害を最小限に抑えることが可能になります。
防湿・防水性能を満たす配線工事
湿度の高い屋内プール環境では、電気配線に対しても高い防湿・防水性能が求められます。
特に水蒸気や結露が常に発生する天井裏や設備ピットでは、通常の配線材料では腐食や絶縁不良の原因になりかねません。
したがって、使用する電線やケーブルは耐湿性・耐薬品性に優れたものを選定し、防水ボックスや気密ジョイントと組み合わせて施工することが基本となります。
配管方式としては、CD管やPF管よりも、防湿性の高いVE管(塩ビ電線管)や金属管(E管)の採用が推奨されます。
さらに、端子ボックスや分電盤においては「防滴形(IPX4相当)」「防噴流形(IPX5相当)」などの防水保護等級に準拠した製品を使用することで、長期的な信頼性を確保できます。
加えて、配線ルートは湿気が滞留しないよう配慮し、傾斜やドレン付きルートで結露水がたまらない設計とすることも忘れてはなりません。
屋内プール特有の高湿度環境では、電気設備の劣化が通常の建築物よりも早く進行するため、設計段階から長寿命を見据えた部材と工法の選定が不可欠です。
照度基準と演出照明の考慮点
プール施設の照明設計では、安全に遊泳できる十分な明るさ(照度)を確保しつつ、施設の雰囲気や視認性を高める演出照明のバランスが求められます。
照度の基準については、日本建築学会や厚生労働省のガイドラインを参照し、「水面:200lx前後」「プールサイド:150lx以上」「更衣室・廊下:100lx以上」などを目安とします。
水面照明は、天井からの直接照明に加え、水中照明を併用することで視界性とデザイン性を高めることができます。
特に夜間利用のある施設では、水中照明による美しい演出効果が利用者満足度に直結するため、色温度や光の拡散特性にも配慮した設計が重要です。
ただし、眩しさ(グレア)への対策も必要です。プールでは水面反射が強く、特定の照明が強すぎると視界を妨げ、事故につながる恐れがあります。
そのため、光源の角度調整や間接照明の活用により、視認性を確保しながら眩しさを抑える工夫が必要です。
以下の表は、施設の部位ごとの照度目安をまとめたものです。
| 施設部位 | 照度の目安(lx) | 備考 |
|---|---|---|
| 水面 | 200 | 安全な遊泳・視認性確保 |
| プールサイド | 150 | 歩行時の視界性向上 |
| 更衣室・通路 | 100 | 一般的な照度基準 |
| 水中照明 | 80〜150 | 演出・視認性を兼ねる |
このように、照明設計では基準の数値に加え、利用者の動きや視線の流れ、空間演出までを視野に入れた総合的な判断が求められます。
照度確保だけでなく、快適さと安全性の両立を図る視点が不可欠です。
設計時に参照すべき基準・ガイドライン
プール設備の設計では、安全性・快適性・衛生環境を確保するために、複数の基準やガイドラインを参照する必要があります。
特に公共性の高い施設では、法令・指針の順守が必須となります。
厚労省「遊泳用プールの衛生基準」
厚生労働省が示す「遊泳用プールの衛生基準」は、プール施設における衛生管理の基礎をなす重要な指針です。
この基準では、水質、ろ過・消毒方法、清掃頻度、温度管理、救護体制などについて具体的な数値目標や実施方法が明記されています。
たとえば、水質については「遊泳用水の塩素濃度を0.4mg/L以上1.0mg/L以下に保つ」などの数値基準が示されており、これにより感染症の予防や快適な遊泳環境の維持が可能となります。
また、シャワーや足洗い場の設置も義務づけられ、衛生面での配慮が求められています。
設計段階でこれらの内容を十分に理解し、施設レイアウトや配管設計に反映させることで、開業後のトラブルを未然に防ぐことができます。
日本建築学会の関連資料
日本建築学会では、プールを含む各種建築設備に関する設計指針や技術資料を発行しています。
特に「建築設備設計基準」や「建築環境工学」などは、空調・換気・照明・給排水に関する詳細な設計条件や評価基準が示されており、プール設備設計にも直接関係します。
たとえば、屋内プールにおける湿度制御では、「相対湿度60%以下を目標とする」といった推奨値が示され、カビや結露対策の参考になります。
また、照明設計では照度や色温度の基準、眩しさの制御に関する記載もあり、利用者の快適性と安全性に配慮した照明計画を立てるうえで有益です。
これらの資料は、建築設備士や設計士が設備設計の精度を高めるうえで欠かせない参考文献といえるでしょう。
地方自治体の設計指針への対応
プール設備の設計では、国の基準だけでなく、各自治体が独自に定める設計指針や条例にも対応する必要があります。
たとえば、東京都や大阪府などの大都市では、建築確認申請や衛生管理の審査において、独自の技術基準や提出書類が求められる場合があります。
また、地方自治体によっては、熱源設備の高効率化、雨水の再利用、バリアフリー対応など、環境保全や地域福祉の観点から追加要件を設けていることもあります。
さらに、学校プールや市民プールなど公共施設では、地域住民の利用を前提とした設計が求められるため、運用管理面まで含めた設計提案が望まれます。
設計初期段階で、管轄自治体の条例や技術基準を入念に調査し、計画に落とし込むことが、設計承認の円滑化と長期的な施設運用の安定化につながります。
設計前に確認すべき3つのポイント
プールの設備設計を行うにあたっては、設計段階で確認しておくべき重要なポイントがいくつか存在します。
特に「運用方針・用途」「維持管理コストとのバランス」「周辺環境への配慮」は、設計の根幹に関わる要素であり、後工程でのトラブルや修正を未然に防ぐためにも事前の確認が欠かせません。
クライアントの運用方針・用途
設計前に必ず確認すべきことのひとつが、クライアントの運用方針とプールの用途です。
たとえば、学校教育用のプールと、フィットネスクラブでの商業用プール、あるいはホテルでのリラクゼーション目的のプールとでは、求められる機能・設備は大きく異なります。
運用時間、利用者の年齢層、混雑予想、イベントの有無など、使用状況をヒアリングして明確にすることで、ろ過設備の能力や更衣室・シャワー室の導線設計、必要な安全対策にも差が出てきます。
また、今後の拡張性も視野に入れて設計しておくことで、長期的な施設活用の柔軟性にもつながります。
維持管理コストとのバランス
初期投資とランニングコストのバランスは、クライアントがプールを長期にわたり運用するうえで極めて重要な要素です。
最新設備を多数導入しても、保守が難しくコストが膨らめば、結果としてクライアントの負担になります。
特に水質管理システムやろ過装置、空調・加温設備は、定期点検や部品交換が発生するため、初期導入時の機種選定において「省エネ性」「耐久性」「メンテナンスのしやすさ」は必ず検討すべきです。
設計者は建築費だけでなく、年間の電気代・水道代・薬品代なども概算で提示し、設備選定の根拠として共有する姿勢が求められます。
近隣環境・騒音・排気への配慮
プール設備は、大型のポンプ・ろ過装置・加熱機器などの稼働により、一定の騒音や排熱、薬品臭などを発生させる可能性があります。
そのため、周辺が住宅地や病院、学校などの静かな環境に立地している場合には、騒音・臭気・排気の影響を最小限に抑える工夫が必要です。
たとえば、機械室の配置を建物の中央部にする、遮音パネルを設置する、排気ダクトを上部へ導くなど、設備的な設計調整が有効です。
建築基準法に加えて、自治体の環境条例や騒音規制の確認も必須となります。
こうした環境配慮は、施設周辺との良好な関係構築にもつながります。
まとめ
今回の記事では、プールの設備設計について解説しました。
設計前には、利用目的や運用方針を明確にし、維持管理コストや近隣環境への配慮を十分に検討しましょう。
事前確認を怠らず、実際の運用を意識した設計を心がけてください。
図面作成や機械設備設計、電気設備設計、自動制御設備設計、数量積算などの業務を外注したい、相談したいという方は以下のボタンをクリックしてお問い合わせページよりご連絡ください。