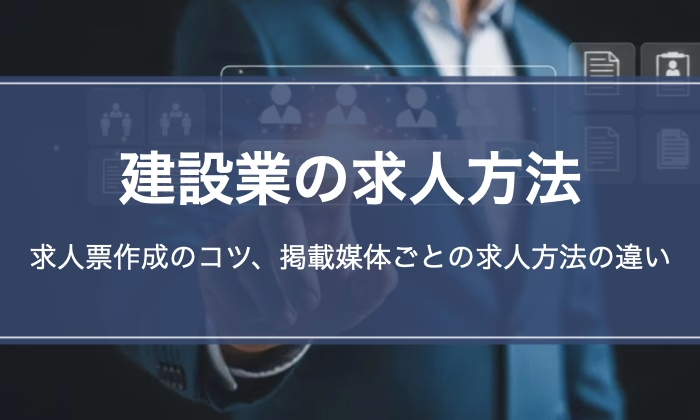「求人を出しても応募が全然集まらない…」ということはありませんか?
建設業界では深刻な人手不足が続いており、「どうすれば効果的に人材を集められるのか?」と悩んでいる経営者や採用担当者は少なくありません。
そこで、今回は建設業における効果的な求人方法と媒体選びのポイントについて解説します。
この記事を読めば、求人サイトの使い分けや無料で始められる掲載方法、自社に合った採用戦略の立て方がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業の採用現状と課題
建設業界では人手不足が深刻化しており、求人を出してもなかなか応募が集まらないという声が多く聞かれます。
建設業が抱える採用難には、いくつかの構造的な問題があります。
以下、それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。
有効求人倍率の高さ
まず、有効求人倍率です。
厚生労働省の職業安定業務統計によると、2023年の全産業平均の有効求人倍率は約1.26倍だったのに対し、建設業は約5.11倍と非常に高く、業界として求人数に対して圧倒的に応募者が不足している状況にあります。
この倍率の高さは、他業種と比較して建設業がいかに人材確保に苦戦しているかを示す重要な指標です。
離職率の高さ
次に、離職率の高さも大きな課題です。
建設業の離職率は10.3~10.5%とされており、全体平均(約8.5%)よりも高い水準です。
離職の主な要因としては、「長時間労働」「厳しい作業環境」「人間関係のストレス」「昇進やキャリア形成の不透明さ」などが挙げられます。
いわゆる“3K(きつい・汚い・危険)”といったネガティブな業界イメージが、求職者を遠ざける一因となっています。
若年層の業界離れ
また、若年層の業界離れも進行しています。
現場では高齢化が進行しており、技能継承の面でも危機的な状況です。
建設業就業者の約35%が55歳以上である一方、29歳以下の若手人材は全体の11%程度にとどまっており、将来的な人材不足がより深刻化する可能性も否定できません。
このような採用難の背景を理解したうえで、効果的な求人戦略を立てることが、建設業界における人材確保の第一歩となります。
建設業に特化した求人方法の概要
建設業における求人方法は、以下のように多岐にわたります。
それぞれの手法は、採用ターゲットや予算、採用スピードに応じて適切に使い分ける必要があります。
- 総合求人サイト(例:リクナビNEXT、マイナビ転職)
- 建設業専門求人サイト(例:建設転職ナビ、現キャリ)
- ハローワーク(公共職業安定所)
- 自社ホームページ(オウンドメディア採用)
- SNS(Instagram、X、YouTube、TikTok)
- リファラル採用(社員紹介)
- 人材紹介会社(建設特化型エージェント含む)
- 人材派遣会社
- 建設業団体やゼネコンが運営する求人サイト
- 求人チラシ・地域フリーペーパーなどの紙媒体
- 職業訓練校・専門学校との提携
- 外国人技能実習生制度の活用
これらの手法は単独でも機能しますが、母集団形成や定着率向上を目指すには、複数の手段を組み合わせるのが効果的です。
たとえば、「無料で始められるハローワーク+自社サイト」や「建設業専門サイト+SNS運用」のような組み合わせが近年注目されています。
よく使われる求人掲載の方式
求人掲載には、料金の支払いタイミングや成果の有無によって主に3つの課金モデルがあります。
それぞれのモデルと、どのメディアがどのモデルを採用しているかを以下にまとめました。
| 掲載方式 | 特徴 | 主な利用メディア |
|---|---|---|
| 掲載課金型 | あらかじめ一定の掲載料を支払って掲載。応募や採用数に関係なく費用が発生する。 | 総合求人サイト(リクナビNEXT、マイナビ転職など) |
| 成果報酬型 | 採用が決定した段階で費用が発生する。初期コストが抑えられる。 | 人材紹介会社、建設専門求人サイト(例:建職バンク) |
| 無料型 | 完全無料で求人を掲載・管理できる。応募数は多くないが、費用リスクがない。 | ハローワーク、自社ホームページ、SNS、ゼネコン専用求人サイトの一部 |
掲載媒体ごとの求人方法の違い
ここでは、建設業で活用できる具体的な求人方法について、主要な手法ごとに特徴・費用・メリット・デメリットを詳細に解説します。
企業の採用目的や予算に応じて、最適な手法を見極めましょう。
総合求人サイトでの求人掲載
総合求人サイトは、業種を問わず広範な求職者層にリーチできるメディアです。
建設業関連の求人でも、「建設業 求人サイト」として知名度の高いリクナビNEXT、マイナビ転職、dodaなどが代表格です。
多くの総合求人サイトは「掲載課金型」が基本で、掲載期間と表示順位に応じた料金体系が設定されています。
相場は1求人あたり10〜50万円(4週間)程度です。
成果に関係なく料金が発生するため、費用対効果を考慮する必要があります。
一部では「成果報酬型プラン」や「無料掲載・成功報酬あり」の形式もありますが、これは限定的です。
メリットは圧倒的な母集団形成力と検索性の高さ。デメリットは競合が多く埋もれやすい点や、建設業経験者にピンポイントで届きにくい点です。
建設業専門の求人サイト利用
建設業に特化した求人サイトは、業界経験者や資格保有者を対象とするため、質の高い母集団と出会えるのが最大のメリットです。
代表的なサイトには「建設転職ナビ」「現キャリ」「建職バンク」「施工管理求人ナビ」などがあります。
これらの媒体は、建築士・施工管理技士・重機オペレーターなど、建設系資格を有する専門人材と接点があるため、即戦力を求める企業にとっては非常に有効です。
案件例としては、施工管理・現場監督・設備保守・CADオペレーターなどがあります。
掲載方式は、掲載課金型(1案件5~30万円/月)と成果報酬型(年収の25~35%)が一般的です。
多くの場合、企業規模や募集職種によってプランが分かれており、専門性が高いため求職者の質も安定しています。
ゼネコン運営の求人サイト活用
大手ゼネコン(清水建設、大林組、大成建設など)や業界団体が運営する求人サイトでは、協力会社やパートナー企業を対象にした掲載枠が設けられているケースがあります。
こうしたサイトは、自社専用ではなく、グループ全体の人材確保や案件補助を目的としたもので、主に施工管理、設備系職種の求人が多く見られます。
たとえば、清水建設の「SHIMZ WORK」や、大成建設の「TAISEIキャリアパートナー」などが該当します。
協力会社であれば、条件次第で無料掲載が可能な場合もあり、母集団が建設業界内に絞られているためマッチング効率が高いという特徴があります。
一方で、掲載には審査や関係性の証明が求められることが多く、一般企業は利用できないケースもあります。
自社ホームページ(オウンドメディアリクルーティング)
自社のホームページで求人を行う「オウンドメディアリクルーティング」は、ブランディングや社風理解を促進し、定着率の高い採用を実現するための手法です。
採用コストも抑えられるため、中小建設会社にとっても非常に有効です。
求人ページでは、以下のような構成が効果的です。
- 募集職種の詳細(仕事内容・求める人物像)
- 勤務地・勤務時間・給与などの条件
- 社内の雰囲気が伝わる写真・インタビュー
- 資格取得支援や福利厚生
- 社長メッセージや企業ビジョン
加えて、検索エンジンからの流入を狙うために「建設業 求人」「地域名+職種」などのキーワードを盛り込んだSEO対策も不可欠です。
ページタイトル・見出し・本文に自然にキーワードを含め、定期的な更新を行いましょう。
ハローワークを使った無料求人掲載
ハローワークは、完全無料で求人を掲載できる公的サービスとして、建設業界でも広く利用されています。
地域密着型の採用に強く、特に地方の建設会社にとっては貴重な採用チャネルです。
無料である一方、求人票の内容によって応募の反応が大きく左右されるため、「仕事内容が伝わりやすい記述」「求める人物像の明記」「待遇の正確な記載」など、丁寧な設計が求められます。
デメリットとしては、専門職に特化した人材へのアプローチが難しいこと、また求人票が定型フォーマットで自由度が低いため、企業の魅力を伝えづらい点が挙げられます。
応募者の質にばらつきが出る傾向もあります。
SNSを活用した求人方法
SNSを活用した採用は、近年急速に広がりを見せている手法で、特に若年層や職人層への訴求に効果的です。
X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、LinkedIn、TikTokなどを活用して、日々の施工現場の様子や社員のインタビューを投稿し、企業の魅力を可視化できます。
成功事例としては、Instagramで「職人の一日」「現場飯」「現場の風景」などを発信して採用に繋げた企業や、TikTokでショート動画を投稿して若者からのエントリーを獲得した建設会社も存在します。
費用は基本無料ですが、継続的な運用や投稿の質が求められるため、採用担当の時間的リソースを割く必要があります。
また、SNS広告(有料)を併用することでターゲット層へのリーチを強化できます。
リファラル採用(社員紹介)
リファラル採用は、既存社員が友人・知人・元同僚などを紹介して採用につなげる手法です。
紹介された求職者は職場の雰囲気や仕事内容に理解があるため、定着率が高く、ミスマッチが少ない点が大きなメリットです。
実施の際は、紹介が成立した場合に社員へ報酬(例:5万円~10万円)を支払う「紹介インセンティブ制度」を設けると、参加率が高まります。
定期的な社内告知や、紹介事例の共有も重要です。
一方で紹介先に偏りが出やすく、多様な人材を集めにくい、関係性の問題で辞退しづらいなどのデメリットもあるため、他の採用手法と併用して運用するのが効果的です。
派遣・紹介エージェントの活用
即戦力を求める場合に有効なのが、建設業界に特化した人材派遣・紹介エージェントの利用です。
紹介型は、求職者の年収の30%前後を成果報酬として支払う形式が一般的です。
たとえば年収500万円の場合、成功報酬は150万円程度になります。
一方、派遣型は時間単価制で、1人あたりの派遣費用は月30〜60万円が目安。即戦力を短期間で確保できる点が強みで、繁忙期の現場対応や急な欠員にも対応できます。
以下に両者の違いを整理します。
| 項目 | 人材紹介 | 人材派遣 |
|---|---|---|
| 費用 | 成果報酬(年収の30%前後) | 時間単価制(月額30~60万円) |
| 雇用形態 | 正社員 | 派遣社員 |
| 適するケース | 長期雇用・幹部候補・有資格者 | 短期対応・現場の穴埋め |
目的に応じて、長期育成を前提とした紹介型か、即戦力確保を目的とした派遣型かを選択しましょう。
求人票作成/応募を集める書き方のコツ
求人票で応募者の目に留まり、応募意欲を高めるためにはターゲットの明確化、表現の具体性、労働条件の詳細記載などが重要です。
ここでは応募者に響く求人票を作成するための実践的な書き方のコツを解説します。
ターゲット(若者・資格保有者)を明確にする方法
効果的な求人票を作る第一歩は、どのような人に来てほしいか「ターゲット」を明確にすることです。
たとえば「若年層の未経験者」を採用したいのか、「施工管理技士や建築士などの資格保有者」を求めているのかによって、訴求すべき内容が大きく変わります。
若年層をターゲットにする場合は、「研修制度」「資格取得支援」「先輩の声」など、未経験者でも安心して働ける環境をアピールしましょう。
一方、経験者や資格保有者には、「担当案件の規模」「年収水準」「残業時間の実態」「裁量の範囲」など、より具体的な待遇面やスキル活用の幅を明示する必要があります。
また、求人票の冒頭で「こんな方を募集しています」といった形でターゲット像を明示すると、ミスマッチを防ぐ効果もあります。
これは選考時の効率化にもつながるため、事業者・求職者双方にとって有益です。
具体的な職種名表現と「1求人1職種」徹底の重要性
求人票で最も重要なのが「職種名」です。
求職者が最初に目にするこの部分が曖昧だと、クリックすらされません。
たとえば「現場スタッフ」ではなく、「施工管理技士(現場監督)」「重機オペレーター」「鉄筋工」など、具体的で専門的な職種名にすることで、応募者の目に留まりやすくなります。
また「1求人1職種」の原則を守ることも重要です。
複数の職種(例:現場監督/作業員/事務)をひとつの求人にまとめると、求職者は「自分に合っていない」と感じやすく、結果として応募を逃してしまいます。
具体的な役職や必要資格、働くシーンを連想しやすい表現を使うことで、応募意欲が高まりやすくなります。
たとえば「公共インフラの施工管理」「住宅基礎工事の重機オペレーター」など、業務内容や担当分野を組み合わせた職種名が有効です。
勤務条件、労働環境、安全対策、キャリア成長や福利厚生などを詳細に記載
建設業界の求職者は、給与や勤務時間といった基本条件だけでなく、「労働環境」や「安全対策」「キャリアアップ支援制度」にも敏感です。
求人票においては、以下のような項目を網羅し、明確かつ誤解のないよう記載することが求められます。
| 項目 | 記載のポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 勤務条件 | 給与、賞与、昇給、勤務時間、休日休暇 | 具体的な数値・実績を記載 |
| 労働環境 | 平均残業時間、現場の雰囲気、チーム体制 | 過度な演出は避け、実態を正直に |
| 安全対策 | ヘルメット・装備支給、月次安全研修、KY活動 | 写真や研修実績で可視化するのが効果的 |
| キャリア成長 | 資格取得支援、社内研修制度、キャリアパス | 受講対象者・支援内容を明示 |
| 福利厚生 | 社会保険、退職金制度、住宅手当、家族手当など | 「あり」だけでなく中身まで説明する |
求職者は、「入社後にどんな働き方ができるのか」「将来のビジョンが描けるか」を重視します。
求人票を通じて、その人が入社後に感じるであろう不安を取り除けるよう、丁寧かつ具体的に伝えることがポイントです。
そうすることで、単なる応募数ではなく、「本気度の高い応募」を得ることができます。
効果的な組み合わせ戦略
建設業の採用成功には、1つの媒体に依存せず、無料媒体と有料媒体をうまく組み合わせることが重要です。
リファラル採用や成果報酬型求人の活用、広告コストに対する応募効果も踏まえたメディア選定が成果を左右します。
無料媒体と有料媒体を掛け合わせた母集団形成
採用活動において応募数=母集団の形成は最優先の課題です。
特に建設業界では人材不足が慢性化しているため、採用の入り口を広げることが不可欠です。
そのため、無料で利用できる媒体と有料媒体の組み合わせが有効です。
無料媒体では、ハローワークや自社採用サイト(オウンドメディア)、SNS(InstagramやXなど)が代表的です。
コストをかけずに情報発信できる一方、即効性や応募者の質にばらつきが出やすい傾向があります。
有料媒体には、総合求人サイト(例:マイナビ転職、リクナビNEXT)や建設業専門求人サイト(例:現キャリ、建設求人ナビ)があります。
これらの媒体には、求職者の「転職意思が高い」ことが多く、母集団の質が担保されやすいという強みがあるんです。
これらを掛け合わせて戦略的に活用することで、応募数と質のバランスを取りながら効率的な母集団形成が可能になります。
たとえば、ハローワークとSNSで広く告知しつつ、有料サイトで経験者を狙い撃ちするような形です。
リファラル採用や成果報酬型との併用戦略
リファラル採用(社員紹介)は、コストを抑えながら自社にマッチした人材を紹介してもらえる方法です。
実際、社員紹介で入社した人は離職率が低くなる傾向にあります。一方で、紹介が出ない期間は母集団形成が止まってしまうため、他の媒体との併用が不可欠です。
そこで有効なのが、成果報酬型の求人サイトです。
成果報酬型とは、採用に至った場合に初めて費用が発生するモデルで、人材紹介会社や一部の専門求人サイトに多く見られます。
この仕組みを活用することで、リファラルで補いきれない職種や人数をカバーできます。
例えば、「施工管理技士はリファラルで紹介」「現場作業員は成果報酬型求人サイトとハローワークを併用」といったように職種ごとに採用チャネルを分ける戦略が効果的です。
下記のように、目的別にメディアを使い分けることで、過不足のないバランス型の採用戦略が実現します。
| 媒体種別 | 主な役割 | 活用例 |
|---|---|---|
| リファラル採用 | 信頼性・定着率の高い人材の確保 | 資格保有者や長期勤務前提の若手 |
| 成果報酬型サイト | 即戦力を低リスクで確保 | 施工管理、設計、事務職 |
| 無料媒体(SNS・ハローワーク) | 認知拡大・予算ゼロで母集団形成 | 若年層、未経験歓迎枠の告知 |
費用対効果を意識したメディア選定例
限られた広告予算のなかで成果を最大化するには、費用対効果(ROI)を踏まえたメディア選定が欠かせません。
たとえば、建設業における1名あたりの採用単価は30~100万円前後といわれており、無駄な出稿は避けるべきです。
まず注目すべきは「掲載課金型」か「成果報酬型」かの違いです。
掲載課金型は掲載しても応募がなければ費用が無駄になる一方、成果報酬型は実際の採用まで費用が発生しないため、初期コストを抑えたい企業には適しています。
さらに、SNSや自社サイトといった無料媒体と有料媒体をバランスよく組み合わせることで、トータルの広告費を抑えつつも、広範な母集団を確保できます。
特に地方の建設会社では、ハローワークとSNS、自社サイトの連携が広告費ゼロで成果を上げる好例もあります。
たとえば以下のようなメディア構成が現実的です。
| 目的 | 推奨媒体 | 費用感 |
|---|---|---|
| 経験者採用(即戦力) | 成果報酬型求人サイト、人材紹介 | 採用時30%前後 |
| 未経験者・若手採用 | ハローワーク、Instagram、X | 無料 |
| 企業ブランディング強化 | 自社採用サイト+SNS | 初期制作+運用工数 |
最終的には「どの媒体で」「どんな人材を」「どのくらいの費用で」採用するのかを明確にしたうえで、継続的にPDCAを回すことが効果的な戦略構築につながります。
媒体任せにせず、自社に合った組み合わせを探る姿勢が重要です。
採用時に注意すべきポイント
採用活動の成否は採った時点ではなく、定着・戦力化に至ってこそ成果と言えます。
そのため、離職防止に向けた制度整備と、採用後の教育・育成体制の構築が非常に重要です。
離職率を下げるための制度整備(OJT・資格支援・定年延長)
建設業界では、せっかく採用した人材が早期に離職してしまうケースが後を絶ちません。
その主な要因は「入社後のフォロー不足」「キャリアの見通しが立たない」「技術習得の支援が不十分」などです。
これを防ぐには、制度面からのアプローチが不可欠です。
まず効果的なのが、OJT(On the Job Training)の体系化です。
新人が現場で経験を積むのは当然ですが、計画性のない現場任せの指導では個人差が生じやすく、モチベーションも維持できません。
育成担当者の明確化やチェックリスト形式の進捗確認シートなどを用意することで、育成プロセスの均質化が図れます。
また、資格取得支援制度も定着率向上に有効です。
施工管理技士や建築士など、キャリアアップに直結する資格の受験料補助、講習費支援などの制度があると、社員の成長意欲を喚起しやすくなります。
これはとくに若手社員にとって「この会社なら成長できる」という安心感にもつながります。
加えて、近年では定年延長や再雇用制度の整備も注目されています。
高年齢層の技術者が持つ豊富な知見を活用することで、若手育成との好循環が生まれやすくなります。
高齢化が進む業界だからこそ、シニア人材の活用も採用戦略における重要な一手です。
採用後に活かす社内体制:教育・育成の仕組みの重要性
採用活動が終わった段階で気を緩めてしまうと、定着・戦力化が進まず、結果的に高い採用コストが無駄になるリスクがあります。
人材の定着には、入社後の「育てる仕組み」が不可欠です。
まず導入すべきなのが、入社後3か月〜1年の育成プランです。
たとえば、「1週目は安全教育と社内ルール」「2週目は現場見学」「3週目から実作業補助」といったように、段階的に業務を習得できるようなカリキュラムを設計する必要があります。
ここで重要なのは、何をいつまでに習得すればよいのかを明確にし、本人と上司が進捗を共有できる状態を作ることです。
また、定期的な面談やフォローアップ面談も効果的です。
月1回程度、直属の上司や人事担当が面談を実施し、不安や悩みを吸い上げることで離職リスクを事前に回避できます。
特に若手や未経験入社の社員にとっては、こうした声かけが大きな安心感につながるのです。
さらに、中長期的な育成制度として、年次別研修や職種別研修を導入する企業も増えています。こ
れにより、社員のキャリアパスが可視化され、目指すべき成長イメージが定まります。
たとえば、「3年目で2級施工管理技士取得」「5年目で主任昇格」などの目標設定が、本人の意欲を高める要因となります。
以下のように、教育制度と支援制度の整備状況を一覧にして整理しておくと、課題発見や施策の優先順位が立てやすくなります。
| 制度項目 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| OJT教育制度 | 配属先に育成担当を設定し、育成計画を明文化 | 業務習熟までの期間短縮、離職抑止 |
| 資格取得支援 | 講習・受験費用の全額補助、社内勉強会 | スキル向上、成長実感による定着促進 |
| 定年延長制度 | 60歳以降も現場技術者・教育担当として再雇用 | 経験継承・人手不足対策 |
| キャリア研修 | 年次別・職種別に応じた定期研修を設計 | 中長期の育成・昇格意識の醸成 |
採用活動は、採るだけでなく「活かす」ことが本質です。
どんなに良い人材でも、受け入れる体制が整っていなければ成果につながりません。
制度整備と育成支援の両輪で、持続可能な採用体制を築くことが求められています。
まとめ
今回の記事では、建設業の求人方法について解説しました。
求人票の書き方には、「正解」があるようでいて、実際には会社ごとにズレやすいポイントがあります。
この記事で紹介した内容を踏まえても、
- 本当に伝わっているか分からない
- どこを直せばいいのか判断できない
- これ以上盛るのは不安
と感じた場合は、一度客観的に確認するのが近道です。
現在、建設・設備業向けに求人票・採用ページの無料診断を行っています。
- 表現が誤解を生んでいないか
- 応募者目線で違和感がないか
- 直すべき箇所がどこか
を整理してお伝えします。
作り直しや代行を前提としたものではありません。
まずは「このままで良いか」の確認としてご利用ください。