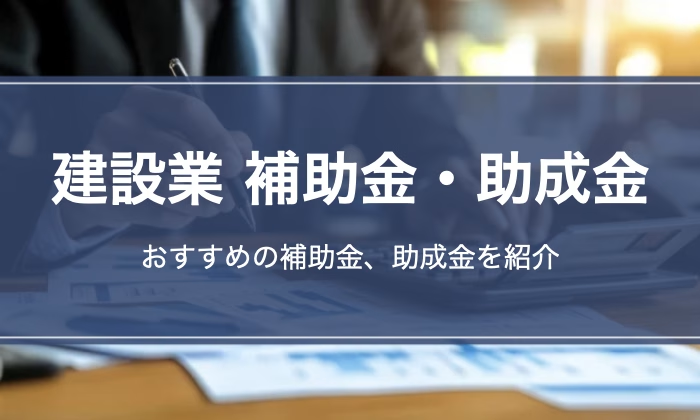「補助金や助成金を活用したいけど、建設業向けに何があるのかわからない」と悩んでいませんか?
どの制度が自社に合うのか分からず、せっかくのチャンスを逃してしまうのはもったいないですよね。
そこで、今回は建設業で活用できる補助金・助成金の種類や特徴、申請時の注意点について解説します。
この記事を読めば自社に合った補助金・助成金の選び方や、2025年に注目すべき制度のポイントがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
2025年建設業が直面する4つの経営課題
2025年の建設業界は、複数の深刻な経営課題に直面しています。
とくに人材不足や原材料高騰、資金繰りの悪化といった構造的な問題は避けて通れず、今後の経営戦略に大きな影響を及ぼす要因となっています。
以下では、それぞれの課題について詳しく解説します。
2025年問題:高齢化と人材流出
建設業における「2025年問題」とは、主に技能労働者の高齢化と若年層の入職不足により、現場の人手が極端に足りなくなる問題を指します。
国土交通省の調査によれば、建設業従事者の約35%以上が55歳以上であり、29歳以下は全体のわずか11%程度にとどまっています。
このままでは、経験を積んだ職人の大量退職に伴い、技術の継承が滞るだけでなく、施工力そのものの低下につながる恐れがあります。
また、若手が定着しにくい理由としては「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージや、長時間労働・低賃金などの労働環境の課題が根強く存在します。
政府も人材確保等支援助成金などを通じて業界全体の改善を図っていますが、現場レベルでは依然として深刻な状況が続いています。
人材流出を食い止めるには、単なる採用だけでなく、職場環境の抜本的な見直しや若手育成の仕組みづくりが求められます。
資材・人件費の高騰と利益圧迫
建設業界では、2021年以降の世界的な物流混乱やウクライナ情勢の影響などにより、建築資材やエネルギー価格が大幅に高騰しています。
加えて、最低賃金の引き上げや職人不足による人件費上昇が、工事原価を押し上げ、企業の利益を圧迫する要因となっています。
下記の表は、建設業界でよく使われる主要資材の価格推移(2022〜2025年見込み)です。
| 資材名 | 2022年価格(円/単位) | 2025年予測価格(円/単位) |
|---|---|---|
| 鉄筋 | 98,000 | 112,000 |
| 合板 | 1,200 | 1,450 |
| 生コン(m³) | 13,500 | 15,200 |
このようなコスト増加をクライアントに転嫁できないケースも多く、特に中小の建設企業では利益率が著しく低下しています。
その結果、資金繰りの悪化や事業継続リスクの増大につながっており、経営の安定を図るために補助金や助成金の活用が不可欠な状況です。
支払いサイトの長期化による資金繰り難
建設業界では元請・下請の構造上、工事完了から入金までの期間(支払いサイト)が長期化しやすく、資金繰りが慢性的に不安定になる傾向があります。
特に公共工事や大型案件では、契約から入金までに数ヶ月以上を要することも珍しくありません。
その一方で、資材購入や人件費の支払いは先行する必要があり、キャッシュフローが逼迫する要因となります。
とくに中小企業では、金融機関からの借り入れが難しいケースや、担保が不足している場合も多いため、経営の健全性を保つには「資金繰り支援制度」や「ファクタリング」などの資金調達手段に加え、補助金・助成金による資金支援が重要な選択肢となります。
さらに、近年では資金繰り改善を目的とした「建設業 助成金」や、省力化投資を促進する補助金も登場しており、これらを活用することで収益構造の見直しにもつながる可能性があります。
時間外労働の規制と人手不足
2024年4月から建設業に対しても「働き方改革関連法」が全面適用され、時間外労働の上限規制(原則月45時間、年360時間)が導入されました。
これにより、今まで繁忙期に残業でカバーしていた労働形態が大きく制限され、人手不足がより深刻化しています。
特に、現場ごとに納期や工程が異なる建設業では、柔軟な労働時間の確保が難しいため、工期遅延や施工不良リスクの増加が懸念されています。
実際に、多くの企業が現場作業の平準化やシフト管理の見直しを進めており、ITツールの導入やロボット技術による自動化が急務となっています。
このような労働環境改善に対しては、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」や、建設業に特化した「人材確保等支援助成金」が有効です。こうした制度を上手に活用することで、従業員の定着率向上と生産性改善を両立させることが可能になります。
建設業が補助金・助成金を活用すべき理由
建設業界では、人手不足や資材費高騰など、経営を圧迫する要因が年々増えています。
こうした中、補助金や助成金の活用は資金調達の負担を軽減しつつ、成長投資や人材対策を加速させる有効な手段です。
ここでは建設業が補助金・助成金を活用すべき3つの理由について解説します。
返済不要で経営負担を軽減
補助金・助成金の最大の特徴は「返済不要」である点です。
銀行融資やリースなどとは異なり、財務上の負担を最小限に抑えつつ、設備投資や人材育成に資金を投入できるメリットがあります。
特に中小建設業にとっては、資金繰りが厳しい中で大きな支えとなります。
たとえば、IT導入補助金やものづくり補助金では、最大で数百万円〜1,000万円単位の資金が支給され、施工管理アプリの導入や省人化機器の導入などに活用する事例が増えています。
こうした制度は、融資とは異なり返済義務がないため、事業のキャッシュフローを圧迫しません。
また、助成金についても、賃金アップや労働環境の整備に取り組むことで受給できる制度が多数存在します。
返済不要というメリットを最大限に活かし、戦略的な設備更新や人材投資につなげることができます。
生産性向上・人材確保の手段になる
補助金・助成金は単なる資金支援にとどまらず、企業の生産性向上や人材確保を後押しする制度設計がされています。
近年は、建設業界における人手不足対策として、省人化や自動化を目的とした補助制度が強化されており、ITツールやロボット導入にかかる費用の一部が補助されるケースもあります。
たとえば「中小企業省力化投資補助金」は、省人化に貢献する設備・システムの導入に対して補助率最大1/2が支給され、業務負担の軽減と人件費の最適化を同時に実現できます。
また、「人材確保等支援助成金」では、働きやすい職場環境の整備や若手技能者の育成支援を目的とした助成が可能です。
このように、建設業の将来を見据えた制度活用は、単なる経費削減ではなく、組織全体の競争力強化にも直結します。
ファクタリングとの併用も効果的
補助金や助成金は申請から支給までに時間がかかるため、資金繰りが逼迫している建設業者にとっては、タイムラグが大きなネックになることがあります。
そこで注目されているのが「ファクタリング」との併用です。
ファクタリングとは、完成工事などの売掛債権を専門業者に譲渡することで、早期に現金化する資金調達手法です。
補助金の採択後、実際に支給されるまでの間の資金繰り対策として利用する企業が増加しています。
特に、小規模な建設事業者では補助金の自己負担分を先に立て替える必要があるため、一時的な資金確保の手段としてファクタリングは有効です。
さらに、金融機関の融資と違い、信用情報に影響を与えずスピーディに資金化できる点もメリットとなります。
補助金で中長期的な競争力強化を図りつつ、ファクタリングで短期的なキャッシュフローの安定化を実現することで、建設業者の経営基盤をより強固に構築できます。
2025年に活用したい建設業向け補助金5選
2025年は建設業にとって経営課題が一層深刻化する年とされ、多くの企業が設備投資や業務改革に迫られます。
そこで活用したいのが補助金制度です。ここでは建設業に特化して、2025年に注目すべき補助金を5つ厳選してご紹介します。
| 補助金名 | 主な目的 | 補助額・補助率 |
|---|---|---|
| ①IT導入補助金 | 業務効率化・IT化 | 最大450万円(補助率1/2) |
| ②ものづくり補助金 | 設備投資・生産革新 | 最大1,250万円(補助率1/2〜2/3) |
| ③小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓・効率化 | 最大200万円(補助率2/3) |
| ④事業再構築補助金 | 新分野進出・構造転換 | 最大1億円(補助率2/3) |
| ⑤省力化投資補助金 | 人手不足対策・省人化 | 最大1,500万円(補助率1/2) |
①IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業の業務効率化やデジタル化を支援する制度で、建設業でも施工管理システムや勤怠管理アプリの導入に活用できます。
補助対象となるのはソフトウェア導入費やその設定費用、クラウド利用料などで、最大補助額は450万円(デジタル化基盤導入枠の場合)です。
例えば、建設現場の進捗状況をリアルタイムで把握できるアプリを導入することで、事務作業を大幅に削減でき、現場監督の業務負担も軽減されます。
また、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応するシステム導入にも利用でき、法令対応のコスト削減にもつながります。
IT導入補助金は定期的に公募されており、事前にIT導入支援事業者の登録ソリューションから選定する必要があります。
早めの準備とスケジュール管理が成功の鍵です。
②ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業が革新的な製品開発や生産プロセス改善を行う際に活用できる制度です。
建設業では、例えば新たな施工工法の導入、業務の省力化・自動化を図る機械設備の導入などが対象となります。
補助額は100万円〜最大1,250万円、補助率は原則1/2(小規模企業や特定要件を満たす場合は2/3)で、比較的大型の投資にも対応できるのが特長です。
たとえば、鉄骨加工の自動化設備を導入することで、作業時間を半減し、生産性を大幅に高める事例もあります。
公募は年数回実施され、審査も厳格なため、事業計画の説得力や収益性の明確化が求められます。
実現性の高いプランと丁寧な申請書作成が採択へのポイントです。
③小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない建設業者でも使いやすい補助制度で、販路開拓や業務効率化に対する取り組みに対し支援が受けられます。
補助上限額は50万円〜200万円程度(通常枠・特別枠により異なる)で、補助率は2/3が基本です。
対象となる経費は、チラシ制作費やホームページの作成、業務効率化のための簡易なITツール導入費、広告費などで、営業活動の底上げや新規受注の獲得に役立ちます。
たとえば、リフォーム専門の建設業者が地域向けにDMを配布し、問い合わせ件数を増やしたという事例もあります。
比較的申請のハードルが低く、個人事業主や一人親方にも利用しやすいため、小規模建設事業者の経営支援に適しています。
④事業再構築補助金
事業再構築補助金は、ウィズコロナ・アフターコロナ時代に対応したビジネスモデルへの転換を支援する制度で、建設業でも新分野への進出や事業の大規模な変革時に活用されています。
例えば、土木業から太陽光発電の施工・保守事業への展開などが対象となり得ます。
補助額は従業員数や事業規模に応じて100万円〜最大1億円、補助率は中小企業で2/3(通常枠の場合)です。
既存事業との関連性や将来的な収益性が問われるため、しっかりとした事業計画の策定が重要になります。
また、近年は「グリーン成長枠」や「産業構造転換枠」などテーマに特化した枠組みも追加されており、脱炭素化やDX推進といった政策に沿った取り組みに対する優遇措置もあります。
⑤中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金は、2024年度からスタートした新制度で、人手不足に悩む中小企業に対して省力化設備の導入を支援する補助金です。
建設業では、測量ドローン、無人搬送車(AGV)、ICT施工機器の導入などが想定されています。
補助額は最大1,500万円、補助率は最大で1/2。対象設備は、事前に登録された「カタログ」内から選定する必要がある点が特徴で、審査も比較的簡易です。
労働集約型の業務が多い建設業にとって、人的負担を減らしつつ生産性を高める設備投資に活用しやすい補助金といえるでしょう。
2025年に申請できる建設業の助成金4選
2025年は建設業界にとって人手不足や労働環境の改善が重要な経営課題となる年です。
国や自治体の助成金制度を上手に活用することで、雇用の安定や働き方改革を推進するチャンスになります。
ここでは、建設業におすすめの助成金を4つご紹介します。
| 助成金名 | 目的 | 最大助成額 |
|---|---|---|
| ①人材確保等支援助成金 | 職場環境の改善と人材定着 | 72万円(コースにより変動) |
| ②トライアル雇用助成金 | 試行的雇用によるミスマッチ防止 | 12万円(1人あたり) |
| ③業務改善助成金 | 最低賃金引き上げと生産性向上 | 最大600万円 |
| ④働き方改革推進支援助成金 | 長時間労働の是正と労務管理改善 | 最大240万円 |
①人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、職場環境の改善や働きやすい職場づくりを通じて、人材の定着と確保を図る事業主を支援する制度です。
建設業では「雇用管理制度助成コース」や「働き方改革支援コース」などが活用しやすく、従業員の評価制度導入や健康づくり施策を導入する際に申請できます。
たとえば、評価制度を新たに構築・運用し、定着率を向上させた場合には最大72万円が助成されます。
また、就業規則の整備、短時間勤務制度の導入、社内研修制度の構築など、幅広い取り組みが対象です。
従業員数が限られた中小建設業でも導入しやすい支援策であり、人材が定着しにくい現場の課題解決にも直結します。
労務管理の改善を通じて、企業全体の魅力向上にもつながります。
②トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、求職者の就業機会の確保と企業側の雇用リスク軽減を目的に、一定期間試行的に雇用した場合に助成される制度です。
建設業では、未経験者や高齢者などを採用する際に特に有効で、3か月間の試用期間を設けてから正式採用する形をとることで、ミスマッチを防ぐことができます。
助成金額は、対象者1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)で、最大12万円が支給されます。
対象者には、若年層、就職困難者、母子家庭の母などが含まれ、求人票への「トライアル雇用希望」の記載が必要です。
特に建設業では、体力や技能に応じた適正配置が重要になるため、実際の作業を通じて適性を見極められるこの制度は、定着率の向上にもつながります。
正式採用後には他の助成金(キャリアアップ助成金など)との併用も可能です。
③業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上に取り組むことを目的として、最低賃金の引き上げとともに業務効率化を図るための設備投資を支援する制度です。
建設業では、タイムカードのIC化、建設資材の自動搬送装置、勤怠管理システムの導入などが対象となります。
助成額は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その業務改善にかかる設備投資費用の一部(最大600万円)を補助するというものです。
補助率は、事業規模により3/4または4/5に設定されています。
建設業界では、現場労働の非効率さや人手不足が慢性化しているため、ICTや省力化機器の導入を進めることで、職場環境の改善と同時に助成金も得られるという大きなメリットがあります。
単なる支援金ではなく、生産性向上と賃金改善をセットで進められる制度です。
④働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、時間外労働の削減や多様な働き方の導入などを支援するもので、建設業の「2024年問題」対策にも適した制度です。
たとえば、36協定の見直しや労務管理ツールの導入、テレワーク環境整備などに活用できます。
建設業においても、現場労働者の勤務時間管理は大きな課題です。
たとえば、勤怠管理システムやGPS打刻アプリなどを導入し、時間外労働を可視化・抑制することで、上限規制への対応が進められます。
助成上限は100万円〜240万円(コースにより異なる)で、補助率は3/4〜4/5となっています。
また、この制度は複数の取組を組み合わせて申請できるため、テレワーク導入と人材研修の実施など、総合的な働き方改革にも対応できます。
将来的な若手人材の採用・定着にも効果的な制度です。
補助金・助成金を活用する際の注意点
補助金・助成金は経営支援に有効な制度ですが、活用にあたってはいくつか注意点があります。
事前に理解しておくことで、申請の失敗や資金計画の混乱を防ぎ、効果的に制度を活かすことが可能になります。
自己資金の準備が必要なケースも
補助金や助成金の多くは「後払い方式」で支給されます。
つまり、対象となる設備の購入や制度導入にかかった費用を一度事業者側が立て替え、その後に補助金として支払われるという仕組みです。
そのため、制度を利用する前に自己資金を準備しておく必要があります。
たとえば、補助率が3/4の制度であっても、残りの1/4は自社負担になりますし、補助金が支給されるまでの数か月間の資金繰りも考慮しなければなりません。
自己資金や運転資金に余裕がない状態で制度を使うと、事業の途中で資金がショートしてしまうリスクもあるのです。
このような点から、補助金・助成金を計画的に活用するためには、事前に「資金調達計画」をしっかりと立てておくことが大切です。
必要に応じて銀行融資やファクタリングの活用も検討しましょう。
申請書類は専門家のサポートを活用
補助金や助成金を受けるためには、申請書類の作成や実施計画の記載、収支計画など、専門的かつ正確な手続きが必要です。
不備があると審査に通らなかったり、支給が遅れたりするため、制度ごとの要件に沿った書類作成が求められます。
特に建設業の場合、現場作業に追われる中で複雑な書類を独自で準備するのは現実的ではないケースも多く見受けられます。
そのため、中小企業診断士や社会保険労務士、行政書士など、補助金申請の実績がある専門家の支援を受けることをおすすめします。
また、専門家に依頼することで、申請時の加点要素や他の制度との併用の可能性も提案してもらえるメリットがあります。
報酬は発生しますが、結果的に採択率の向上や手続きの簡素化につながり、時間とリスクの両方を抑えることができます。
制度変更に備えて最新情報を確認
補助金・助成金の制度は年度や政府方針により頻繁に変更されます。
たとえば、申請期間が急に短縮されたり、要件が追加されたりするケースがあり、前年までの情報を参考にしていても、最新の内容と異なることがあります。
実際、2023年度以降もDX関連の補助金が新設されたり、働き方改革関連の助成金が拡充されたりと、情勢に応じた改定が行われています。
こうした変更に柔軟に対応するためにも、制度の公式ホームページ(経済産業省、中小企業庁、厚生労働省など)をこまめにチェックすることが重要です。
また、信用できる中小企業支援サイトや、各地の商工会議所・事業支援センターなどからも最新の情報が発信されていますので、定期的に確認しましょう。
まとめ
今回の記事では、建設業の補助金、助成金について解説しました。
申請には自己資金の準備や正確な書類作成が必要です。
制度変更も多いため、常に最新情報を確認し、専門家の力を借りながら確実に活用しましょう。