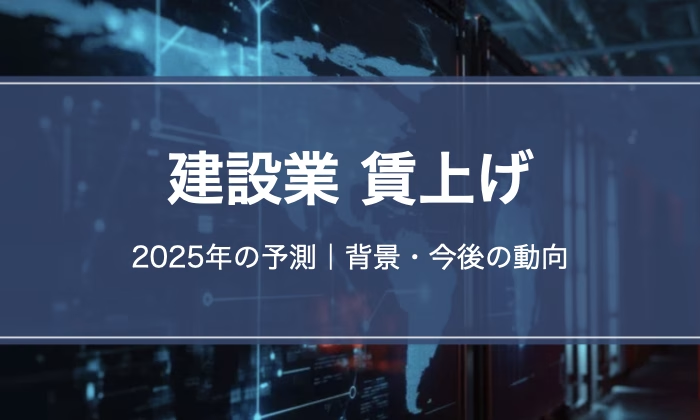2025年の建設業における賃上げ予測と、その背景や企業動向について解説します。
この記事を読めば、大手から中小までの賃上げ傾向や政府の支援策、今後の課題と展望がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建設業界における2025年の賃上げ予測
2025年の建設業界では、人材不足や法規制の影響を背景に賃上げが継続すると見込まれています。
過去2年間の実績や春闘の要求水準、大手企業の動きを見ると、前年以上の賃上げが現実的な流れとなっており、業界全体での給与改善が進むことが予測されます。
2023年・2024年の賃上げ実績から見る傾向
2023年と2024年の賃上げ実績を振り返ると、建設業界は全産業平均を上回る水準で推移しています。
| 年度 | 建設業の平均賃上げ率 | 全産業平均 |
|---|---|---|
| 2023年 | 3.36% | 3.60% |
| 2024年 | 5.94% | 5.33% |
厚生労働省の調査によれば、2023年の建設業の平均賃上げ率は3.36%であり、全体の3.6%に近い数値でした。
翌2024年には大きく伸び、建設業は5.94%と、全体平均の5.33%を上回る結果となっています。
特に大手建設会社では6%を超える賃上げを実施し、新卒初任給の引き上げや賞与増額といった具体策が取られました。
このような背景には、2024年問題として注目された残業時間上限規制の影響や、慢性的な職人不足があります。
加えて、物価高騰に対応するための生活水準維持が求められていることもあり、給与改善は不可避となりました。
これらの実績は、2025年も賃上げ傾向が続くことを裏付ける材料といえるでしょう。
2025年春闘の目標と中小企業への影響
2025年の春闘において、労働組合の連合は「賃上げ分3%以上、定期昇給を含めて5%以上」という目標を掲げています。
さらに、中小企業については大企業との格差是正を目的に、1%上乗せした水準を要求し、6%を目安とした引き上げを提案しています。
この数値は、単なる給与改善にとどまらず、人材定着や新規採用の競争力を確保するための戦略的な意味合いを持っています。
一方で、中小企業にとっては人件費の増加が経営を圧迫するリスクがあります。
特に資材高騰や工期短縮といった課題を抱える現場では、十分な原資を確保できるかが焦点となります。
ただし、政府は総合評価落札方式における加点制度や賃上げ促進税制を通じて、中小企業の負担軽減を図っています。
そのため、一定の支援策を活用することで、中小企業においても安定した賃上げが実現する可能性が高いと考えられます。
2025年は、大手と中小の賃上げ格差を是正する重要な転換点となるでしょう。
2025年賃上げを表明した大手建設企業の動き
すでに複数の大手建設企業が2025年の賃上げ方針を公表しています。
代表的な例が西松建設で、ベースアップと定期昇給を合わせて平均10%超の賃上げを予定しています。
さらに、新卒総合職の初任給を前年比13%増の30万円とする方針を打ち出し、人材確保に積極的な姿勢を見せています。
また、竹中工務店や大成建設といった業界大手も、2024年に引き続き高い水準のベースアップを実施する見込みです。
特に竹中工務店では、人的資本投資として大幅な給与改善を続けており、新卒初任給の引き上げも継続的に実施しています。
鹿島建設や清水建設も若手社員を中心に処遇改善を進め、賞与や諸手当の見直しを含めた施策を導入しています。
これらの動きは、単に従業員の生活を支えるだけでなく、人材不足が深刻化する中で優秀な人材を確保するための競争力強化策といえます。
大手企業の姿勢は業界全体に波及効果をもたらし、2025年は賃上げの広がりが一層加速すると予測されます。
賃上げが進む背景と要因
建設業界で賃上げが進んでいる背景には、人材不足や規制強化、物価高騰といった複合的な要因があります。
さらに、政府が政策的に賃上げを後押ししていることも大きな要素です。ここでは、それぞれの要因を詳しく見ていきます。
深刻化する職人不足と高齢化問題
建設業界では、職人不足と高齢化が深刻な課題となっています。
国土交通省のデータによれば、建設業従事者の約3割が55歳以上であり、29歳以下の若年層は全体の1割程度しかいません。
このままでは、技能継承が進まず、現場の生産性低下や工期遅延を招く可能性が高いとされています。
こうした状況の中で人材を確保するためには、処遇改善が不可欠です。
特に若手層に対しては、他産業と比較しても魅力のある給与水準を提示しなければ、新規参入を促すことは難しいのが現状です。
そのため、賃上げは人材不足解消と若手獲得の両面で避けられない施策となっています。
また、熟練技能者が引退する前に若手を育成する必要性も高まっており、賃上げによる人材循環が今後の持続可能性を左右するといえるでしょう。
2024年問題(残業時間上限規制)の影響
建設業界における2024年問題とは、働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が適用されることを指します。
これにより、従来のように長時間労働で人手不足を補う方法が使えなくなりました。
その結果、企業は限られた労働時間内で業務を遂行する必要があり、従業員1人あたりの価値が相対的に高まりました。
この状況は、労働力の需給ギャップをさらに拡大させ、賃上げ圧力を強めています。
現場では人材確保が最優先課題となり、給与引き上げによって他社との差別化を図る動きが広がっています。
また、時間外労働の削減に伴い、労働生産性を高めるためのデジタル技術導入も進んでいますが、短期的には人件費増加が避けられず、賃上げは現実的な対応策とされています。
2024年問題は労働環境の改善を促す一方で、賃金体系の見直しを加速させたといえるでしょう。
建設業特有の構造問題(下請け・一人親方制度など)
建設業界には多重下請け構造や一人親方制度といった特有の仕組みが存在し、これが賃上げ実現を難しくしてきました。
元請企業が賃上げを行っても、下請や孫請の段階にまで波及しにくく、実際に現場で働く職人の収入改善にはつながりにくいのが実情です。
また、一人親方と呼ばれる個人事業主の職人は、労働者としての法的保護を受けにくいため、賃上げの恩恵を受けづらい状況にあります。
こうした構造的な問題に対処するため、国や自治体は元請企業に対して下請契約における適正価格の確保を求めています。
さらに、技能労働者への処遇改善を条件に評価点を加算する仕組みも導入されつつあります。
長年の慣習として固定化されてきた構造の是正は容易ではありませんが、業界全体で取り組まなければ持続的な人材確保は困難です。
賃上げが進むためには、この構造改革が不可欠な課題といえるでしょう。
物価高騰と生活維持のための賃上げ圧力
近年の物価上昇は、建設業界の賃上げを後押しする要因となっています。
エネルギー価格や資材費の高騰により、建設コストは上昇し、同時に従業員の生活費負担も増加しています。
実質賃金が低下すれば、労働者の生活水準は下がり、人材の流出につながる恐れがあります。
こうした事態を避けるため、企業はベースアップを含めた賃上げを行い、従業員の購買力を維持する必要があります。
特に若年層の労働者にとって、生活の安定は就職先を選ぶ大きな基準です。
物価高の影響で可処分所得が減少する中、魅力的な給与体系を提示することは採用活動における重要な差別化要素となります。
さらに、賃上げは消費拡大にもつながり、結果的に経済全体の循環を促進する効果も期待できます。
建設業界が他産業に遅れを取らずに人材を確保するためにも、物価高騰を踏まえた賃上げは不可避な動きとなっています。
政府による賃上げ支援策(総合評価落札方式・賃上げ促進税制など)
政府は建設業界の賃上げを後押しするため、さまざまな施策を打ち出しています。
その代表例が、公共工事の入札において用いられる総合評価落札方式です。
この方式では、賃上げや処遇改善に取り組む企業を高く評価し、落札の可能性を高める仕組みを導入しています。
これにより、企業は競争力を維持するためにも積極的に賃上げに取り組むインセンティブを得ています。
また、賃上げ促進税制も重要な政策のひとつです。
これは、一定水準以上の賃上げを実施した企業に対して法人税の控除を行う制度であり、特に中小企業にとっては大きな支援となります。
さらに、下請業者への適正価格転嫁を促すガイドラインの策定も進んでおり、業界全体で賃金改善が広がるような仕組みづくりが進行中です。
こうした施策は、建設業における構造的な問題を補完し、持続的な賃上げを後押しする役割を果たしています。
主要建設企業における2024〜2025年の賃上げ事例
2024年から2025年にかけて、建設業界の大手企業は積極的な賃上げに踏み切っています。
背景には人材不足や若手確保の必要性があり、各社が異なるアプローチで従業員処遇の改善を進めています。
ここでは代表的な企業の具体的な取り組みを紹介します。
竹中工務店のベースアップと初任給引き上げ
竹中工務店は2024年に大幅なベースアップを実施し、さらに初任給の引き上げも発表しました。
特に注目されるのは、新卒採用における待遇改善です。
従来よりも高い給与水準を設定することで、他業種と比べて魅力的な労働環境を提供し、優秀な人材の確保を目指しています。
加えて、既存従業員に対しても一律の賃上げを実施することで、社内全体のモチベーション向上を図りました。
また、竹中工務店は労働環境の改善とキャリア形成支援にも注力しており、賃金面と働き方の両面から魅力を高める戦略を取っています。
これにより、建設業界にありがちな「長時間労働・低賃金」というイメージを払拭し、若手人材の流入促進につなげています。
こうした取り組みは、2025年にかけて業界全体の給与水準を押し上げる要因のひとつになると考えられます。
大成建設の平均6%超の賃上げ実績
大成建設は2024年の春闘において、平均6%を超える賃上げを実現しました。
これは大手ゼネコンの中でも高水準の取り組みであり、従業員一人ひとりの生活安定を重視した姿勢が表れています。
特に、物価高騰や生活費上昇の影響を考慮し、実質賃金の確保を目的とした点が特徴です。
同社は人材の定着率向上を重視しており、給与改善だけでなく福利厚生制度の充実も同時に進めています。
例えば、住宅手当や子育て支援策の拡充など、ライフステージに応じたサポートを強化することで、従業員が長期的に働ける環境づくりを推進しています。
平均6%超という水準は業界全体に強いインパクトを与え、他社にも賃上げの流れを広げる役割を果たしました。
結果的に、大成建設の取り組みは、2025年の賃金動向に大きな影響を与えると見込まれています。
清水建設・鹿島建設の若手層重視の処遇改善
清水建設と鹿島建設は、特に若手社員や中堅層の処遇改善に重点を置いた賃上げを進めています。
清水建設は2024年に若手層を対象としたベースアップを実施し、将来の幹部候補人材の確保を狙っています。
これにより、若手が安心してキャリアを積み重ねられる環境を整え、定着率向上を目指しました。
一方、鹿島建設は若手社員の給与水準を引き上げると同時に、働き方改革を推進しています。
具体的には、労働時間の適正化や研修制度の拡充などを行い、賃金面とキャリア形成を両立させる戦略を取っています。
このような施策は、建設業界に不足している若年層の参入を促し、技能継承を円滑にする効果が期待されています。
清水建設と鹿島建設の事例は、単なる給与改善にとどまらず、将来を見据えた人材戦略として注目されています。
西松建設による10%超の賃上げ表明
西松建設は2024年に10%を超える賃上げを表明し、業界内外に大きな衝撃を与えました。
これほど大幅な引き上げは異例であり、労働市場における競争力強化を狙った大胆な取り組みといえます。
背景には、人材不足の深刻化と中堅社員の流出防止があります。
高水準の給与改善によって、優秀な人材の流出を防ぎ、さらには他業界からの人材獲得も視野に入れている点が特徴です。
また、西松建設は賃上げに加えて教育・研修制度の拡充も進めており、従業員がスキルアップできる環境を整えています。
これにより、単に賃金を上げるだけでなく、長期的に成長できる職場を提供する姿勢を示しています。
10%超の賃上げは短期的なインパクトが大きいだけでなく、業界全体に「賃金水準を底上げする必要性」を突きつけた事例として高く評価されています。
建設業の賃上げに伴う課題と解消への動き
建設業界では賃上げの動きが加速していますが、その一方で解決すべき課題も多く存在します。
特に、多重下請け構造や労働環境の厳しさ、人材不足といった構造的な問題が浮き彫りになっています。
ここでは、課題とその解消に向けた取り組みについて解説します。
多重下請け構造の見直しと現場作業員の待遇改善
建設業界に根強く残る多重下請け構造は、賃上げを妨げる大きな要因の一つです。
元請けから下請け、さらに孫請けと複数層にわたる構造により、利益が分散し、現場作業員の給与改善に十分反映されない状況が長年続いてきました。
この問題を解決するために、国や自治体は「適正な工期設定」や「公契約条例」の導入を進め、元請け企業に対して下請け業者への適切な利益配分を求めています。
さらに、企業側も自主的に下請け契約の透明化や直接雇用の推進を進める動きが見られます。
現場で働く技能労働者の待遇改善を実現するためには、構造全体の改革が不可欠です。
今後は、元請け企業の責任が一層問われ、現場に従事する労働者が安心して働ける環境づくりが求められています。
労働環境の改善と福利厚生の充実
賃上げが行われても、労働環境の改善が伴わなければ、人材の定着は難しいのが現状です。
建設業界は長時間労働や休日の少なさが課題として指摘されてきました。
これに対し、各社は時間外労働の削減や完全週休二日制の導入を進めています。
また、福利厚生面の充実も重要な要素となっています。
例えば、住宅手当や資格取得支援制度、育児・介護支援といった制度を導入することで、多様な働き方に対応し、従業員のライフステージに合わせたサポートを行う企業が増えています。
さらに、健康経営を掲げ、メンタルヘルスケアや現場の安全対策を強化する動きも広がっています。
単なる給与の増額だけでなく、労働環境全体を改善することで、建設業界の魅力を高め、若手人材の流入を促すことが可能になります。
人材確保に向けたベースアップと初任給強化
建設業界における人材不足は深刻であり、特に若手層の確保が急務です。
そのため、多くの大手企業はベースアップと初任給の引き上げを積極的に実施しています。
ベースアップによって全体の給与水準を底上げすることで、既存社員のモチベーションを高めつつ、初任給の改善により新卒採用における競争力を高めています。
| 企業名 | ベースアップ率 | 初任給の引き上げ額 |
|---|---|---|
| A社 | 5% | 20,000円 |
| B社 | 7% | 25,000円 |
このように具体的な数値を掲げることで、学生や転職希望者にアピールしやすくなります。
また、給与だけでなく教育研修制度の充実もセットで行うことで、将来性のある職場であることを示すことができます。
今後も人材確保のためには賃金と教育の両輪による戦略が欠かせません。
2025年以降の建設業界における賃上げ動向
2025年の賃上げは一つの節目にすぎず、その後も建設業界では人材不足や物価高騰への対応を背景に賃金改善の流れが続くと予測されます。
ここでは、地域や中小企業への波及効果、人材確保と生産性向上の取り組み、そして企業の競争力維持との関係について詳しく解説します。
地域企業や中小企業への波及効果
大手建設企業が率先して賃上げを行うことで、その動きは地域に根差す中小企業にも広がりつつあります。
これまで中小企業は利益率の低さから賃上げに慎重でしたが、大手が水準を引き上げることで、優秀な人材が流出する懸念が強まり、賃上げを避けられない状況になっています。
特に地方においては公共工事の比率が高いため、国や自治体による設計労務単価の引き上げが、地域企業の賃上げを後押ししています。
さらに、建設業界の下請け構造において、元請けの賃上げ方針が下請け企業の給与改善に反映されやすくなってきました。
これにより、地域経済全体への波及効果も期待されます。
ただし、中小企業は資金力や人員体制に限界があるため、持続的な賃上げを行うには経営改善やデジタル化といった生産性向上策を同時に進める必要があります。
人材確保と生産性向上のための取り組み
賃上げは人材確保の有力な手段ですが、それだけでは限界があります。
建設業界は長時間労働や厳しい現場環境が敬遠されがちであり、給与改善に加え、働き方改革や生産性の向上をセットで実現しなければ人材不足を解消できません。
各企業はICT建機の導入やBIM/CIMの活用により現場作業の効率化を進めています。
これにより少人数でも高い生産性を実現し、賃上げの原資を確保する仕組みを作ろうとしています。
また、週休二日制の定着や残業時間削減に取り組む企業も増えており、給与と働きやすさを両立させることで若手や女性の参入を促しています。
このように、賃上げと生産性向上は相互に関係しており、技術革新と人材戦略を並行して進めることが業界全体の持続的成長につながります。
賃上げと企業の競争力維持の関係性
建設業における賃上げは単なる人件費増加ではなく、競争力維持のための重要な投資と位置付けられています。
人材不足が慢性化する中、賃金水準が低い企業は優秀な人材を確保できず、結果として工事の品質や受注力に影響が出る可能性があります。
逆に、積極的な賃上げを行う企業は人材定着率が高まり、長期的には競争力を高めることにつながります。
| 項目 | 賃上げに消極的な企業 | 賃上げに積極的な企業 |
|---|---|---|
| 人材確保力 | 低下傾向 | 安定・強化 |
| 生産性 | 現状維持〜低下 | 向上が期待 |
| 競争力 | 縮小傾向 | 強化される |
今後、賃上げは企業規模を問わず避けられないテーマであり、それをいかに経営戦略に組み込むかが業界で生き残る鍵となります。
まとめ
今回の記事では、建設業の賃上げについて解説しました。
賃上げは人材確保や競争力維持に不可欠ですが、持続可能な経営には生産性向上や働き方改革も並行して進めることが重要です。
ぜひ自社の課題を見直し、早めに取り組みを始めましょう。